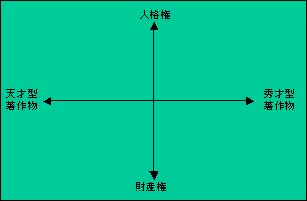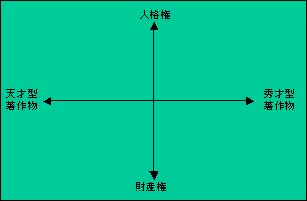著作権をとらえなおす(その1)
昨今の著作権関連の訴訟を見ていると、欧米での著作件に関わる事案とは、その係争点や落としどころが、かなり異なっているコトが多い。このアタりには、日本特有の著作権をめぐる事情が絡んでいる。日本においては、欧米で著作権の概念が成立するはるか以前から、今でいう著作権に相当する権利や、それをビジネスに利用する上での契約関係など、独自の権利体系が確立していた。
それは、そのような権利関係が、世界最初の商業複製美術たる「浮世絵」ビジネスの隆盛とともに確立したからだ。浮世絵を印刷し出版するまでには、原画を描く作家や、版元、彫りや刷り関わる職人といった、多くの人々が関わっている。ビジネスの規模が拡大し、関係者が多くなればなるほど、それらの人々の間で売上をどう配分するか、という問題がおおきくなる。
従って、このような中から、基本的なルールや個別の契約関係ができあがってきた。著作権のことを別名「版権」というのは、まさに、この「浮世絵の版」にまつわる権利が起源であることそ示している。これだけでなく、今でも著作権関連の用語の中には、浮世絵業界の用語にルーツを持つコトバが多く残っている。このような、独特の権利関係やビジネス上の契約関係が存在していた以上、単に「著作権」といっても、その指し示す中身は、欧米のそれとイコールではないのも当然だろう。
歴史は大事だし、伝統は大切にしなくてはいけないのは当然だが、発想そのものが伝統にとらわれ過ぎてしまっては問題だ。ましてや、著作権が著作物という、クリエイティビティーの所産を扱うものである以上、歴史と伝統の中だけで解決できない要素を必然的にはらんでしまう。そのワリに、日本の著作者の多くにとっては、著作権のあり方自体が、浮世絵以来の伝統から抜け出せていない。これでは、著作権を活かす発想はでてこない。
この問題がどこにあるかを知るためには、まず問題の構造から考える必要がある。一口に著作権といっても、著作物をめぐる権利のあり方は一様ではなく、いろいろな面がある。これを整理して考えなくてはいけない。権利のあり方については、大きく分けて、権利そのもののあり方と、著作物のあり方の両面において違いをとらえることができる。まず、「権利のあり方」だが、これについては、著作権法自体の中で規定されているように、人格権と財産権とという二つの面がある。
財産権を担保するには、人格権の一部である「氏名表示権」が前提となっているなど、両者は密接な関係にある。しかし著作者の側からすると、どちらの権利がより重要になるかは著作物のあり方により大きく変ってくる。著作物には、人格権が重要になるタイプの著作物と、財産権が重要になるタイプの著作物がある。したがって、著作者にとって一義的に主張したいのはどちらの方か、という視点から、「財産権対人格権」という軸を一つ設定することができる。
たとえば、フリーソフトウェアを考えるとわかりやすい。フリーソフトの作者にとっては、そのソフトから得られる収益より、そのフリーソフトがデファクトスタンダードのツールとなることにより得られる、作者としての名声や技術に対する評価の方が重視される。だからこそ、財産権は放棄しても、作者としてのアイデンティティーを担保する人格権だけはキープし、作者不明の公共財たる「パブリックドメイン」とはしないのだ。
一方著作物の性格には、本質的な構造の違いがある。著作権法においては、本質的に性質の違う著作物について、権利という面からひとくくりにして、「著作権」として扱おうとしている、と言ったほうが正しいだろう。著作物の違いは、著作者が著作物を生み出すプロセスの違いに帰することができる。その一方の極は、いわゆる芸術作品的な著作物である。もう一方は、学術論文やデータベース的な著作物である。
前者を「天才型著作物」、後者を「秀才型著作物」と呼べば、「天才型対秀才型」という軸が設定できる。絵画や楽曲などは前者である一方、プログラムや論文などは後者に分類できる。天才型著作物の作成プロセスは、才能ある特定の人間のアタマの中でブラックボックスになっている。秀才型著作物の作成プロセスは、しばしばそれらが共同著作物として作られることからもわかるように、作成に関わった個々人からすると外在化している。映画などは共同著作物ではあるものの、個々人の内部的ブラックボックスに依存する部分もあるため、両者の中間に位置付けられるだろう。
一見同じような「著作物」でも、著作者からすると「天才型」か「秀才型」か分類可能なものもある。たとえば旧国鉄の往年のSL「C62型」をテーマにした写真集でも、一人のカメラマンが各地のC62型の力走を捉えた迫力ある写真を集めた写真集なら「天才型著作物」だが、C62の1号機から49号機まで、全機の時代別の変遷をデータベース的に集めた写真集なら「秀才型著作物」といえる。
この2軸を用いると、図1のように各象限に合わせ、四つの著作物との関わり方を分類できる。次回はこの4象限をベースに、日本の著作権観の問題点を探ってみよう。
図1
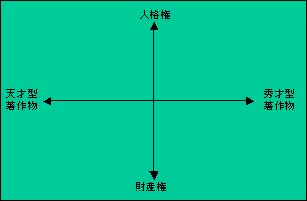
(05/03/18)
(c)2005 FUJII Yoshihiko
「Essay & Diary」にもどる
「Contents Index」にもどる
はじめにもどる