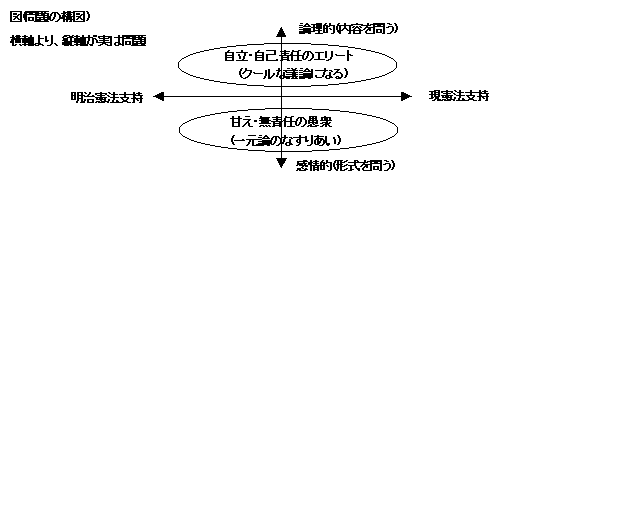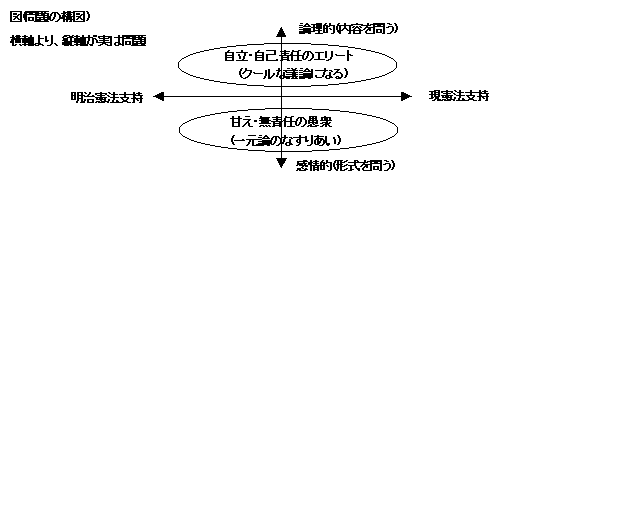教育勅語に関する考察
1.「勅語」の時代背景
教学聖旨(明治12年):
教育令以降の地方における教育の混乱を、「天皇御親政運動」により乗り切ることを目指した文章(非公開)
軍人勅諭(明治15年):
軍事教育上の軍令としての倫理基準を、軍隊に対し超法規的(統帥権)を持つ天皇の言葉として示したもの
大日本帝国憲法公布(明治22年):
日本を近代的な立憲君主国家として、体制基盤整備する方向が確立
徳育涵養の義に付き建議(明治23年):
地方における自由民権運動の興隆に対抗し、立憲体制にふさわしい倫理基準を求める、地方長官会議での決議
以上のような経緯から、教育勅語は「大日本帝国憲法に基づく立憲政体としての日本と、そこにおける天皇制にふさわしい倫理基準と教育思想を、天皇と臣民がともに誓うもの」として作成された。大日本帝国憲法において重要なポイントは、超法規的なのは「万世一系の国体」であり、それをよりどころに、法的な規定として「大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す(第一条)」という天皇の存在が規定されている点にある。これゆえ、大日本帝国は「近代における立憲君主国」というその地位と天皇制との折り合いをつけることができた。したがって教育勅語は、「大元帥からの軍令」として出された「軍人勅諭」のように無媒介に超法規的な天皇からの諭旨ではなく、あくまでも大日本帝国憲法に基づき、「まず何よりも「明治憲法」の条文、さらにはその条文を成り立たせている原理・精神と、厳密に整合する」(「天皇と日本の近代化」八木公生)ものでなくてはならなかった。
このため勅語の内容は、「教育勅語のような一つの短い文章が強烈な印象を与えたことは、国際的にも稀有な例」(「日本近代思想体系6「教育の体系」」岩波書店)であるとともに、今も一種の吸引力を持っている文章であり、あの家永三郎氏をして「頗る普遍性豊かにして近代的国家道徳を多分に盛った教訓」(「教育勅語成立の思想史的研究」)と評価せしめたものとなった。これは「君主が臣民の良心の自由に干渉」する恐れのある「一の国教の建立」の危険性を徹底的に排除したゆえに可能になった。従来の勅語観は、その内容や語られている思想・倫理に対する肯定・否定を問わず、「成文化された勅語の内容」ではなく、その影響を含めて、この文章をめぐって外部的に行われた儀礼や荘厳の呪縛から逃れていないところに問題がある。
2. 「勅語」を生んだ構造
大日本帝国憲法が公布された明治20年代初頭は、幕末から明治維新を経て、復古主義から文明開化まで、多様な思想が林立していた時期である。その中で徳育など倫理・教育をめぐる思想基盤として社会的影響力の大きいものは、次の3つがあった。
(1)欧風主義
英米独仏など、日本の法体系を作る上で参考にした諸外国の法体系の中に含まれる倫理規定を輸入する形で徳育体系と作ろうとするもの。法体系としての整合性はいいが、キリスト教的倫理主義に基づいている点が難点。外国留学組の若手官僚層に支持が多い。
(2)漢風主義
当時としてはもっとも伝統的だった、江戸時代の倫理観である儒教的な倫理観に基づく徳育体系を目指すもの。厳密には、日本的儒教は正統派の儒教からはかなり変形しており、実質は幕府の官学主義といえる。幕臣等から転進したベテラン官僚層に支持が多い。
(3)和風主義
平安時代以降の公家社会における伝統的な天皇のあり方である、「うしはく」ではなく「しらす」統治(力による領有ではなく、精神的なよりどころとしての存在)に、倫理的な支柱を求めようとするもの。維新の元勲等、ベテラン政治家層に支持が多い。
大日本帝国憲法による立憲主義自体が、これらの3つのどれにも加担しない、中立かつ超越的な政体の樹立を目指したものである。当然教育勅語もその思想の延長上に作られた。
この一連の作業は、実質的には井上毅によっておこなわれた。具体的には、
1.欧風主義に対しては、欧米的な法体系にのっとった「政令」としての勅語の内容と位置付けを取り入れる
2.漢風主義に対しては、君臣の「忠」を優先させる日本的儒教ではなく、親子の「孝」を優先させる元来の儒教精神を強調することで牽制を図るとともに、武家社会的な制度ではない、本来の天皇のあり方との整合性を図る
3.和風主義に対しては、「統治者ではなく秩序の体現者であり象徴」という公家社会的な天皇のあり方と、近代立憲君主制における皇帝のあり方との類似性を利用し、立憲君主国の精神的支柱としてこれを取り入れる
ことにより、近代的な倫理基準として、立憲政体にのっとった「勅語」を作ることに成功した。これはまた、和歌の勅撰が天皇の統治に欠かせなかった、大陸の皇帝とは違う天皇制の「冶す(しらす)」アイデンティティーを、西欧的な「君臨するが支配しない」立憲君主主義とオーバーラップさせ、「孝」をキーワードとする儒教の精神で色付けするという、明治期の政体のあり方を具現化するものでもあった。
3.「勅語」をとりまく問題点
(1) 成立過程における問題点
大日本帝国憲法および教育勅語が、欧風、漢風、和風のバランス、もしくは妥協の上に作られた事実は、その成立プロセスにも反映している。「徳育涵養の義に付き建議」に対して作成された文案も、実際にその3つの流れを汲む3つのパターンがあった。
文部官僚である中村正直による文部省案は、欧風主義に基づく、欧米の法体系に込められた倫理基準を元としていた(井上毅は「洋風の気習」と批判)。
侍講である元田永孚による「教育大旨」は、漢風主義に基づく、日本的儒教主義を元にしていた(井上毅は「漢風の口吻」と批判)
それらの並列する意見を統合する形で、それぞれの文章や文言の要素を取り入れる形で、井上毅が「真成なる王言の体」たるべき文章として、和風主義=立憲主義の立場からまとめたものが、最終稿の教育勅語であり、こういうプロセスを経た分、観念度、抽象度が高く、そこに玉虫色の解釈が入る余地があったことは否めない。
(2) その公布形式における問題点
井上毅は教育勅語の策定にあたり、学習院または教育会において、演説の体裁で公布されることを念頭においていた。しかし、実際には文部大臣に文章として下賜され、大臣をして全国一般に訓令を出すという、政令に準じる形で世に広められた。このため、元来は「天皇が、徳のある臣民とともに、明治国家にふさわしい倫理基準を作ってゆこう」という「自力救済的」宣言であったものが、それにすがれば徳の道に近づけるという「他力本願的」な倫理基準となる道を開いた。
(3) 成文法的形態を取ったがゆえの問題点
欧米にける成文法といえども、その程度はさておき、それを支える慣習法的要素があってはじめて運用可能なものである。明治期の日本への欧米法の輸入は、あくまでも成文法的なところにとどまり、慣習法的規定を成文化したり、日本の慣習法との整合性を図ったりという、厳密な運用のための土壌作りは不充分であった。
このため、公布と同時に当初の理念は忘れられ、その場その場で都合のいい「我田引水」型解釈、あるいはマッチポンプ的な政令等による詳細規定で運用されることが多く、これがその後の歴史に痛恨を残すことと成る。教育勅語は観念的、抽象的で、玉虫色の解釈が可能なだけでなく、内容とは関係ない「ご利益期待」型の公布形式もあいまって、過剰な影響を与えることとなった。
4. 「勅語」論議の構図
(1) 内容と形式、二つの勅語観
内容は極めて普遍的で優れていたが、あまりに高尚な文章であり、正しい理解のためには高い教養が必要とされ、多くの国民にとっては真意は理解不可能であった。このため、ある種の「紋所」「免罪符」として、宗教的に形式の神聖さが重視され、日本人の宗教観ともあいまって、内容とはかけ離れた「意味性」を持つに至った。これは、「般若心経」を写経や読経する人は多いが、その説く内容自体をきちんと理解している人がほとんどいないことと、構造的によく似ている。
結果「教育勅語」を含む明治憲法体制の「宗教化」の中で、内容とはうらはらに、「甘え・無責任」を転嫁するよりどころを求めていた「大衆」の心の故郷となった。この「形式の宗教化」は、戦後の「日本国憲法・教育基本法」への帰依と、全く構造を一にするものであり、「憲法論」「勅語・基本法論」がその内容ではなく、あくまでも形式(マッカーサーが制定)に拘泥する理由でもある。
(2) 戦前・戦後の一貫性
和辻哲郎が語ったように、日本国憲法の「日本国民統合の象徴」という規定は、日本の歴史を一貫して流れる「治らす(しらす)」存在としての天皇のあり方を的確に表現しているものであり、国事行為へのかかわりも含め、内容的には「近代立憲君主国」のあり方として、明治憲法の規定と強い一貫性を持つ。「自立・自己責任」に基づく行動がとれる「近代市民」を前提に考えるのなら、「明治憲法・教育勅語」体系も「日本国憲法・教育基本法」体系も、「近代立憲君主国」の基本規定としてはそれほど異なるものではない。
明治期においては、「自立・自己責任」の近代市民たる「エリート層」よりも、「甘え・無責任」の愚衆であっても、急速な近代化推進の原動力になる「近代大衆」の大量生産が不可避であり、市民社会の確立を待たず強力な大衆社会化が推進された。この順序の取り違いが、のちに大衆がその「数」により力を持ち、エリートがその中に埋没するという、戦前の日本の悲劇の引き金となった。この構図は、戦後も一貫して引き継がれており、現在我々が抱えている社会的な諸問題も、その原因は「甘え・無責任」を許した「大衆創出」と、そのゆきつく先としての「40年体制」に求められる
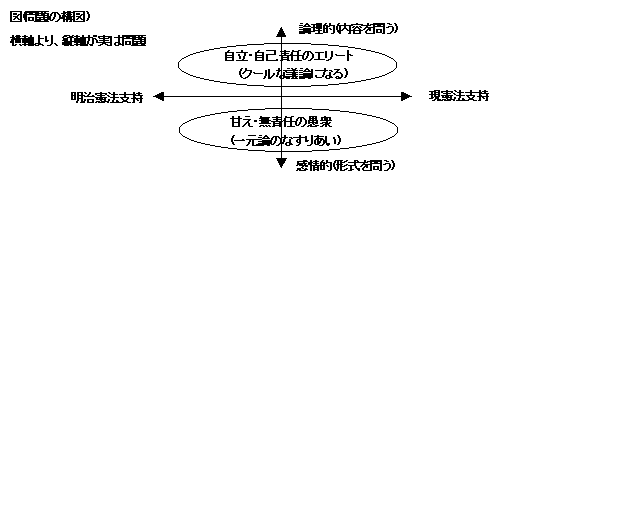
(06/08/11)
(c)2006 FUJII Yoshihiko
「Essay & Diary」にもどる
「Contents Index」にもどる
はじめにもどる