トップページに戻る

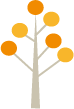
近親者を亡くした人々のグリーフ過程を理解し援助するための手引き
(心理援助の専門家・医療関係者向け、文責:田村智英子)
以下のまとめメモは、この本から学んだ内容です。
Grief Counseling and Grief Therapy: A Handbook for the Mental Health Practitioner, 3rd edition
J. William Worden. Springer Publishing Company, NY, USA 2002
※ 2008年にこの本の第4版が出版されています。翻訳本( 『グリーフカウンセリング:悲しみを癒すためのハンドブック』鳴澤實(監訳)/大学専任カウンセラー会(訳)、川島書店 1993年)もあります。ただし、第2版の翻訳であり、参考になりますが、その後の英語の版ではかなりの追記、章立ての変更があります。
ウォーデンは、私たちのグリーフ心理過程を理解し支援するための理論として、歴史的に大きな意味をもつキュブラー=ロスなどの知見を踏まえ、また自身が集めたデータを元に、わかりやすい体系をまとめました。ウォーデンの4つの課題を柱とする理論は、専門家にも一般の人々にもわかりやすく、私たちが自分自身の気持ちを振り返るために利用しやすいものとして、欧米で広く知られるようになりました。私たちは2003年より有志で集まってウォーデンの教科書をもとに毎月のグリーフ・ワークと支援の勉強会を行っていますが、その中でも、ウォーデンの理論は心理支援のベースとして大変有用だと感じています。
目次
1.アタッチメントと喪失から理解するグリーフの基本
2.通常のグリーフ反応
3.抑うつ状態のチェック
4.ウォ−デンが提唱している4つのグリーフ課題(タスク) ←重要!
5.グリーフを修飾する因子
6.グリーフ・カウンセリングの原則
7.グリーフ過程の支援に役立ついろいろな方策
1.アタッチメントと喪失から理解するグリーフの基本
- グリーフは、悲哀、悲嘆と訳すことが多い。
- グリーフは、愛着(アタッチメント)のある対象との絆の喪失時、あるいは、喪失する可能性が強い状況においてみられる心理的反応プロセスとして理解され、モーニング・ワーク(喪の作業)が始まる。
- 死別以外の喪失体験からも生じる反応である(身体の一部を失う、自身のアイデンティティを失う、心から大切にしていたものを失うなど)。
- 喪失体験の対象としては、アタッチメントが強い対象であれば、肉親でなくともよい。ペットや友人でも深い心理的な関わりがある対象であれば、グリーフ反応は生じる。一方、肉親であってもアタッチメントがない対象を喪失してもグリーフ反応は生じない。他人の死の話を見聞きしたり殺人事件を見たりすることで生じる。
2.通常のグリーフ反応
〜これらは正常な反応であることを理解し、伝える
感情面
悲しみ、怒り、罪悪感と自責、不安、孤独感、疲労感、無力感、ショック、思慕、解放感、安堵感、感情鈍麻
身体的感覚面
腹部の空虚感、胸部の圧迫感、喉の緊張感、音への過敏、離人感(道を歩いていても、まわりのものが自分を含めて現実と感じられない)、息切れ、筋力の弱さ、エネルギー・元気が感じられない、口の渇き
認知面
信じない、混乱、頭がいっぱいで気を取られている状態、故人の実在感、幻覚
行動面
睡眠障害、食欲異常、ぼんやりした行動、社会的引きこり、故人の夢、故人を思い出させるものの回避、探索と叫び、ため息、落ち着きのない過剰行動、泣くこと、故人を思い出す場所の訪問や品物の携帯、故人の持ち物を大切にする
3.抑うつ状態のチェック
第2項で述べた多くの事象は正常な心理的反応の範囲として理解できるグリーフであるが、喪失体験をした人の中には、一時的に抑うつ状態を示す人も少ないながら存在する。臨床的に明らかな抑うつ状態がみられた場合には(あるいは疑われた場合には)、精神科医、心理専門職などに対応を相談する。
抑うつ状態の兆候として、以下のようなことについて質問して確認する
- 睡眠の異常(眠れない、過眠)
- 食欲の異常(食べられない、過食)
- 気分の日内変動が激しい
- これまで楽しかったことが楽しくない、食べ物がおいしいと感じられない、など
4.ウォ−デンが提唱している4つのグリーフ課題(タスク) 重要!
- この4つの課題をこなしていくのがグリーフのプロセス。
- 課題をこなす順番は、順番どおりとは限らない、前後しても繰り返してもよい。(これがキュブラー=ロスの“段階”理論と違うところ。)
- 4つの課題をこなすには、通常2〜3年かかる。(少しずつ状況は変化はしていくが。)
第1の課題
喪失の事実を認める
第2の課題
グリーフに伴う様々な心理的「痛み」を味わっていく
第3の課題
故人のいない状況に心理的に適応する
- 内的な適応(自己観の変化や理解者がいなくなった状況に対する適応など)
- 外的な適応(仕事や家庭内の役割分担の変化など)
- スピリチュアルな適応(宗教観、世界観、人生観などの変化)
第4の課題
故人を情緒的に再配置し、上手に記憶にとどめながら、生活を続けていく
5.グリーフを修飾する因子
- 亡くなったのは誰であったか
- 故人との間のアタッチメントの状況(アタッチメントの強さ、アタッチメントの保証、関係のアンビヴァレンス(両価性)、故人との葛藤など)
- 死の状況(地理的距離、突然か予期できた死か、暴力的・トラウマティックな死、複数の死、防ぐことのできた死、はっきりしない死、社会的偏見を伴う死など)
- グリーフ経験者のこれまでの履歴(過去の抑うつ状態や心理的不適応の履歴など)
- グリーフ経験者のパーソナリティ(年齢・性、コーピングのスタイル、アタッチメントのスタイル、認知のスタイル、自我の強さ、信念や価値観などの世界観など)
- グリーフ経験者がおかれた社会的状況(周囲のサポートがあるか、周囲のサポートに満足できているか、グリーフ経験者のもつ社会的役割、社会的資源、グリーフ経験者が属している集団からの社会的な期待など)
- 併発的事項(同時に他の死別を経験したり職を失うなど)
6.グリーフ・カウンセリングの原則
その人がどこまで4つのグリーフ課題をこなしているかを話し合いながら、4つの課題を(順番にこだわらわずに)終えることを目標とする。
注意:グリーフ・カウンセリングは、複雑化していないノーマルなグリーフに対する支援として実施する。複雑化したグリーフに対しては、専門職によるセラピーを提供することが望ましい。
グリーフ・カウンセリングの実際
- 遺された人が喪失を現実のものとして認められるように援助する(第1の課題)
- 遺された人が様々な感情を認め感じることを援助する(第2の課題)
怒り、罪悪感、不安、無力感、悲しみなど
- 故人なしに生きることを援助する(第3の課題)
- その人にとっての喪失の意味を見出すことを援助する(第3の課題)
- 故人に対する感情の再配置を促す(第4の課題)
- グリーフに時間を提供する(時間がかかってよいことを伝えることは大事!)
- グリーフの際の「正常な」行動について説明する(心理教育として一般論を伝える)
- 個人差を認める
- その人の防衛機制とコーピング・スタイルを検討する
- 精神病理的な状況(抑うつ状態など)を識別して他職種に紹介する
7.グリーフ過程の支援に役立ついろいろな方策
- 感情を呼び起こす言葉を意識的に用いる
- 象徴(シンボル)となるものを利用する
- 書くこと(手紙、日記など)
- 描くこと
- 亡くなった人になってみるなどのロール・プレイング
- 認知の枠組みを再構成する
- 思い出の記録を作る(アルバム、ビデオ、回顧録など)
- 比喩の活用
- Directed Imaginary(故人を思い浮かべるよう指示、エンプティ・チェアなど)
このページの最初に戻る
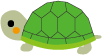

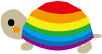
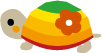

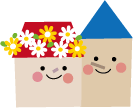 トップページに戻る メンタルケア・心理支援関連情報のページに戻る
トップページに戻る メンタルケア・心理支援関連情報のページに戻る
リンク、転載など自由ですが、その際は引用元を記していただければ幸いです。(田村智英子)
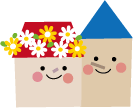 トップページに戻る メンタルケア・心理支援関連情報のページに戻る
トップページに戻る メンタルケア・心理支援関連情報のページに戻る