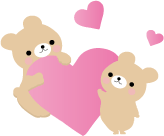
私は、「遺伝カウンセラー」である。といっても、現在日本にはそうした職種の免許は存在しないので、自称遺伝カウンセラーであることをお許しいただきたい。一応米国の正規の遺伝カウンセラー養成課程を卒業したので、米国では少しだけ胸を張れるが、それでも2000人以上も同種の人々がいる中では新米である。
遺伝カウンセラーという職業を知っている人はとても少ない。夜遅く病院から出てきてタクシーに乗ると「お客さん、今まで仕事だったの?じゃ、お医者さんか看護婦さん?」と聞かれる。「いえ、違います」の後が困る。「遺伝カウンセラーなんですよ」でわかる可能性は低いし、説明するのも簡単ではない気がしてしまう。「ある種のカウンセラーなんです」とごまかしてしまうこともあるが、試しに「遺伝に関係したことの相談にのるカウンセラーなんですよ」と言ってみることもある。そうすると案外話がはずみ、「がんっていうのはやっぱり遺伝なんですか」「最近は遺伝子で何でもわかるっていうじゃないですか」と質問攻めに合ったりする。遺伝性疾患の多くは比較的珍しい病気であるが、遺伝にまつわる話は一般の人々にとって割合身近な話題のようである。
先日、美容院で白髪隠しのヘア・マニキュアを施してもらった。大学で教えているということしか言っていなかったのだが、美容師さんと話していたら、「俺の目の形って親そっくりなんですよ、遺伝ですかね」とのたまう。笑いながら聞いていたら今度は洗髪をしてくれる美容師さんが「俺、髪の毛やばいような気がするんですけど、親はふさふさなんですよ、遺伝だったら俺も大丈夫ですよね」などと言う。いやはや、遺伝という言葉は本当に日常語のようだ。おそるおそる、「私、実はそういう遺伝の疑問に答える仕事をしているんですよ」と言ってみたら、「そんな仕事があるんですか」と驚いていたが。
日本にはこれまで、私のような医師ではない遺伝カウンセラーは存在しなかった。しかし、遺伝カウンセリングそのものは臨床遺伝専門医を中心に、看護師、臨床心理士なども加わって行われてきた。だから、日本に遺伝カウンセリングがなかったわけではない。留学する時、私はそれほど遺伝カウンセラーになろうと強く思っていたわけではなく、米国流のあり方を見てみたいという程度の気持ちだった。力試しのつもりで応募したフルブライト奨学金にたまたま合格してしまったので慌てて大学院の願書を出したら、日本人が珍しかったのか、1学年たった4人の枠に入れてもらえたのは幸いである。行ってみたら、その教育システムの充実度は並大抵のものではなかった。2年半の修士課程は言葉では表せないほど大変だったが、徹底的に知識とスキルをたたきこまれ、帰国する頃には、日本で最初の遺伝カウンセラーになる意気込みがすっかりできあがっていた。30代半ばを過ぎてから誰の後押しもなく留学すると言い出したとき、薬学部卒業以来勤めてきた製薬会社を辞めるなんて、帰ってきても就職は難しいのではと、多くの人が心配してくださったが、帰国後はそうした人々がまた心配して手を差し伸べてくださったことにとても感謝している。
現在私は、お茶の水女子大学の大学院に昨年出来た非医師の遺伝カウンセラーを養成する修士課程にて後進の指導にあたっている。同時に、いくつかの医療機関にて実際に患者様やご家族にお目にかかる遺伝カウンセリングにも従事している。新しい分野なのですべてが手探りであり、周囲の理解を得るのも大変で苦労は多いが、やりがいも大きくて毎日がとても楽しい。患者家族の皆様や遺伝医療に関わる様々な職種の医療者が、一緒に頑張ろうと言ってくださるのも本当にありがたい。
遺伝カウンセリングでは、遺伝性疾患や先天異常などについて心配や疑問を抱える方々に、医学的情報を提供し、心理的、社会的支援を行う。遺伝カウンセラーには、遺伝や遺伝子、遺伝性疾患に関する知識のほかに、心理学、カウンセリング理論、生命倫理学、医療制度の基本、遺伝に関係した国のガイドラインなどについての知識も欠かせない。その上で、これら複数の分野の知識を有機的に統合して実際の遺伝カウンセリングを行っていく。遺伝子解析研究が進み遺伝医療が大きく変化しつつある現代において、社会に生きる私たちの抱える課題は何なのか。遺伝カウンセラーの視点から、そうしたことを今後少しずつ述べて行きたい。
「遺伝カウンセリングって何ですか」という質問をしばしば受ける。先月のコラムでは「遺伝性疾患や先天異常などについて心配や疑問を抱える方々に、医学的情報を提供し、心理的、社会的支援を行う」と書いた。しかし、本格的に遺伝カウンセリングを定義しようと思うと、これはかなりやっかいである。
まず、「遺伝」という語の指す範囲が不明瞭だ。世の中の疾患すべてが遺伝、非遺伝ときっちり分けられるわけではなく、突然変異もあるし、遺伝かもしれないがよくわかっていない疾患もあれば、ある疾患になりやすい遺伝的要因を受け継いでいても発症したりしなかったりする疾患もある。同じ症状を呈する疾患の中に、遺伝性のものと遺伝でないものが混在している場合もある。どんな疾患でも遺伝子に関わる問題は広く遺伝カウンセリングで扱おうではないか、という意見も存在する。また、遺伝カウンセリングは英語で genetic counseling というのだが、厳密に「遺伝」を意味する hereditary という語とは異なり、genetic には「遺伝の」という意味だけでなくもう少し広く「発生上の」というニュアンスも含まれる。したがって、英米の genetic counseling では、遺伝であってもなくても、胎児や生まれた子どもの先天的な疾患について広く相談にのることが多い。その中には妊娠中の飲酒や薬物服用の相談も含まれることもある。
次に、「カウンセリング」という語の意味も曖昧である。心理職の行うカウンセリングは、カウンセリング理論に基づいた専門的な行為として知られている。しかし、化粧品やかつらのカウンセリングや英会話学校のカウンセリングというときには、相手に合わせた情報提供を指すことが多い。美容整形や不妊治療において、個々の患者のライフ・スタイルや希望を聞きながら治療の方法を決めていくことをカウンセリングと呼ぶこともある。
それでは、遺伝カウンセリングにおける「カウンセリング」という語は何を指しているのだろうか。実は、実施者側の解釈も様々で、医師の丁寧な説明で対応している場合もあれば、医師の説明後に看護師がゆっくり話し相手になっている場合もあるし、心理専門職が対応していることもある。来談される方々の意見も同じではなく、私が遺伝カウンセリングを行うと、「こういう情報提供って大事ですよね」という方もいれば「やっぱり心のケアが必要ですね」という方もいる。
一般的には、心理専門職のレベルまで至らないとしても、心理カウンセリングの理論やスキルが重視されていることは間違いない。私の恩師であるB.ビーセッカーは、「遺伝カウンセリングとは、遺伝学的情報を中心として動的に繰り広げられる心理教育的プロセスである。クライアントと遺伝カウンセリング実施者の間に確立された心理療法上の治療的関係の中で、クライアントが、医学的および確率的な遺伝学的情報を自分なりに受けとめ、自律的に決断していく姿勢を自ら促進し、さらに、時間の経過にともない状況に心理的に適応していく、そうした自身の能力を高めることができるように、支援する。」と述べている。しかし、米国に2000人以上いる遺伝カウンセラーの中には、ここまで心理カウンセリング重視でない人も多々いるし、どんなに心理カウンセリングを重視しても、遺伝カウンセリングにおいて正確で最新の医学的情報を適切に提供することは欠かせない。
こうして日々、遺伝カウンセリングの定義について悩んでいたら、米国で表現音楽療法を学んだ友人が『音楽療法を定義する』(ケネス・E・ブルシア著、東海大学出版会)という本を教えてくれた。人々に説明したり、行為の専門性や専門職のアイデンティティを明確化したりするためには定義が必要である一方、「音楽」と「療法」という曖昧な語から作られた音楽療法という概念を定義することが容易でないこと、しかしその議論を通して音楽療法とは何かという本質が見えてくることなどが述べられていて、遺伝カウンセリングの定義の議論とまさに合致する話と思わず膝を打った。
私の教える大学院では、修士1年の前期に「遺伝カウンセリング学」を学ぶが、その初回に「遺伝カウンセリングの定義」について話し合う。遺伝カウンセリングを定義することの難しさに関する議論を通じて、学生たちが遺伝カウンセリングの本質的な部分に触れることができればと思う。
遺伝の相談を受けていると、「うちはがん家系だ」という人が少なくない。がんは遺伝するのだろうか?
がんは、遺伝子の変化によって起こるが、多くのがんは遺伝ではない。遺伝子の変化が積み重なり、身体を構成している細胞のコントロールが乱れて、正常に機能しない細胞が無秩序に増えるようになった状態ががんである。この遺伝子変化は通常、親から子へ受け継がれた遺伝子上には存在しなかったものであり、生まれた後、身体の一部分で後天的に遺伝子が変化し、そうした変化が積もり積もってがんが発生する。したがって、身体の一部にがんが生じても、それ以外の部分にはがんに至るほどの遺伝子変化は生じておらず、精子や卵子にはがんになるような遺伝子変化は起きていないので、その人の子どもにそのがんが遺伝することはない。
がん予防の第一歩は、後天的な遺伝子変化を減らすことである。タバコを避けるといった努力は遺伝子が変化する機会を減らす。ところが実際には、ライフ・スタイルに気をつけても、ある程度の遺伝子変化は避けて通れない。どんな人においても後天的な遺伝子変化は時々起こっており、環境要因もあるが、特に理由がなくてもたまたま遺伝子に傷がつくこともある。人間の身体は遺伝子変化を修復するしくみも備えているが、年齢を重ねるにつれて、誰にでも起こりうる遺伝子変化が少しずつ積み重なっていくことは避けようがない。人類が長生きするようになり、遺伝子変化の蓄積が避けられない以上、現在の科学ではがんは防ぎようがない。現状では、たとえがんに罹ってもそれを早く発見し治療することで命を落とさず再び元気に暮らすことができるように、という方向で研究が進んでいる。
ところで、もしも多くのがんが遺伝ではないのなら、なぜ、がん家系と思われるような家系が存在するのだろうか。答は簡単、がんは珍しい病気ではないからである。日本人の死因のトップはがんであり、親族や知人にがんに罹った人が何人かいるのはむしろ自然なことである。
ところが、遺伝カウンセリングで家族や親族の病歴を詳しく聞いていると、中にはこれはもしかすると本当に遺伝かもしれないと思える家系に出会うことがある。冒頭で多くのがんは遺伝ではないと書いたが、実は、がん全体の約10%は遺伝性であるとされている。正確には、がんそのものが遺伝しているわけではないが、特定の種類のがんに罹りやすい体質が遺伝している。そうした体質を受け継いだ人々は、一般の人々に比べてがんに罹るリスクが高い。前述したように、がん家系に見えても遺伝ではないケースも多いので、遺伝かどうか見分けるのは専門家でないと難しいが、特徴として、遺伝の場合には、血縁者の中に似たような種類のがんに罹った人が複数いる、一般のがん患者に比べて若い年齢でがんを発症する、ひとりの人が複数のがんを発症する、などの傾向がみられる。
遺伝的にがんに罹りやすい体質をもつ人は、若い時から検診を受けるなど予防手段を講じることが大切だ。がんはもはや死の病ではなく、適切に対処すれば予防や治療が十分可能である。がんリスクが一般より高いと知ることはショックなことかもしれないが、遺伝性がん家系の人々は、知らなかったら手遅れで死んでいたかもしれない、わかってよかったと、事実を前向きにとらえていることが多い。また、遺伝性のがん家系においても全員に遺伝するわけではないため、自分に遺伝しているかどうかを確かめる遺伝子診断を受けることもできるようになってきた。ただ、がんに罹りやすい体質が遺伝していたとしても必ずがんになるとは限らないし、何歳でがんになるかは予測できない。がんを発症しやすい体質が遺伝していると知った上で、いつがんになるのか案じながら生きていくことは決して楽なことではない。こうした遺伝子診断を実施した場合にどのようなメリットとデメリットがあるのか、熟慮が必要だ。まだがんに罹っていない人が将来の疾患リスクを知るために遺伝子診断を受けるということは、これまでの医療では想定されなかった新しい領域である。十分な情報提供や検診の体制とともに、こうした遺伝子診断が人々におよぼす心理社会的影響も考慮した支援体制を整えることが重要である。
繰り返すが、がん家系に見えても、本当に遺伝性かどうか判断するのはプロに任せたほうがよい。がんに罹りやすい体質の遺伝や遺伝性のがんリスクを知る遺伝子診断について話し合うために、遺伝カウンセリングの果たす役割は大きい。
本年4月より、認定遺伝カウンセラー制度が正式に始まった。この制度は、日本遺伝カウンセリング学会と日本人類遺伝学会が協力して作り上げたものである。遺伝カウンセラー養成の専門機関として所定の要件を満たして認定された大学院課程を卒業した者、およびそれに相当する資格が認められた者は、認定試験を受験することができる。養成課程の認定も今年から始まり、私の教えるお茶の水女子大学を含め、初年度には7校が認定された。(田村事後補足:2010現在9校)今後、こうした課程で遺伝学やカウンセリング論の専門的な知識、技術を学んだ者が、少しずつ増えてくるであろう。こうした認定遺伝カウンセラーたちは、社会においてどのような役割を担っていくのだろうか。
前々回、遺伝カウンセリングを定義することの難しさについて述べた。どの範囲の遺伝性疾患、先天異常を含むのか、カウンセリングとしてどのような心理支援を行なうものなのか、厳密に定めることは難しいが、「遺伝カウンセリング」という語は徐々に広がりつつある。文部科学省、厚生労働省、経済産業省が合同で出している「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」や、経済産業省の「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン」になどにおいても、遺伝カウンセリングとその重要性は大きく取り上げられている。こうした指針においては、遺伝カウンセリングとは、対話を通じて、正確な情報を提供し、疑問に適切に答え、その者の遺伝性疾患等に関する理解を深め、遺伝子検査や遺伝子解析研究や遺伝性疾患、遺伝性の体質などをめぐる不安又は悩みにこたえることによって、今後の生活に向けて自らの意思で選択し、行動できるように支援、援助することであるとされている。
遺伝カウンセリングを行なう診療科領域は多岐にわたる。たとえば、小児科領域では、生まれた子どもが先天的に複数の症状を有する場合に、臨床遺伝専門医による疾患の詳細な診断に基づいて、その疾患に関する医学的な情報、遺伝性の有無、次の子に同じ病気がみられる確率や、今後の治療、医療的マネージメントの方法についての情報をわかりやすく説明し、理解を促したり、書籍やホームページなどの情報資源や患者家族会のような当事者団体をはじめとする社会資源の紹介も行なったりする。その子どもを取り巻く家族が、心理的に状況に適応していくことができるように必要に応じて簡単な心理カウンセリング的支援を行なう場合もある。
成人領域の遺伝カウンセリングとしては、先天的、遺伝的な疾患をもって生まれた子どもが大きくなった場合、あるいは、大人になってから発症するような疾患や、前回書いた遺伝性のがんなどの事例が考えられる。こうした状況の本人や家族に対して、疾患や遺伝に関する情報を提供し、心理的、社会的にも支援していく。現在は発症していない人が、将来自分が病気になる可能性を知るための遺伝子診断を受けるかどうか考える相談にのることもある。
産科領域の遺伝カウンセリングでは、これから生まれてくる子どもに、なんらかの病気がみられることを心配している人々に対応する。たとえば高齢妊娠の不安を抱えていたり、自身や家族のもつ病気が自分の子どもに見られる可能性があるのか知りたいと思っていたりする人の相談にのり、他の疾患領域と同様、情報提供や、心理的、社会的支援を行う。また、産科領域では特に、出生前診断や着床前診断、生殖補助医療などが話題にのぼることが多い。こうしたことは倫理的にも複雑な問題をはらんでおり、遺伝カウンセリングにおける適切な取り扱いのあり方が常々議論されている。そうした議論についてはまた別途述べたいと思うが、遺伝カウンセリングは曲がりなりにも「カウンセリング」としての要素を含んでいるので、出生前診断などを強く勧めたりしないのはもちろんであるが、同時に、頭から否定することもせず、十分で正確な情報を提供しながら、そうした事項をめぐる心理的、社会的側面についてじっくり話し合い、それぞれのクライエントに合った方向性をクライエント自身が選んでいくプロセスをサポートしていく。
このように、様々な疾患、診療科領域において遺伝カウンセリングのニーズがあると考えられている。これまで多くの医師、看護師、ソーシャル・ワーカーその他いろいろな医療者が、そうしたニーズにこたえるべく対応してきた。今後はその中に新たな職種として登場する認定遺伝カウンセラーも加わる。これら多数の職種が互いの専門性を活かして連携しながら、広く患者、家族を支えていく体制が整うことが期待されている。
遺伝カウンセリングでは情報提供と心理社会的支援を行なう、という表現をすることがあるが、心理社会的とはどういう意味かという質問をしばしば受ける。米国で遺伝カウンセリングを語る際には、psychosocial という単語を使うことが多く、J. Weil が著した代表的な教科書の表題も Psychosocial Genetic Counseling(Oxford University Press, 2000)となっているのだが、この psychosocial を「心理社会的」と訳しても、どうもしっくりこないと感じる人が少なくないようだ。
そもそも、日本語で「社会的」というと、外に出かけていって直面するような大きな集団との関係を指している感じがする。しかし、英語の social という語は、自分という個人より外側の広がりとその関係性すべてを指している。たとえば、ある人にとっての social background (社会的背景)といえば、就学、就労状況などだけでなく、家族の状況も含む。また、ある人にとっての social support system とはその人を身近で支えてくれる人々を指すので、近しい家族が含まれることが多い。
したがって、遺伝カウンセラーの行なう心理社会的支援のひとつは、個人だけでなくその人を取り囲む家族やまわりの人々も視野に入れてサポートすることである。たとえば、遺伝性疾患や先天異常をもって生まれた子どもがその子らしく生きていくことができるように、適切な医療を行なうだけでなく、その子どもの疾患や障害に対する両親やその他の家族、周囲の人々の受け止め方がその子の成長に大きく影響するという観点にたって、これらの人々が情報を理解し心理的に状況に適応できるように支援する。あるいは、出生前診断について決めかねている夫婦に対して、ふたりの間でじっくり話し合いができるようにきっかけを提供することもある。ひとりの人に対して遺伝カウンセリングを行なう際にも、その方の気持ちについてだけでなく、家族やまわりの人々と軋轢が生じていないか話し合ったり、学校や職場での状況について話し合ったりする。
こうした心理社会的なサポートは遺伝性疾患でなくても重要であるが、遺伝性疾患の場合はさらに、家族の中に遺伝的要因の保因者や患者が何人もいることがあり、このことが状況を複雑化しているため、個人だけでなく複数の人々を考慮することが欠かせない。たとえば、その家族に代々伝わる疾患が家族の中でどのように受け止められてきたかという家族の価値観が、個人の価値観に大きく影響している場合がある。あるいは、ひとつの家系において、遺伝した人、遺伝しなかった人が混在していて、互いに気を使ったり羨んだりしていることもある。
また、実務的なことがらとして、来談者に対し、その疾患の専門医を紹介したり、特定の遺伝子検査を行なうことができる検査機関を探したり、ひとつの疾患でたくさんの異なる診療科にかからなければいけない人ができるだけ円滑に必要な検査や治療をきちんと受けることができるようにコーディネートしたり、リハビリテーションや子どもの療育への橋渡しを行なったり、医療費の援助制度や福祉サービスを紹介してもらうようソーシャル・ワーカーと連携したり、というような仕事も、遺伝カウンセラーの大切な業務である。こうした事項は、疾患や疾患の可能性を有する人々が社会の中で少しでも生きやすくなるための方策であり、社会的支援といえよう。
一方、遺伝カウンセラーは、個人や家族に対して遺伝カウンセリングを行なう仕事とは別の形で社会に働きかけていく活動も行なっている。たとえば、一般市民に対して遺伝についての啓発教育を行なったり、患者家族会や医学関連学会における講演を通じて遺伝カウンセリングをめぐる状況について社会に訴えたりする。あるいは、当事者団体のアドバイザーとしてその団体の活動を支えていることもあるし、遺伝医療に関連した行政に携わる者や、遺伝カウンセラーの教育養成に従事する者もいる。
遺伝カウンセラーの仕事をしていると、私たち人間は、身近な家族や友人に始まって学校や職場、地域の人々や、趣味や病気が同じものどうしの仲間など、多くの人々と出会い、助け合ったり衝突したりしながら生きているとつくづく実感する。そして、個人個人の心理が互いに影響しあって、ひとりひとり複雑な心理社会的状況を形成している。このような状況におかれた人々に、少しでも質の高い「心理社会的な」遺伝カウンセリングを提供していければと願っている。
近年、疾患関連遺伝子が次々と明らかになり、遺伝子検査が疾患の診断に応用されるようになってきた。もちろん、親から特定の遺伝子を受け継いでも、その後のライフ・スタイルによって個人の身体的、精神的状況は多様な様相を呈するので、遺伝子で何もかも決まるわけではない。しかし、遺伝子検査は、ほとんどの場合採血だけで済むという簡便さも手伝って、急速な勢いで医療現場に取り入れられつつある。
遺伝子の検査とそれにともなう診断が臨床で用いられる時の目的は様々である。既に症状のある人に対して、症状をみただけでは複数の疾患の可能性があったり診断が不確かだったりする際に、特定の疾患かどうかをよりはっきり診断するために行なう場合は確定診断と呼ばれる。あるいは、将来病気にかかる可能性を予測するために、現在は症状を有していない人が疾患関連遺伝子の変化を持っているかどうかを調べる場合は、発症前診断と呼ばれる。また、保因者診断と称して、自身には症状がなくても、子孫が受け継いだ場合は疾患を発症する可能性がある遺伝子の変化をその人が持っているかどうか調べることもある。
こうした遺伝子診断は、医療の中も特殊なもので慎重に行なうべきと考えられており、実施に際しては遺伝カウンセリングを提供することが望ましいとされている。なぜ、遺伝子診断はそれほど特殊なのだろうか。
理由のひとつとして、遺伝子は通常、生涯不変であることがあげられる。血圧や血糖値の検査なら、検査値が悪くてもその後の治療やライフ・スタイルの改善により検査結果の好転が期待できる。しかし、親から受け継いだ遺伝子は生活習慣を変えても変化しないので、疾患関連遺伝子の異常がいったん見つかってしまうと、一生その事実を抱えて病気や発症リスクと向き合いながら生きていかねばならなくなる。治療できる病気であればまだよいかもしれないが、治療法の少ない疾患の場合はどうだろうか。
実際には、一般的な生活習慣病などの疾患に対しては、遺伝子検査で発症確率を算定することはまだほとんどできない。しかし、確実ではなくても、将来の疾患の可能性を示唆する結果が認められることはままある。こうした不確かな結果の解釈は非常に難しい。また、心理的な影響も否定できない。本人の心理的負担のみならず、遺伝子診断の結果、複数の血縁者の間で疾患関連遺伝子の異常を受け継いだ人と受け継がなかった人がいるとわかった場合、たとえば兄弟姉妹間などで軋轢や罪悪感などが生じることもある。
将来は、遺伝子によって、生涯にわたる様々な疾患の発症確率が予測できるようになるであろう。さらには、外見やいろいろな能力、性格、寿命などの予測もできるようになるかもしれない。そうした情報に基づいて、まだ病気になってもいないのに、結婚や就学、就労、生命保険加入などにおいて、差別的な待遇を受ける可能性も出てくる。兄弟姉妹間で遺伝的状況が違う場合に、養育や相続上の不公平を引き起こすかもしれない。
また、遺伝子や DNA は究極のプライバシーと呼ばれることがある( DNA 全体のうち特定の機能を担っている部分が遺伝子)。DNA や遺伝子はひとりひとり微妙に異なっており、これを調べることで個人の特定が可能だ。もちろん指紋と同様、DNA だけではそれが誰のものかはわからないが、その人の DNA 情報が過去に登録されていたり、所有者のわかっている髪の毛や体液などから得られた DNA や両親などの DNA と照合することができたりする場合には、ある DNA がその人のものなのか、かなりの確率で判別可能だ。こうした方法は既に事故で亡くなった方の遺体の確認や犯罪者の同定などに用いられている。DNA 親子鑑定も実施されて久しい。ちなみに、疾患の遺伝子診断など別の目的で親子の遺伝子を調べた際に、予期せぬ結果として父親と血がつながっていないことなどが判明することもあり、そうした際の情報の取り扱いは難しい。
このように、遺伝子診断には複雑な問題が絡むことが少なくない。したがって、その検査、診断がその人や家族にもたらすメリット、デメリットをよく話し合いながら、十分な情報提供、理解のもとでのインフォームド・コンセントが欠かせない。しかし、最先端の複雑な知識をわかりやすく説明することは容易でない上、遺伝子診断には研究的要素や不確かな事項も多い。一方で、患者・家族も医療者も、遺伝子という言葉に科学の進歩を感じて漠然とした期待を抱いていることが少なくなく、安易に検査に臨む傾向がある。こうした状況で、適切なインフォームド・コンセントのプロセスをふむために、遺伝カウンセリングが必要になるのである。
お断りしておくが、これは中絶の是非についての議論ではない。それはそれで大切な問題であるし、出生前診断や中絶をめぐる倫理的、社会的な問題については、別の機会にとりあげたいと思っている。しかし今回は、法律の解釈いかんによって生じうる心理支援上の弊害について述べたい。
法律関係の方々には釈迦に説法だが、我が国では刑法で堕胎罪が規定されている一方で、母体保護法にて、「妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」および「暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの」の2点が違法性の阻却の条件として定められ、いずれかに該当すれば、一定の要件を満たした上で、人工妊娠中絶が可能である。
出生前診断を受けなくても、妊婦検診の超音波検査などによって胎児の異常を指摘されることは珍しくない。先天異常の可能性が大きいと診断された後、妊娠22週未満であればカップルの希望に応じて中絶が実施されることがある。これらの中絶は、きっかけは胎児異常でも、母体保護法の文言に照らして、今後、身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれがあるという解釈のもとに実施されていると思われる。
それなら、胎児異常ゆえの中絶は法律の解釈上合法なのだろうか。医療現場の認識は必ずしもそうではない。たとえば、臨床遺伝専門医の研修では「胎児異常を理由とした中絶はできない」と教える講師が多い。中絶の説明の際に「本当は赤ちゃんの異常を理由とした中絶はできないので、あなたのケースは違法なのです」と話す産科医もいる。このように、胎児異常を理由とした中絶を実際には行なっていても、本来は違法と考えている医療者が少なくないようなのだ。
遺伝カウンセリングでは、「先天異常を有する子どもは産まないほうがいい」ともいわないし、「どんな子どもでも受け入れるべき」と説くこともない。あくまでも来談者が、自身の状況を自分なりに消化して自身の気持ちと向き合っていく過程をサポートし、そして何か選択肢がある場合には、その人なりに選択肢を選んで決断していく過程を支援する。したがって、もしも日本では胎児異常ゆえの中絶は違法で実施できないなら、そうした方向で遺伝カウンセリングを行うことは可能だ。すなわち、来談者が、胎児に異常があっても中絶できないという状況に心理的に適応していくプロセスを支援する。一方、胎児異常ゆえの中絶が可能なのであれば、その選択肢を選ぶのか選ばないのか、カップルが悩みながら決めていく過程を支援する。遺伝カウンセラーは、物事の是非を判断する立場にはないので、当事者が迷った末に自身の価値観にそって出した結論に対してはどんな結論でも支援していく立場をとりたいと思っている。
妊娠経過中に胎児異常が見つかった場合、その後の選択肢を考えるための材料として、診断の状況や予想される疾患に関する正確な情報提供が欠かせない。ショックに対する心理的なサポートが必要になることもある。既に超音波検査で胎児の様子を見たり胎動を感じたりしている場合もあり、妊婦、カップルの心理は複雑だ。いずれにしても中絶について考えるのは楽な作業ではない。しかし、カップルが一生懸命悩むことは大事であるし、迷って結論を出した方に対しては、少なくとも一生懸命悩み考えたことには誇りを持って欲しいと思う。中絶後の心理を考えた場合、罪悪感はゼロにはならないとしても、自分なりに考えて決めることは非常に大切で、不消化なままで決めたり、他人の意見に従って中絶を選んだりした場合には、中絶後の心理的ストレスが大きくなりがちだ。
ただでさえも重く難しい問題である中絶をめぐって、現場の医療者が中絶実施可能としておきながら、「でも本当は違法」と伝えることの心理的影響は少なくない。実施不可能なら不可能というほうがかえってましだとも感じる。産科医が、本当は違法かもしれないと思いつつ中絶を実施するジレンマの中で、カップルに「本当は違法なのだけれど」とわざわざ伝えがちな現状は、中絶の倫理的問題の議論とは別の次元で、心理的な弊害が大きい。こうした現状を、法律の専門家の先生にもぜひ知っていただきたいと思っている。
出生前診断とは、一般的に、胎児の疾患や症状の有無を妊娠中に検査、診断することを指す。羊水検査はその代表的な方法だ。胎児の周囲に存在する羊水とよばれる水の中には、胎児の皮膚の表面から剥げ落ちた断片など胎児由来の細胞が浮いている。そこで、おなかの上から超音波で見て胎児を避けながら細い針を刺し、注射器で羊水を少量抜いて、羊水中の胎児細胞の染色体や遺伝子などを調べる。他に、羊水そのものや、絨毛、胎児の血液などを採取する方法もある。さらに、妊娠中の胎児の検査という意味では、超音波検査も広義の出生前診断に含まれる。
超音波検査は胎児や母体に害を及ぼさないが、羊水や絨毛、胎児の血液などの採取にはリスクが伴う。たとえば羊水検査では、適切な時期に適切な方法で行っても、300回に1回度程度の頻度で、胎児には異常がなくても検査を行なったために流産などによって胎児が死亡することがある。したがってこうした検査の実施時には、胎児の親が、リスクの存在を理解した上で検査実施に同意する必要がある。
一方、リスクが少ない検査として知られているのが、母体血清マーカー検査である。妊婦から採血し母体の血中成分から胎児が染色体異常を有する可能性の確率を予測、算出する。安全性は高いが、胎児の細胞を調べてはいないので高い正確性は期待できない。この検査の曖昧な結果を上手に利用するのは難しく、説明にも時間がかかるし、確率情報に過ぎない結果を見て混乱する人も多い。こうした問題点に鑑み、この検査の安易な普及に歯止めをかけるべく、厚生科学審議会などの見解が出されている。もっと正確でかつリスクの少ない検査の開発を目指して研究が進んでいるが、ほとんどがまだ実用化の段階には至っていない。
ところで、もしもリスクが少なければ、あるいはリスクがあっても親がリスクを理解した上で検査を希望すれば、出生前診断の実施には問題がないのだろうか。出生前診断は、胎児の状態に合わせて適切な医療管理を行うために必要な検査として行なわれる場合もあり、こうした医療目的のものは、医療目的か否かの線引きが難しい部分もあるが、一般的に容認される傾向にある。しかし、治療や対処の手立てがない疾患に胎児が罹患しているか調べる出生前診断は、何のために行うのかが問題になる。何もできないとしても心の準備のために知っておきたいという親もいる。しかし知っておきたいという理由だけで、リスクのある検査を受けることが適当か、熟慮が必要だ。
それでは、疾患を有する胎児を選んで中絶するための出生前診断は認められるだろうか。調べる疾患や症状の種類や重篤度によっても状況が異なるので一概には言えないが、妊娠22週未満であれば中絶は実質的には可能であるし、出生前診断を禁じた法律はない。しかし、疾患や障害を有する胎児を生まれてくるべき存在ではないとして中絶することは、人が疾患や障害を持ちつつ生きていく権利を脅かす行為だとする意見や、親の考えで胎児を選ぶことに疑問を投げかける声は少なくない。一方、胎児はまだ人ではなく人権を持たないので、疾患や障害を持って生きている人の差別は禁ずべきだが胎児の段階では話は別とする意見もある。とはいっても、たしかに胎児は法的には「人」ではないが、単なる「物」であるとも言い難く、選択的中絶のための出生前診断を考えているカップルも、笑いながら満足して検査を受けているわけではなく、悩みながらの選択であることが多い。実際には、異常がないことを確認して安心したいと思って検査を受けるカップルも少なくなく、安心するつもりが予想外の結果を得てうろたえることもある。
出生前診断を全面的に禁止してしまえば話は簡単だが、現実的には多くの医療機関で検査が実施されている。そうした中で、高齢妊娠や遺伝性疾患の心配を抱えているカップルは出生前診断を受けるべきかどうか悩む。さらに医療者側も、検査を受けるようにとも受けないようにとも言えずに頭を抱えている。遺伝医学関連の10学会による「遺伝学的検査に関するガイドライン」では、出生前診断実施の条件を提示し、検査前の十分な遺伝カウンセリングが大事と述べている(註)。しかし、この問題を扱う際には、「遺伝カウンセリングを」と言えば済むものではない。遺伝カウンセリングは重要だが、そこで何をどのように話し合うかが非常に難しいのである。ここから先の話を、次回、じっくり論じてみたい。
(註)田村事後補足:2011年2月より、10学会のガイドラインは日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」となり、出生前診断に関しては日本産科婦人科学会の指針等を参照することとなった。
出生前診断に関しては様々な見解がある。診断結果によっては人工妊娠中絶という選択を視野に入れつつ行う出生前診断に対して反対する意見の代表例は、人は疾患や障害があっても生きていく権利があり胎児も同じとする考え方である。また、大事な決断を当人に代わって決める時にはその当人の最善の利益を考えて決めるべきだが、親の都合で中絶を決めるのは胎児の最善の利益になっているとはいいがたいので、親には決める権利がないのではとする意見もある。あるいは、産みたい気持ちがあっても、周囲からのプレッシャーや生まれた後の社会の受け入れに対する不安によって中絶を選ぶ人がいることも問題だとされている。病気や障害をもつ人を排除するのではなく、そうした人々が生きにくい社会のほうを変えていくべきという声もある。子どもの病気や症状の詳細について十分な情報が与えられないまま中絶を決める人がいることも指摘されている。医療者としては情報を提供しているつもりでも、急に胎児異常を告げられたショックで情報を消化する余裕がないのに、中絶可能な時期に制限があるために決断を急がされることも問題だ。
一方、親には出生前診断とそれに伴う選択的中絶を選ぶ権利があるという主張もある。いったんこの世に生を受けたのであれば社会として疾患や障害をもつ人を受け入れて支援していくことは大切だが、生まれる前に病気とわかった子どもを産むかどうかは親が決めてよいとする見解もある。あるいは、差別がゼロではない社会の現状では仕方ない選択肢だと認める声もあるし、当事者でない人が「産んで育てなさい」と親に強制することはできないという考え方もあるだろう。
出生前診断とそれに伴う胎児異常を理由とした人工妊娠中絶について考える際には、こうした生命倫理学的な議論を避けて通ることはできないが、その是非の判断は、疾患や症状の種類や重篤度、その家族の経済状況や社会的背景などによっても異なるとする考え方もあり、いずれにしてもすぐに結論が出るような問題ではない。
実は、私の思う遺伝カウンセリングでは、出生前診断に関するこうした生命倫理学的考え方を説くことはしない。こうした見解は一般論であって、個別のケースにおいて判断するのはあくまでも当事者カップルである。医療者はカップルや子どものその後の人生すべてに責任を持てるわけではなく、遺伝カウンセリング実施者が他人の人生の大事な決断に大きく干渉することは避けたいと思っている。しかし、カップルの価値観は社会の議論に影響される。社会として出生前診断に関して一定の方向を目指そうという議論が活発になれば、多くのカップルがそうした価値観に沿って決断するであろう。社会において出生前診断についてしっかり議論していくことは、そういう意味で重要である。
しかし、私の行なう遺伝カウンセリングでは、検査の方法や危険性、検査でわかることわからないこと、実際に疾患の可能性がどのくらいあるかといった医学的事項とともに、先に述べたような見解を含め、倫理的、法的、社会的見地から多様な意見が存在することもお伝えするが、これらはすべて情報としてお話しする。そしてカップルが、そうした情報に対してどう感じるか、自身の気持ちや価値観を振り返りつつ出生前診断を受けるかどうか決断する過程を、心理カウンセリング的技術も駆使しながら支援する。状況の受け止め方によってカップルの決断は左右されるが、人間の心理は複雑で、同じような疾患の状況に対しても、楽観的な人、悲観的な人など多様である。遺伝カウンセラーとしては、情報は誰に対しても同じように伝わるのではなく、どんな情報も受け止める側の気持ちが伴う形で消化されるのだという認識に立ち、出生前診断に関して個人個人の様々な気持ちを取り上げ話し合う過程を通して、決断に至る道を支援し、カップルがどんな結論に至ったとしてもそれを支持する。中立的立場を貫きながら、気長に話し合いを重ねてカップルの決断を支援していくためには高度な技術が必要で、決して容易なことではないが、それを目指したいと私は思っている。
ところで、医療の現場では、出生前診断とその後の中絶は重篤な疾患に限るという考えが主流である。特に日本では、遺伝カウンセリングにおいても、カップルに対してそう伝えるべきとする意見が少なくない。しかし、この考え方は私の思う遺伝カウンセリングと少し異なっている。これは、遺伝カウンセリングとは何かという概念の根底にも関わる議論であるが、次回はこのことについて考察してみたい。
出生前診断とその後の中絶を考える際、一般的に、その対象となるのは重篤な疾患に限るとする傾向がある。遺伝関連の10学会による「遺伝学的検査に関するガイドライン」(註)では、新生児期、小児期に発症する重篤な遺伝病や染色体異常、あるいは胎児がその他の何らかの重篤な疾患に罹患する可能性があることなどを出生前診断の条件としている。そこで日本では、カップルが、生命予後が悪くない、治療法が存在する、知的障害がない、といったいわゆる「軽い疾患」の出生前診断を希望しても、「それはできない」と告げられることが少なくない。しかし実際には、できないと言われるだけでは納得できない人も多い。それではどのように話を進めたらよいのだろうか。
ここで忘れてはならないのは、来談者の多くは、疾患や遺伝に関連した疑問や不安は抱えていても、その人なりの理解力と判断力を有する人間として尊重されるべき存在だということだ。医学的には軽微な症状でも「それは自分にとっては一大事」ととらえる人を誰も否定することはできない。そこで私は、遺伝カウンセリングにおいて、疾患や遺伝、出生前診断に関する情報を提供した上で、個々の来談者がそうした情報をどのように受け取っているかを取り上げて話し合う。確率の数字を大きいと感じるか小さいと感じるか、その疾患を重いと思うか軽いと思うか、なぜそう感じるのか、その疾患に関連した事柄がその人の生活や人生にとってどのような意味を持つか。これらを掘り下げて話し合うプロセスは必ずしも楽な作業ではない。疾患に対する偏見や嫌悪感、遺伝に関連した罪悪感など、自身のネガティブな感情に向き合わねばならないときもある。しかし、ネガティブな感情を持っていることは人として自然なことであり、否定されるべきものではない。心理カウンセリング理論では、来談者の気持ちや考えを肯定的に受容することが基本である。来談者は否定されずに話を聞いてもらって初めて安心して正直な気持ちを語れるようになり、その過程で自身の気持ちと向き合うことができる。そして、自身の気持ちや考えに気づき、整理し、これからどうするかを決めていくことが可能になるのである。
私は、軽い疾患の出生前診断もどんどん行ってよいと思っているわけではないし、疾患によっては検査を依頼しようにもどこでも調べてもらえないようなものもあるので、その場合は実施不可能と伝えることはある。しかし、実施可能なものについては、その出生前診断を受けるかどうか、これまで述べたような一連のプロセスを経てひとりひとりの来談者にじっくり考えてもらいたいし、そうやって決めた結論はどんなものでも尊重したいと思う。
来談者が「軽い疾患」の出生前診断を希望しているとき、それを頭から否定することは心理カウンセリング理論の原則に反している。実際、来談者は反対されると、「そんなことを言われても私は心配なのです」と、まず相手に理解してもらおうとする方向に話し合いが進んでしまう。しかし実際に必要なのは、来談者が医療者を説得することではなく、来談者自身が自分の気持ちとじっくり向き合うことである。「病気は嫌だ」という人に対して、当事者でない人が「それは偏見だ、間違っている」と言うことはできない。どんな軽い疾患であっても、「病気は嫌だ」という気持ちは多かれ少なかれ誰にでもある。そのことを認めた上で、それでも引き受けていかねばならない現実もあることに気づき、その状況を受け止めていく能力もまた、人は有している。私は、こうした人のもつ能力を信じてじっくり話し合うことを大事にしているし、そうした話し合いの中で感動することは本当に多い。
日本の遺伝カウンセリング実施者の中には、人々が安易に出生前診断、中絶という道を選ばないように、疾患を有する子どももその子なりに成長するし子育ての楽しみは大いにあるのだと話すべきという意見が多く見られる。経験豊かな医療者からそのように諭されることは無駄ではないし、押し付けがましくないやり方で上手に話す医療者も少なくない。私自身は別の立場で取り組みたいと思ってはいるが、医療者の諭しそのものを否定しているわけではないし、諭す者とカウンセリング理論にのっとって来談者の気持ちを尊重する者の両者は共存可能だとも思う。ただ、そうした実践のどの部分を遺伝カウンセリングと呼ぶかということは、将来的に整理していかねばならない課題である。
(註)田村事後補足:2011年2月より、10学会のガイドラインは日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」となり、出生前診断に関しては日本産科婦人科学会の指針等を参照することとなった。
2003年、「ヒトゲノム計画」によって明らかにされた人間の DNA の全配列が発表された。この「ヒトゲノム計画」という国際プロジェクトが1990年にスタートしたとき、米国政府はそのために30億ドルという巨額の予算を計上したが、その際、全予算の3〜5%を別枠で確保して、ELSI( Ethical, Legal, and Social Implications ; 倫理的、法的、社会的諸問題)の研究に当てると決めた。以来、これまで十数年にわたり全米中の生命倫理や法律、社会学、教育学、心理学など様々な分野の研究者たちが、ELSI 関連研究費を利用して、DNA や遺伝子の研究と並行して考えていかねばならない倫理的、法的、社会的諸問題を洗い出し、議論してきている。
たとえば、疾患や体質に関連した遺伝子情報を伝えられた人々の心理的反応の研究はよく知られている。遺伝子の状態だけでは将来の症状の完全な予測はできないため、遺伝子解析結果は確率情報とともに語られることが多いが、あいまいな確率の受け取り方は人によって異なることが判明し、遺伝子検査時の確率の伝え方の検討という課題が浮き彫りになった。あるいは、個人の遺伝子の状況によって将来の疾患の予測が可能になってくると、遺伝子情報を利用して保険加入や就学、就労時の社会的差別が生じる可能性も指摘され、遺伝子による差別を防ぐための法整備が進む動きにつながった。体格や性格など疾患以外の事柄に関連した遺伝子の状態を調べて利用していくことの是非の議論も続いているし、中高生を対象としたDNAに関する教育プログラムの研究も進んでいる。このほか多種多様な ELSI 研究が実施され多くの知見が得られてきた。さらに、ELSI 研究を通じて、DNA 解析や遺伝医学の専門家たちと、生命倫理、法律、社会学、教育学、心理学など異分野の専門家たちが、互いの領域について学びあい共通の言葉で議論ができるようになったことは大きな収穫である。
一方、ヒトゲノム計画が国際プロジェクトであったのに対し、ELSI 研究が米国を中心として行われてきたことの限界もある。ヒトゲノム計画で判明した DNA 配列の情報は人類共通であり世界中で利用可能だ。したがって、ELSI を意識していない国においても、DNA や遺伝子の知見は、社会や人々の生活に影響をもたらしていくだろう。しかし、米国の ELSI 研究のリーダーたちは、「倫理観も法律も社会背景も国や地域によって多様である以上、それぞれの国や地域で ELSI と取り組んでもらうしかない」と言う。
では日本ではどうだろうか。日本の DNA サイエンスの発展は欧米と同等かそれ以上だが、それに比べると日本の ELSI 研究が今一歩であることは否めない。ELSI 研究どころか、「情報提供が大事」、「差別を減らすために教育が必要」といった観念論の発言が繰り返されるだけのことも多い。ELSI という語を耳にする機会は増えてはいるが、日本で ELSI というと、人間の DNA や遺伝子の解析研究を倫理的に行うためのルールの話になってしまうことも少なくない。個人情報保護やインフォームド・コンセントのあり方の議論や、三省による「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の話も大事である。しかし、ELSI とはもともと、DNA 研究の倫理的な遂行の仕方の話というよりも、DNA 研究が進む際に別途考えておくべきことの議論の分野なのだ。
最近、医療者や DNA 研究者の中に ELSI を考える人たちが出てきた。彼らが、日常の診療や研究の傍ら、人々の意識調査のアンケートをとったり生命倫理学の勉強をしたりしていることには頭が下がる。しかし、医療者や DNA 研究者の視点は医療や医科学研究に関することが中心になりがちだし、彼らの多くはアンケートや聞き取り調査といった心理社会学的研究の方法論にあまり詳しくない。DNA 研究がどんどん進む現代にあって、目の前の診療や医科学研究に直結した問題だけなく、将来の社会や生活を見渡して考えておくべきことはたくさんある。日本においても、もっと社会学や心理学、教育学、法律、生命倫理その他の分野の専門家を巻き込んで、広い視野で ELSI を研究し議論をしていく必要があるのではないだろうか。
人々は、遺伝子や DNA の時代の未来に、大きな期待と不安の両方を感じている。ヒトゲノム計画で得られたサイエンスの知見を私たちの生活や社会において用いていく際に、我々人間は何を考えておかねばならないのか。DNA 科学の進歩を賞賛するだけでなく、その波及効果としての ELSI について、日本でも研究が進み議論が重ねられることを願いたい。
連載の最後に、法律を専門とする方々に四つのことを申し上げて締めくくりとしたい。
まず、遺伝カウンセリング体制の整備に法律家の力が必要であること。来談者と長時間話をするだけの遺伝カウンセリングは経済効率の悪い行為であり、現場のニーズはあっても、医療機関が遺伝カウンセリングを積極的に導入しようとする動きは少ない。そこで発想を転換して、遺伝カウンセリングは医療者と患者、家族のコミュニケーションを促進し、医療機関全体の診療を円滑に進めるために必要な行為ととらえてもらう必要がある。平成17年1月27日に東京高裁で判決が出た遺伝性疾患の説明上の過失の判例から考えても、遺伝カウンセリングは医療機関側の説明義務を全うする手段、リスク・マネージメントの方策となり、同時に患者、家族にとっての利益も大きい。このように、遺伝カウンセリング体制の充実には法的視点のサポートが有用であると思う。
第二に、着床前診断や出生前診断、胎児異常を理由とした人工妊娠中絶等に関する倫理的、法的な議論の際、それらの是非という観点からのみならず、「行う際にはどのように行うか」というプロセスに着目した議論の方向性も探っていただきたい。これらの選択肢を考慮する際には、人々が十分な情報を得て自律的に決断する過程を保証することが大切で、遺伝カウンセリングの充実が欠かせない。賛成派、反対派だけでなく、過程重視派の台頭が望まれる。
第三に、個人情報保護法による医療情報の扱いにおいては、遺伝診療が十分に考慮されていないことを知っていただきたい。個人のカルテに書かれたその人の血縁者の病歴は誰の情報なのか。夫の遺伝子変化が子に伝わる可能性がある時、妊娠中の妻のカルテに夫の遺伝子の情報を転記してよいのか。家族を代々診ている家庭医にとって、親戚の遺伝性疾患を知った上で目の前の患者の診断が可能になる場合があるが、それはその親戚の病歴情報をその人の同意なく使用したことにならないだろうか。こうしたことが個人情報保護法では十分想定されていない。
第四に、遺伝や遺伝子による非合理的な社会的差別への対応の検討が急務である。遺伝子の状況によってある程度将来予測が可能になると、疾患を発症していなくても個人の遺伝子をあらかじめ調べて、就学や就労、保険加入の際の情報として使われるかもしれない。生命保険や医療保険等の加入時や学校や職場において、健康診断や問診で遺伝子検査や家族の遺伝的な病歴情報が利用されるようになる可能性は否定できない。遺伝子や遺伝の状況が結婚や離婚の際に問題になることもあるであろう。
既に疾患を発症している場合、就学、就労、保険加入時等に、これらの人々が特別に扱われることをどのように考えるかは難しい。疾患状況によっては同等に扱えない場合もあるであろう。であるとすれば、特定の遺伝子や遺伝の状況を有する人々が、たとえ疾患は発症していなくても、特別の扱いを受けることが是認される場面もあるかもしれない。しかしそれが是認されるには、それなりの合理的な理由がなければならない。現在、遺伝子によってわかることはごくわずかである。遺伝子技術に人々が寄せる期待は大きいが、人間の身体の形、機能、性格、行動、病気のなりやすさ等は、生活習慣や環境、学習や訓練等に影響され、遺伝子だけで全てが決まるわけではない。遺伝子情報のみから予測できる将来の状況は、少なくとも現在の科学の水準では多くの場合非常に不確かである。その不確かな情報によって、たとえば十年以上先に数十%の確率で発症する疾患を理由に目の前の雇用の機会が奪われることは適切ではないであろう。したがって遺伝子情報による差別問題を考える際には、その遺伝子情報から予測できる内容の科学的妥当性の吟味が欠かせない。もちろん、ゆくゆくは、より精度の高い将来予測が可能な遺伝子検査が出現するであろう。その時生じ得る社会的差別に対して、我々は何ができるか。我が国ではそうした議論はまだほとんど出てきていない。遺伝子関連技術の進歩のスピードは目覚しく、社会の受け入れ態勢が整うことを待っていてはくれない。急がねば、と日々感じている。
遺伝カウンセリングに関連して法律にまつわる事柄に遭遇することは多く、法律の専門家の方々には常日頃から助けられている。今後、遺伝カウンセリングに従事する人々が、多くの法律家の方々と交流を深めていくことを心から望みつつ、連載の終わりとしたい。これまで拙文をお読みいただいた皆様、ありがとうございました。ご意見等は、田村智英子までお願い申し上げます。
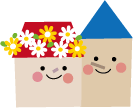 トップページに戻る 田村智英子文献のページに戻る
トップページに戻る 田村智英子文献のページに戻る