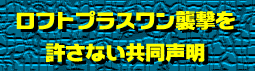 |
|---|
ごく私的・脱線的に
<現代暴力論ノート>捕遺として
向井 孝
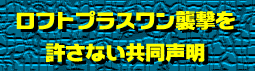 |
|---|
(1) 立場と関係
そもそも「ロフトプラスワン襲撃を許さない…」なんて名乗りからして、何か内ゲバまがいのケンカ沙汰と知れる。
とすれば、どっちがどう転ぼうと、ぼくにはあまりかかわりが無い他人事である。日常市民社会のはずれでの、まあ当事者だけのコップの中の嵐や。
それがまた「なんで物好きにもあんたが共同署名人になったんか」と訊かれたら
第一に、この「声明」の呼びかけを送ってきたのが、ほかならぬ鹿島君だったから。
第二に、ことの経緯とか是非の如何はどうでも、この場合の一対多数という「弱い者の泣き寝入りでは済まされん」という趣旨には賛成やから。
第三に、ロフト何とかという、面白そうな一パイ屋の営業が、こんなことで面白くなくなるのは面白くないから。
−つまりこれは「いらんお節介」というものだが、「関係」というのはしばしば、こんなことから始まって深みにはまるものである。
(2) 弱い者の暴力・非暴力
さてここで先ず「ケンカは結果として<強い>もんが勝つ」。そして「<勝ち>を決定する<強い>とは、相手より物理的暴力が優越していること」、という判りきったことを云っておきたい。
その上で佐藤君のことでいえば、もしそれが一対一の個人のケンカとしての「暴力沙汰」だったら、どっちがどっちであろうとぼくには本来無関係のことや。放っとけばよい。
しかしそれがどうしても放っておけん事になるのは、例えば佐藤君個人がやったことへの対応が、戦旗派あるいはその有志の「一対組織(又は多数)」というかたちの、次の段階として出てきた。それは暴力の第一次の質的転換である。
換言すると、「相手の方が強い」とか、「ひょっとしたら負ける」と思うような場合、ふつう弱い者は正面からケンカを仕掛けるものではない。
あえてやるとしたら、結局佐藤君のように(と云っても現場をみてへんから無責任な推測やけど)、聴衆の中の一人として講演中にイヤ味なヤジを飛ばしたり、揶揄的ビラを配ったりというようなこと(それだけでも勇気と多少の覚悟がいるやろ)ぐらいしかない。それは暴力での対決を求める挑発でも、そのためのものでもなく、むしろ暴力を封じるためのおのずからの<弱い者の非暴力>−<暴ニ非ザル力>として出てきたやり方の一つなのである。そしてそのとき<非暴力>もまた<暴力>と同じく<生命力>の発現であって、とくに弱い者にとって<暴力>に対応する意味の<力>である。
(ついでに云うと、弱い者同士の暴力沙汰は子供のケンカにみられる<擬闘>のような結果で終わるものだ。もしそうでなければ一瞬で完結する<衝動的錯乱>、あるいは思いつめた執念の果ての<待ち伏せ的対決>。もしくは捨て身ともいうべき<テロ>である。そして組織的には<ゲリラ>しかない。しかしその結果は99%決まっている)。
(3) 組織、その内部攻撃性
先に「<強い>とは物理的暴力が相手より優越していること」と、判りきったことを云った。が、この当たり前の定理は、すぐさま相手側の具体的な対応−つまり<人数><物量>その<組織化>によって、ごく簡単にくつがえる。
つまり<暴力>は<組織>に対しては(こちらも組織で対応しないかぎり)、殆ど無力なのだ。(だから<組織論>こそが又、現代暴力論の核心となる)
そして<組織>というと、その典型のような政治党派、セクトの例をあげるまでもなく、まず何よりも<統一と団結>である。
もちろんそれは規約、党則、統制として成文化され、みんなの合意と承認で成立する。決して強制や支配を意味するものではない。
にもかかわらず、いま拡大中の組織でさえも派閥が生まれるのを避けられないのは、なぜか。ましてや運動がマンネリ化して停滞し行き詰まると、たちまち路線をめぐって、それが内への締めつけ−査問、糾弾、さらに骨肉相喰む内ゲバや分派闘争として現れるのは何故か−。
つまりどんな組織でも、それが<統一と団結>を志向するかぎり、いつでも<内ゲバ>の可能性を内在するのである。(今までに書かれた<社会運動史>がほとんど運動の<分裂抗争史>に外ならないことでも知れるように、それは<統一と団結>が<組織の内部攻撃性>に依拠する特性を明らかにしている)。
(4) 暴力の変質と転換
暴力が組織を意味するものとなったその瞬間から、その暴力は変質する。
つまり人間的それゆえ動物的<生命力>ともいうべき本来の生命力としての意味を失うのである。
それは第一に、佐藤君の場合にみたような<組織暴力対個>という、露骨な優劣のかたちをとる。が、それだけに大抵はとどまらない。
第二に、<員数対員数>→<組織体組織>に転化する。優劣の拡大的均衡化である。
第三の転換−つまり第一、第二の過程を総括し、しかも<不可視>となった<構造暴力>→<疑似非暴力体制>へと収束することでの固定である。
それは弱い者がそのことを承認し支持することで、<絶対暴力>ともいう意味のものになる。
いいかえれば、佐藤君が戦旗派から受けたロフトでの暴力沙汰は、右の第一の段階でありながら、その次に出てくる<対応>とからんで、暴力についての本質的省察の問題を提起している。
(5) 疑似非暴力体制の現実
くりかえしになるが、現代社会の最右翼に位置する最大の<組織>が国家であり、その具体性が<政府>である。
それは代議制にはじまり、法規法律条例などによる秩序維持を名目とする合法暴力装置−警察、裁判、刑務所を具備した<疑似非暴力体制>をつくっている。
国民はその疑似非暴力イデオロギーに無自覚なまま非暴力秩序として合意し、更にくりかえしの<選挙>によって追認しているのである。
そしてそこから出てくる問いは、この自分が自分を縛っているに等しい、打つ手なしの状況の下で、ぼくらは何がやれるか、何を武器として抵抗するのか、である。
その答えは、ただ二つの方向しかない。すなわち<暴力的抵抗>か、<非暴力直接行動>かである。
しかしもう明らかなように、前者は一回きりの賭けである。さらに組織的対応−その強化・拡大は、権力の弾圧を挑発する。そのことで出てくる運動の危機浮沈が、しばしばスパイ問題や内ゲバとなることも、また、既に充分見てきたことである。
−−とすれば唯一残されているのは<非暴力直接行動>(以下NDと略)のみである。選択の余地はもうない。
昨今それは頗る紛らわしい無抵抗主義・非暴力主義、あるいは非暴力行動として語られることであいまい化されているが、まさにそのことを自覚することにおいて<暴ニ非ザル力>としての<直接行動>なのである。
(6) 非暴力直接行動(ND)とは何か。
順不同で恣意的に、思いつくまま並べると−−。
1.<直接行動>とは、生産と創造、芸術と文化の<自治管理>、労働と遊戯の<自己享有>であって、それこそが弱い者たち−人民−のみが日常で果たし、やり遂げている<生活力>なのだ。そしてそのことを保証する絶対条件が<非暴力>社会なのだ。
2.そもそも<ND>は、ぼくら弱い者だけがもつ<生活力>−<生命力>−<力>−であることをまずしっかりと確認せよ。
3.国家はその権力を、直接的暴力ではなく、<疑似>非暴力体制における略取的介入支配として具体化している。
それゆえ<ND>は、本来の営為のままで、しかもそのことで疑似非暴力体制を<拒否>し<抵抗>するものとなる。
4.<ND>は、勝つことを目指さない。ただやられてもやられても、やられてしまわないだけなのである。暴力的挑発には「豆腐に釘」「柳に風」で対峙する。「勝つのではない、負けてしまわんだけや」というとき<ND>は、相手の<疑似>を、むしろ逆の<力>−相手の弱味とするという意味と方法になる。そのことでの、国家を拒否する永久革命−歴史へとつながる・・・。
こう書いてきて、どうも不充分で云い足りない。<ND>は<目的>が<方法>そのものでなければならないのに、いまどんな<ND>のやり方を示せるか、と問われるとぼくは、答えることばに窮する。
しかし<ND>は、ある事態、ある情況が眼前にあって、課題的にそれへと身をのり出してぶつかる<ぶつかり方>のさまざまさ、<臨機応変のたのしみ方−あそび>なのだといえば、すこし通じるかもしれない。
そこでぼくがこれまでやってきたことを例にとれば、−−たちまち「なァーんや」と云われるやろけど−−佐藤君のロフトでやったことまがいの、まあ権力に対する「五月の蠅か、寝入り花の蚊」同様の、時たまのイヤガラセぐらいのことでしかなかった。(それに対するケーサツは、起訴も拘留もでけへんまま、かえって新聞が書き立てて宣伝してくれるわが家への「ガサ入れ」が計五回だけ、ということ)。
それで−−このごろはもうぼくもトシやから、殆ど動けんけど−−すこし前までは労働者少数派のデモやピケ、座り込みなどにちょっと期待し、釜が崎、山谷、新宿のさわぎ、秋の嵐やいのけんの提起を応援しながら、「東アジア反日武装戦線」「日本赤軍」などの逮捕者救援を、当然のこととして関わってきた、ということである。
そして、いま<反天皇制><反原発><死刑制度廃止><国家賠償請求訴訟>などに、ほんのちょっぴりかかわっているのは、何がともあれそれが、疑似非暴力化した国家暴力の<綻び目>と向きあう特徴的課題の<場>だからだ。
(7) 歴史・ND・女たち
ここらで結末を急ぎたい。
このごろぼくがしきりにおもうのは、歴史の連続性という大きな流れのなかでの<変遷>というよりも<未完の小達成>があること、そしてその意味についてである。(例えばそれは<ND>の社会的日常を、もっともそのような自然さであらわしている女たちの<女性史>において、ぼくの母や祖母が歩んだ五〇年百年前と、いまぼくと親しい知己の彼女たちとの、その共通と相違に気付けば、変遷とだけ云えるものではない歴史の意味が明らかになるだろう)
それをこの小論に即して云えば、強い者が支配する直接暴力社会から、現代国家の疑似非暴力体制社会まで辿りつくには、弱い者の長くてさまざまな段階の道程があった。そしてその連続性においてこれからもそれが続きながら、決して留まることはないという歴史への、ぼくの信頼である。
意識の如何にかかわらず遂には<ND>の小達成が歴史をつくり続けるという確信である。
歴史を河になぞらえたら、個人の一生は河の流れの中の無にも等しい一滴の一瞬にすぎない。ぼくはその無のような一滴として、その流れに流されながら、時にはその流れの、渦巻くところや、淀んだり急に走り出す傍流やらを泳いで、おもえば結構たのしくおもしろく、好き勝手な一瞬を流れ流されたと思う。そしてその流れこそが、文字通りぼくの<運動>の一瞬の意味だったのである。
もう少し<ND>とは何か、を続ける−−
5.暴力は、克服的積極的現象的(可視的)である。それゆえその行使は疑似非暴力体制のもとでは<非日常>なものとして、つねに世論に監視され、その過剰な行使は逆に抑止されざるをえないだろう。
6.<ND>は防御的受動的精神的(不可視的)である。しかしそれゆえに歴史の連続性の持続のなかでの<ある小達成>をつくる不可視の蓄積なのだと云えようか。
7.<非暴力>と<直接行動>を一つにするのは、本質矛盾ではないのか、としばしば問われる。否。たとえば生物の雌雄、人間の男女の−−生物本来の使命−−生殖という対関係が、新しい生命をつくり続けるように、<ND>はそれゆえ<生命><生活>であることにおいて、どんな暴力支配も左右できない<力>なのである。
8.佐藤君のパロディ名刺やビラや野次が、みんなを思わず笑い出させるようなユーモア、風刺の、とくに<遊び>そのものであったら、もっとよかった。
このことで欠除しているのは<ND>の視点である。というよりも佐藤君がもし気付いて、<女たちの立場>から問題提起したのだったら、もっと深い暴力非暴力の本質に触れえたにちがいない。
9.歴史の連続性と、そのなかでの<ある小達成>というとき、それはもっぱら<ND>の自覚とひろがりを先導するこれからの<女たち>が鍵をにぎっている。そのことを最後に強調しておきたい。
99・2・8 (未完的完了)