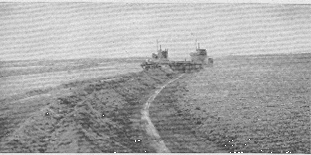
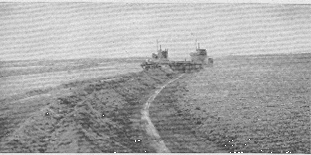
カリホルニア稲作圃場の畦畔造成
Farmers' Bulletin No.2022
USDA 1950 より
4 実験農場
営農部会は、実際に10ヘクタールの試験をやってみようということになった。
機械を使うからにはさしあたり60ヘクタール(6戸分、実際は6稼動力)の規模になることを考え、技術会議(農林省本局にあって、各試験機関を統轄する部局)に応援を求めた。
技術会議からは数名の稲作と機械の専門家が営農部会にでてもらい、1年がかりで試験農場計画をつくりあげた。
そのとき専従でわが班に来てくれたのが、農業技術研究所の武井昭氏である。
試験地の場所は八郎潟干拓の周辺干拓地(中央干拓地を囲んだ承水路とか残留湖面の外側にある干拓地)南部2工区60ヘクタール、時は干陸直前から干陸までの2〜3年間の話である(中央干拓地は、まだ水面下)。
『エリート官僚論』の著者は
「その実現のためには、当時の農業・農村の常識を超えた巨額の投資を必要とするものであり、補助金あるいは低利融資によって相当な国費が投入されたが、ーーーーー」
と述べているが、この実験農場計画はこのような経緯のもとで作られた。
場所は地元農家に売り渡す前の干拓地を仮に使用、実施は秋田県の農業試験場が国の委託事業として行ったものである。
「プロジェクト担当者は、知識もノウハウももっていなかった」と『官僚論』の著者は云うが、当時農林省でえられた最高水準の稲作知識、技術会議の技術者達が集まって作った計画で、著者の云うようなフザケタものではなかった。
ただ、稲作60ヘクタールという経営技術は、試験場ももっていなかった。そこに実験の意味があった。当時農林省にはアメリカの稲作技術を知るものがいなっかた。
日本では行われていない等高線状の仮畦畔(毎年壊して作り替える畦畔)と、掛け流し様式と、空からの散播は、われわれ事務局の提案で、技術会議の一応のフィルターにかけられたものの、アメリカ農務省や州政府発行の文献、農林省職員でアメリカ研修旅行から帰ってきた者の資料、当時行われた派米農業青年のスライド写真とうから学ぶ以外に方法はなかった。
カリフォルニア州等の等高線状畦畔の潅漑方式は、昭和初期まで日本の各地に残っていた未整理の水田、即ち等高線状の曲がりくねった小区画な形状の、上の田から下の田に掛け流す潅漑方式と、規模の差はあれ、潅漑方式の原理は同じである。
日本の区画整理された田は、畦畔は几帳面に方形である。しかしその後機械が入るために区画を大きく取ろうとすると、緩斜面でも、水平面をとるための切り盛り土量が増し、造成費が増す。
あるいは、排水が悪くなるから排水のため暗渠工が必要となる。
しかるにアメリカの水田は、緩斜面であるが、斜面のまま、いわば山なりで、畦畔の方が等高線状に曲がっているから地盤の切り盛り不要である。
畦畔を撤去すれば斜面のままだから地表に水たまりが出来るような排水不良にはならない。
(わが国では、一般に大区画と称しても、単位は固定畦畔に囲まれた水平面10〜30aの矩形に過ぎない。実験農場では、道路に囲まれた緩斜面20ha(60haを三等分)の矩形に、毎年数本の仮畦畔を作る計画であった。)
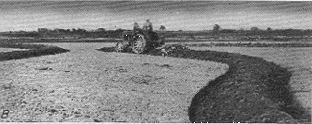
アメリカ南部諸州における畦畔造成
Farmers' Bulltin No.2043
USDA 1952 より
このように大農式と小農式とでは原理が異なる場合が多い。散播と正条式田植えもそうである。そして日本の試験場技術も小農を前提として発展したものである。
その例証として、次の文をあげる。(八郎潟干拓地整備委員会は昭和36年より46年まで、11年間調査研究を行った。)
『八郎潟干拓地耕地整備委員会総括報告書』昭和47年3月農業土木学会(八幡敏雄教授)には、まえがきに
「ーーーーーー発足の当初のは従来の開拓事業と同じように適正規模の農家をできるだけ沢山つくって入植させる計画であった八郎潟も、やがて事業計画は検討し直されて、学会に委託がもたらされた時点では、干拓地に大型機械化農業を樹立し、これを日本農業近代化のためのモデルとしようという方針が打ち出されていたのである。
この課題についても当時のわれわれの知識は甚だ乏しいもであった。大型トラクターは想像できても米国で行われているような稲の直播栽培やイネを刈るコンバインは実感できないというのがいつわりのない実態であったのである。
昭和36年5月、農業土木学会に提出された研究調査委託の目論見書の冒頭にーーー『八郎潟干拓地においては、将来の日本農業のモデルたるにふさわしい近代的大規模機械化農業を行う方針であるからーーーー しかるに従来の耕地整備事業は小規模経営を前提として行なわれてきたため、八郎潟の耕地整備計画に必要な理論や技術も未完成であるからーーー』」
「事業者たる農林省は自らの機構の中に八郎潟干拓事業を推進するためのブレインとして八郎潟干拓企画委員会をつくって、作目や経営規模は主として営農部会で論議されたようだが、適正規模の多くの農家を入れるべきだと考えた一戸当たり2.5ヘクタールの当初計画の段階から一戸当たり10ヘクタール(従って戸数は激減)の現在の実施計画まで経営規模は様々に変わった。」
「我々としてはそのことに若干の疑問を感じながらも作業をすすめたのであった。しかしこの11年間にわが国の食糧事情には激しい変化が起こっており、この一二年米が余るという事態まで生ずるに及んで、完了途上にある八郎潟干拓ないし新農村建設事業はここで再びその計画内容を再点検しなければならなくなりつつある。ーーーー」
さらに第3章(長崎明)「八郎潟耕地整備についての基本計画」の「前提条件の問題点」という箇所で
「-----われわれの間では協業たると個別たるとを問わず、一戸当たり経営面積を5ヘクタールとするよりも2.5ヘクタール程度にして入植農家を多くする方がモデルとしても現実的であり、将来畜産を導入するにも有利であるとの意見が優勢であった。(その後、一戸当たり経営面積は逆に拡大され10ヘクタールとされた)」
「暗渠排水組織」の項では、
「ーーーーしかし、従来わが国の水田にける地下排水の効果については、いまだ必ずしも明確な実績がえられていないし、他方米国における米作大農場においては地下排水の実例がないという事実等から、八郎潟の水田において地下排水が絶対不可欠であるとは、いま必ずしも断定しえないのが実状である」
としるしてある。
また、更地(さらち)に絵を描くといっても干陸直前のいわば、まだ湖底にある土地だから、計画段階にはトラクターの走行試験もできないこともハンデになった。
カリフォルニアの稲作農業とわが国の稲作農業を比較してみると、際立つものに、カリフォルニアの田の造成---広い緩斜面に何本かの曲線状の仮畦畔を作る方法と湛水直播、かたやわが国の緩斜面を階段状にけずった狭い水平面を直線状固定畦畔で固める方法と田植えである。
総労働時間は、一方は10a当たり数時間(?)、一方は(当時)10〜20日で、収量は同じである。
八郎潟干拓には、ほかでは得られない更地がある。手本がアメリカにある。とにかくカリフォルニア稲作をまねてみよう。これが機械化実験農場の構えであった。
(写真は1950,52年アメリカ農務省発行の「ファーマーズ・ブリテン」農業者向け普及用の小冊子より)
(実験農場の実施)
実験農場は、更地(さらち)に絵を描くといっても干陸直前の、まだ湖底にある土地だったから、計画段階にはトラクターの走行試験もできない。機械化試験といっても土地造成試験からやらなくてはならなかった。
実験の経過については、武井氏の『35年を回顧して』に詳しいが、試験を苦しめた第一の要因は、試験がしやすいように、砂地がかった南部二工区を選んだことにあったと思う。
八郎潟干拓地の圃場整備で、干陸前から問題になったのは、湖底を覆っているヘドロ地盤であった。
ヘドロ粘土質を乾かすには干陸後数年は掛かるであろう。その間は地耐力が弱く、とうていトラクターなど使えないことが予想された。
しかし、砂地なら乾くだろうと誰もが期待をかけた。南部二工区は砂地であった。しかしこの土地は、地元に売り渡さなければならない土地であるから、試験をいそがなければならない。
皆、乾くと思っていたが、この期待は、なかばはずれた。
私は圃場整備完了直前の試験地にいってみたことがあるが(私は配置換えで経済課)、背後地の既存田地帯から押してくる地下水と、排水路を流れる流水で、湖面に排水する排水機をいくらまわしても、圃場面はかわくどころか、何度も小型トラクターが陥没して、大型湿地用トラクターの救援を受けたのを覚えている。
トラクターの牽引力の不足で仮畦畔の造成に苦労した話が、武井氏の『回顧』に出ているが、土の乾き具合が作業に大変影響していた。通常の土木具機械はしめった泥土には大変弱い。
湛水直播で浮き苗が大量にでたことを、聞かされたが、試験場の試験としては具合が悪かったかと同情できる。
前にも云ったが、その後、私は農林省の肩入れで出版されている小冊子で、湛水直播の品種別試験でいくつかのアメリカ品種のうち日本系品種がことごとく定着不良であることを発表したアメリカ研究者の論文を知った。
実験農場計画の策定では、使用品種を決めるについて湛水直播の観点から検討しようとする意見は試験場関係を含め、技術会議の誰からも出なかった。つまり品種発芽・苗立ちの性能と結びつける考えがなかったわけである。
日本の水稲育種の技術水準は高いのだと思っていたが、零細農維持の技術に過ぎないと、この論文でつくづく思はされた。
数10年たっても湛水直播に着目した品種が開発されたと聞いたこともない。
しかし、60ヘクタール(機械化体系)実験農場は(アメリカ稲作を照準にしながら)、この機械化体系のどこに欠陥があるかを探すのが目的であって、稲作のはじめからうまく行くとは思っていなかった。
私は圃場工事が始まる前に(土地改良長期計画作成のために)経済課に戻されたが、農技研から派遣された武井氏らは残って、県の試験場とともに苦労された。
実験は1年で中断され、地元農家用に通常区画で整備された。等高線畦畔実験は立ち消えとなった。
だが営農部会の10ヘクタール案は生き残った。