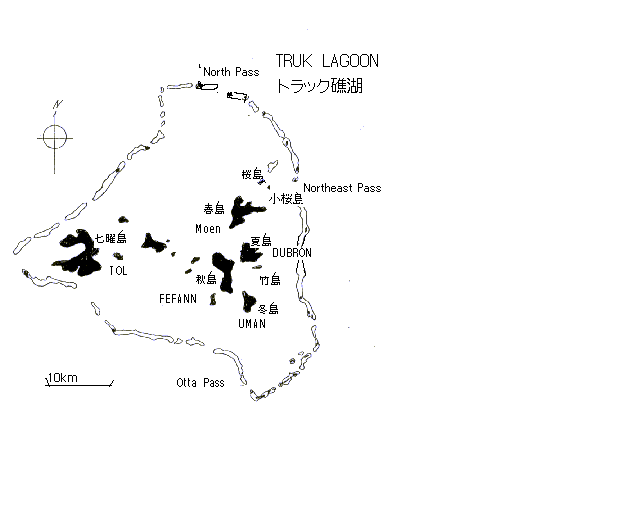
3 トラック島(一) サイパン陥落頃まで
1 夏島に着く
1914年、第1次大戦中、日本はドイツ領ミクロネシアを占領、つづいて1920年、これを国際連盟から委任統治領として承認され、以来「南洋群島」として支配してきた。この南洋群島に、サイパン、トラック、パラオ、ポナペなどが含まれる。
私の小学生時代(1930年頃)の国語読本に、「トラック島便り」という章があった。珊瑚礁(さんごしょう)の海を泳ぐ魚の美しさなどを、トラックにいる父から内地の子に書き送った手紙文である。私が夏島におりたったときのトラック島に関する知識は、どうやらそれだけであった。
トラック島(トラック諸島が正しい呼び名であろうが、トラック島と呼んでおく)は、グアム島やサイパン島のような1つの大きな島と違って、東西60キロ、南北50キロもある壮大な環礁(かんしょう)の中に、比較的小型の火山島群と極小の珊瑚礁島が散らばってできている群島である。
火山島は『春夏秋冬』の名がつけられた四季諸島と、水曜、木曜など『曜日』名がつけられた七曜島の2群がある。散在する極小の珊瑚礁島には、櫻島とか竹島とかの植物名がつけられている。島数250。(島名は日本の委任統治時代のもので、戦後は旧名に戻った)
環礁は、上巾がほんの数メーターから数10メーターが海面すれすれに出ている超長大なリング状の珊瑚礁であって、リングのところどころが死んだ珊瑚虫の殻が白い砂の堆積となって水面に現れた島になっている。堆積してできた島には数本の椰子が生えている。
これら環礁上の島々を、中心部にある火山島から見た方位に従って、子島(ねじま)とか午島(うまじま)とか、十二支名を付けている。また、環礁にはところどころ切れ目があり、船が航行できる個所は水道と呼ばれていたが、当時は南水道以外は機雷で閉鎖されていた。
環礁内の海域を礁湖(ラグーンlagoon)と呼ぶが、トラック礁湖は広大で水深もあるから連合艦隊の停泊地としても、絶好の条件を備えていた。
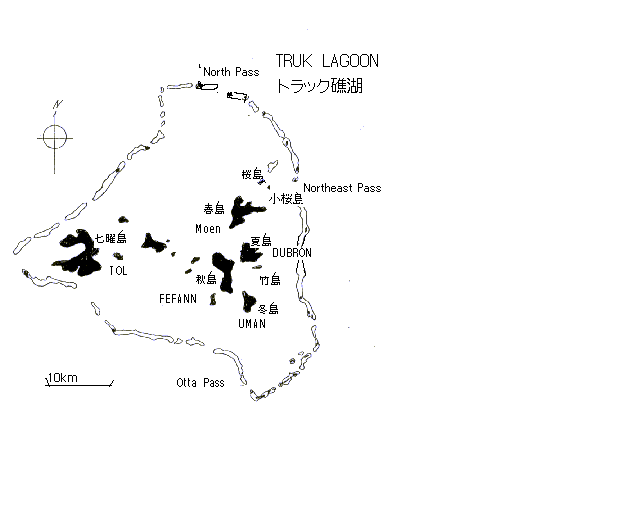
中央の火山島の水辺から環礁を遠望すると、水平線近くに、それと平行した白い線になって見えるが、注意しなければ見失うほどである。
しかし、火山島の山に登れば、視線は海面を見おろす角度になり、視界に入る海域は広くなるから、この白線は鮮やかにトラックの大礁湖と外洋を境するリングであることがわかる。白い線は、珊瑚礁と、それよって起きる白波である。
トラック環礁というのが一般に通っている呼称だが、広大な海域を現す語として「礁」で現すのは無理があろう。
トラック礁湖の大きさは、伊豆半島の基部と三浦半島に囲まれる海域くらいと考えればよい。そしてその中に大小250の島々が点在する。火山島のうち比較的大きい部類の春島(モエン)が、伊豆大島の半分より小さめである。
昭和19年5月20日、われわれを乗せた飛行艇は、サイパンから数時間でトラック諸島夏島についた。
四季諸島の中央の夏島には第四艦隊の司令部があり、水上飛行基地もここにあった。トラックの火山島はいずれも山が海面に突きでているような形で、平地部は狭く、そのかわりに珊瑚礁棚が海岸を取りまいている。夏島の水上基地を上がると、狭い傾斜地にいろいろな軍施設、病院などがあり、行き交う人も多く、雑然とした活気があった。
同行のW少尉の勤務先部隊は、この島内にあった。またポナペ島行きのO少尉もポナペ行きの便がなく、夏島の司令部に留まることになった。私の行き先である第46防空隊は隣の春島にあり、ここで3人はあわただしく分かれ分かれになった。
第四艦隊は、トラック島夏島に司令部を置き、周辺の島嶼を含む海域の防衛に当たっていた。艦隊といっても当時艦船は特務艦が1隻だから奇妙に思った。
阿川弘之著「井上成美」等によると、開戦当時は、第四艦隊は旗艦鹿島以下一応の艦船を揃え、ウエーキ島攻略にでたり、ポートモレスビー攻略作戦では、ラバウルに進出し、臨時参加の航空艦隊によって、米空母と交戦(珊瑚海海戦:昭17、4)している。
その後、トラック島は、ガダルカナル戦の頃から、19年の2月初め連合艦隊がダバオに退避するまで、その泊地になっているのだから、第四艦隊の役目は島の管理人のようなものだろう。その年(昭19)の2月の大空襲で固有の艦船は姿を消し、私がついた頃は水上基地付近の海面に犠牲になった船の1つが赤腹を出していた。
2 春島
私は春島行きの連絡便に乗った。船は館山砲術学校の訓練でおなじみとなった大発(だいはつ:上陸用舟艇)である。春島は目の前に見え、1時間もかからずにその桟橋に着いた。ところがそこは島の西端にある22航空戦隊桟橋で、私の行く46防空隊へ行くには、東端近くにある通信隊桟橋行きの便を使わなければならないことがわかった。
島内には自動車路はあるけれど、道は遠いらしく、もはや暮れも近く、航空隊司令部で泊めてもらうことになった。
司令部は、飛行場の端の山裾の崖に掘られた洞窟の中にあり、入口の前はドラム缶を積んだ大きな掩体(えんたい)が口を塞ぐように築かれていた。洞窟の中は大講堂のように広々としており、こうこうとした灯のもとで大勢が机に向かって執務していた。
夕食後、1人の士官に誘われて、洞窟の外のベンチに掛けて涼みながら雑談をした。外はすでに真っ暗であった。ふと彼はかがんで足元から何かを拾って、「これはなんだか分かるかね」といって私に手渡した。それはとげとげした金属片で、「爆弾の破片」であると教えられた。ついに戦場のまっただ中に来たのだと思った。
翌朝、第46防空隊から1台のトラックが迎えにきてくれた。
春島は、西岸を底辺とし頂点が東に細く伸びた三角形をしており、西岸と北岸が6キロ、南岸は7キロ、山体は西半分が高く、東へ象の鼻のように伸びている。平坦地は西海岸沿いにあり、ここに飛行場がある。ただし平地帯の巾は広くなく、すぐに西部山地が迫っている。山波を東側に越すと一たん谷となり、再び切り立った高さ200米位の中央山地となる。
頂上は裸岩の現れた台地状となっており、台地がつきると地形はこんどは東へゆるく下がりながら象の鼻の東端に達する。
第46防空隊は、この中央山地の頂にあるのだが、山頂へ上る自動車路は航空隊とは反対側の島の東端から緩い斜面を上るものしかない。したがって車は航空隊司令部から西岸を北上し、つぎに北側海岸を東へ行き、東端近くでUターン状に山の稜線にはいって、山を上り詰めて中央台地に達する大迂回ルートをとらなければならない。自動車路は、三角形の島の2辺と半を走ることになる。
私を乗せた迎えのトラックは、まず西海岸沿いの平坦地を北上するのだが、ここは1式陸上攻撃機の残骸の山がつづき、飛行場というより飛行機スクラップの廃棄場である。車はその中を縫うようにして進んだ。
『諸戦記』によると、昭和19年2月17日の米機動部隊の襲撃により、ラバウル向けのものが地上で破壊されたとある。 陸上攻撃機。陸上基地から発着するので艦載機より大型長距離。海軍では急降下爆撃するものを爆撃機、水平爆弾投下すものを攻撃機と呼んだ。
記憶では西海岸線はもっと短く、春島飛行場は1個所だとおもっていたが、今度の旅行で確かめられたのは、平地の北端が現在国際飛行場となっており、航空隊司令部のあったとおもう南端には、案内図上では別の滑走路跡がかかれている。
ここに今度泊まったトラックコンチネンタルホテルがあり、北端の飛行場から5キロも離れている。しかもこの間の道路沿いに春島の中心市街、つまり郵便局、銀行、スーパーマーケットがたちならんでいる。かって、この辺に1式陸攻の残骸のあったのだ。
陸攻用と戦闘機用の滑走路が北と南に2本あったのだろうか。しかも私が行ってからは、飛んでいる陸攻を見たことはなかった。西海岸は、私のいた中央台地からは西部山嶺の陰になるし、その後もあまり通ったこともないので、この辺の記憶はなはだ漠としている。
北側海岸にでると、平地はまったくなく、珊瑚礁の海岸から、すぐ椰子やその他の木の繁るの山腹となり、道は珊瑚礁の水際をはしりる。やがて東端にいたると燈台があり、近くに口径20センチ水平砲台がある。その手前を右折して山地にはいると、コンクリート造りの海軍の通信所がある。ここは標高10米位だが、稜線上だから北側の海も南側の海も見える。道はこれから西に向かい、稜線にそって蛇行しながら斜面を上る。両側は森林がつづく。
3 第46防空隊に着任
道は蛇行しながらやがて標高200メーター程の山頂に近ずくと、とつぜん森林帯が終わり、露岩の広がった裸台地にでる。土のあるところも表土は流されて赤褐色のちゃらちゃらした小砂利まじりの赤土である。これまでとは一変して視界は開け、両側の窓から広い海面と点在する島々が展望できる。
荒涼とした裸台地をしばらく進むと、露岩の緩斜面に丸木の門柱があり、傍らに小さな衛兵塔が立っている。これが第46防空隊の入口である。 門を入ると、左側にバンガロー風の本部建物がある。高床平屋建で、ベランダが巡らしてあり、北を向いた正面は開け放されている。
本部前はちょとした広場になっており、その先は崖になる。ここからは、正面眼下には春島北海岸線が見おろされ、その先は北の海面がひらけ、視界の中程に櫻島、小櫻島が並んでみえ、さらに遥かその先には環礁の白い線と環礁上の子島(ねじま)がみえ、その先は外洋と水平線になる。
視線を移せば、右下前方には今傍らを通ってきた春島燈台と通信所の無線塔があり、その先の海面をへだてて環礁には東水道がみえる。反対側、西方には、谷を越えて西部の山峯が対峙し、それに隠れた七曜島の端がみえる。
本部の裏は、やや小高い露岩の現れた傾斜面で雨水を集める集水地となっており、そこまで上れば南側海域に夏島と秋島がみえ、夏島の向こうに竹島、冬島、さらに先の海面に南水道のある環礁が遠望される。
本部の西側には黒塗り木造の貯水タンク群が貨車のように並んでいて、集水地から樋が渡されている。タンクの前が洗濯場兼風呂場で、ドラム缶風呂が数本並んでいる。タンクと道をへだてて烹炊(ほうすい)所がある。その道を奥、つまり西方に進むと、露岩台地はさらに西南に一段とせり上がり、ひろがった台地の頂上面となる。ここからは360度トラック礁湖が展望できる。高角砲陣地はここに造られている。
口径12センチ高角砲6門、25ミリ2連対空機銃1基、13ミリ対空機銃1基、探照灯2基。高角砲は3門づつの2ケ小隊、機銃1ケ小隊という編成である。6門の高角砲は2、30米間隔でほぼ円形に配置され、その北に機銃が配置されている。高角砲、機銃とも、1基づつ岩盤を掘って縁を土で盛り上げたドーナッツ型の掩体(えんたい)壕が中に据え付けられている。掩体壕はかなり高いから、外からは高角砲の砲身だけが突き出て見える。
小隊毎に小隊長指揮壕があり、全体の真ん中に隊長の指揮壕がある。指揮壕は外から見ると蟻塚のようで、中にいるものの頭だけがかろうじて見える。指揮壕と各壕の連絡は伝声管(でんせいかん:金属パイプを張り巡らしたもので両端にラッパ口があり、一方の口に向かってしゃべった声が他の口で聞き取られる)によっておこなう。
隊長の指揮壕には、さらに地下を掘り下げた1坪ほどの地下空間があり、電話当番がいる。K隊長はここに簡易ベッドを持ち込んで寝所としていた。夜の空襲のとき、本部からここまでくるのが大変だからである。ほかの幹部は本部で寝起きしていた。
着任早々のある夜、空襲警報があったとき、なにかあって私だけ少し遅れて本部を飛びだした。戦闘時には隊長指揮所に入ることになっていたのだが、おりから月のない闇夜で、砲台陣地までいったが指揮所も大砲の掩体もどこにあるのか見当がつかない。伝令の声とか砲の操作音などが聞こえてこないかと、地面に伏して耳を澄ましているうちに、とうとう敵機の爆音が聞こえてきて弱りはてた。
砲台が設置されたばかりの頃、伝声管の敷設が間に合わなくて、中継伝令を掩体の外に置いたところ、運悪く爆弾の破片か銃弾に当たって戦死したことがあったという。
これが、それまでのこの隊の唯一の戦死であった。その話を聞いていたから、壕の外に迷子でいるのは、恐ろしいばかりか、みっともない。ようやく聞こえてきた話し声で指揮壕を探し当てたときは、起死回生の思いであった。
兵員の兵舎というものはない。各小隊とも、それぞれ台地の縁の崖下、中腹に洞窟を掘って、これを居住区にしていた。したがって、それまでの部隊の日課は、大砲打と岩盤堀の明け暮れであったようだ。
***
話は、防空隊に着任したところから直ちに隊の配置図に移ってしまったが、そのまえにグアム島以来の麻袋軍服姿の始末にふれておかなければならない。
幸いに、隊には将校用戦闘服と防暑服(半袖半ズボンの装)が用意してあり、ようやくにして士官の威厳を取り戻すことができた。ただし襟に着ける階級章はなかったから、グアムで同期生からもらったのを誰かと半分分けしたものを、終わりまで胸にくっつけることになった。
軍刀は、先任兵曹が秘蔵していた日本刀を借り受けることにした。もっとも、この軍刀は、後日めずらしく視察にまわってきた司令の出迎えの整列で、「かしら右」の号令を掛けたときにつかっただけで、敗戦後アメリカ軍に提供する運命になって、結局は持ち主には返らずじまいとなった。
対空戦闘のときは、鉄帽(ヘルメット)をかぶり、双眼鏡を首に掛けるけれども、首から下はふだんの丸腰であるのはいうまでもない。
隊員は戦闘配置のとき以外は、シャツか裸でいた。トラック島は熱帯圏だけれども、汗をかくのは日盛りに山を下って平地を歩くときぐらいのもので、内地の夏よりはるかに過ごしやすい。とくにわが隊のような山頂暮らしは、気温と風光については最上の天地である。
4 第46防空隊(続き)
防空隊とはどういうものかを全く知らないまま赴任してきた。対空砲台のような組織は、どういうもので、いかに運営すべきかなどは、砲術学校で教える中心課題の1つであるべきものだが、学校の教科は射撃の仕方だけであった。
それはともかくとして、第46防空隊について述べよう。
この隊が組織上は第4艦隊の指揮下にあったことはたしかだが、司令部とは離れた別の島のてっぺんにおり、日常の戦闘について艦隊の指揮命令があるわけではない。
隊の隣に、艦隊司令部のレーダー見張所があり、敵機が来れば「空襲警報」という声が聞こえてくる。これが4艦隊の指令だといえないこともないが、司令部は対岸の夏島の防空壕に入っていて(本当は私はそこへ行ったことも見たこともない)、見張り所の報告を聞いているだけだ。敵機を見ているのは、見張り所と高角砲台だけだ。
砲台は自分の判断だけで弾を撃つ。また、私が着任した以降、艦隊から弾薬の補給を受けたことがない。食糧(後述の鰹の配給を別にして)の支給してもらうわけでもないから、実体は独立の部隊運営であった。
編成は、隊長の下に小隊長がおり、見張り、指揮(機銃)、射撃第1、第2、弾薬の各小隊があり、車両機械班は射撃第2小隊長が采配をとっていた。指揮小隊は、指揮官のもとで「射撃装置」を操作し、射撃小隊はそれに連動して砲を動かし、弾を込め発射するのが建て前のはずだが、指揮小隊は後でのべる事情で、隊長指揮所員と機銃員に分かれていた。
防空隊は陸上部隊だから陸軍式の小隊名を使ったのだろうが、実際の砲台運営とはかけ離れてゆき、しまいには小隊名も使われなくなった。
別に主計班、衛生班があった。食糧が窮屈になるにしたがい烹炊所を握る主計兵曹の、兵員の中での権力は絶対になって、彼らは「主計長」、「主計長」、と彼のことを呼んでいた。隊長は私に主計長兼務を任命したのだが、私の主計長は名目だけで、やる気も能力もなく、隊長が実質主計長でもあった。防空隊は陸戦装備として小銃をめいめいもっていたが、使うことはなかった。
隊の幹部は、隊長がK中尉、小隊長は兵曹長4人、いずれも下士官から叩き上げの特務士官であり、これに予備学生出身の私が先任小隊長として加わったわけである。
K隊長は小柄で痩せぎすで、日に焼けて浅黒く、しわの深い、田舎のおじさん風のおとなしい人であったが、実務に掛けてはさすがにベテランで、兼務主計長としての私のでる幕はなかった。
先任のN兵曹長は、胃腸がわるく青白い顔をしていたが、間もなく夏島の海軍病院に入院し、やがて内地送還となった。病気送還は計ってやったことだと言う噂もあった。
W兵曹長は射撃第1小隊担当、私が12センチ砲の構造の疑問など、砲の技術面のこと話しをした唯一の人だったが、この人も間もなく夏島の司令部の何処かに転勤となった。
I兵曹長は、練習艦隊の相撲の大関だったという、柏戸張りの筋肉質の大男で、ガキ大将のごとく兵員を叱咤激励して使うのがうまかった。
「ニミッツ(米太平洋艦隊司令長官)をやっつけて、金門湾(だかハドソン湾)で観艦式をやる」
が、彼の得意の口上。機銃小隊担当。のちに、新設された隣の水平砲台部隊に移った。
O兵曹長は射撃第2小隊担当。娑婆で自動車関係の仕事でもやっていた人か、車両や発電機関係を取り仕切っていた。小太り、生白い顔にちょび髭を付けていた。I氏も付けていたから、兵曹長クラスにちょび髭が流行していたようだ。粘液質で少々ネクラのところがあり、士官室の人事移動に絡んだトラブルメーカーでもあった。
彼は、だれか高級士官の噂がでたとき、「何某は赤城(ミッドウエー海戦で撃沈された空母)がやられたとき、慌てて信号旗を頭からかぶってワアワアいってた」などといっていたから、ミッドウエー海戦のとき赤城の乗組員だったのだ。
今考えると、口止めされていたのか、あるいはあまり愉快でなっかたのか、その時以外、赤城の話を聞いたことはなかった。O兵曹長のほかの人たちも、それぞれ皆自分の戦歴をまったく語らなかった。
私としては、違った世界に飛び込んだばかりで当面の事態に対応するのが精いっぱいで、彼らの来歴を問いただす余裕もなかったのだろうが、いろいろなことを聞いておかなかったのは、この戦記を書く上では、たいへん惜しいことであった。
私は見張小隊担当、といっても形式だけで、戦闘時は隊長指揮壕におり、やがて弾のなくなる頃、高角砲指揮専門となった。
注、ミッドウェー海戦
日本海軍は緒戦の真珠湾奇襲攻撃で米太平洋艦隊の戦艦群に壊滅的打撃を与えたが、ハワイを離れていた米機動部隊(空母)は攻撃を免れていた。
米の強大な建艦能力による戦力増強の近いことを懼れていた山本連合艦隊司令長官は、ミッドウエー島を攻略して米機動部隊を誘い出し、これを撃破して有利な状況を造りだし、早期和平の緒を導こうと考えた。
翌昭和17年(1942)6月、太平洋戦史上空前の大艦隊がミッドウエー作戦に動員された。
作戦の主役は先の真珠湾攻撃の成功で意気軒昂の南雲中将率いる機動部隊(「赤城」等大型空母4隻を基幹とする)。 これに加うるにミッドウエー攻略部隊(上陸作戦部隊)、アリューシャン攻略部隊(アッツ島、キスカ島攻略)。そして背後に山本長官自らが乗る旗艦「大和」以下の主力部隊。
動員された艦船は350隻(内、空母8、戦艦11、巡洋艦22、駆逐艦65、潜水艦21)、飛行機1000機、将兵10万人という大規模なものであった。
連合艦隊の出動は穏密裏に行われたにも拘わらず、米側はこの作戦行動を電報の暗号解読により事前に察知しており、ミッドウエー島防備態勢を固めるとともに、その海域に空母3隻、巡洋艦8隻、駆逐艦15隻の機動部隊を待機させていた。注
6月4日、米機動部隊はまだハワイにいると思いこんでいる南雲機動部隊は、まずミッドウエー基地の攻撃を始めたが、ようやく敵機動部隊の所在に気付いたときはすでに遅く、米機動部隊の爆撃機の襲撃をうけ応戦するまもなく空母3隻は炎上の後、撃沈または自沈、1隻もまもなく撃沈されてしまった。
米側は空母1隻駆逐艦1隻を失ったが、日本連合艦隊は主戦力の空母4隻とその航空機全部を失い、なすことなくトラック島や内地に撤退した。
このようにミッドウエー海戦で、(粗)戦力は米を上回っていたにも拘わらず、日本海軍が惨敗した原因は、米国の科学技術の優秀性にあっただけではなく、人的要因すなわち日本海軍の情報収集能力の不足、作戦中のずさんな索敵、実戦における指揮能力の欠如にもあった。以降、日本海軍は戦力において2度と優位に立つことできず、坂を転げるように敗退をつづけていった。
ミッドウエー海戦には、澤地久枝著、「滄海(うみ)よ眠れ」という、他の戦記、回顧録には見られないユニークな著作がある。ここには、戦争に翻弄された将兵とその家族の消息のほか、関係者が戦後書いて広く行き渡っている海戦記録には、身内の過誤を隠すためのねつ造があるという指摘と、知られていない米軍捕虜(墜落した米機の搭乗員)の虐殺あるいは漂流日本兵の置き去り等、旧海軍関係者が触れられたくない部分が容赦なく暴かれている。
そのために、旧海軍関係者から強い抵抗を受けたといわれているし(同書、文庫版解説)、著者も文中で、40年もたって何をいまさら暴くのかといった反発が新聞投書に現れたことをしるしているが、破れた日本海軍のいつわらざる姿を知るには、こういう作家の力も必要であろう。
*
ミドウエーのあまりにも深刻な敗戦は、国民にはひた隠しにされ(戦勝と報道された)、海軍部内においてさえ公表以外は一切が秘密にされていた。内地に帰った機動部隊の生き残り将兵(護衛駆逐艦に収容された)は「各基地に分けて皆缶詰にされ、下士官/兵は家族との面会も許されないままやがて全員、南方へ転属された」(阿川弘之、「山本五十六」)
海軍では、上等兵曹の最上席者は先任兵曹とよばれ、下士官・兵の実質統率者で、日々の作業は先任兵曹の采配で運営された。わが隊の先任兵曹、A上等兵曹は、年令50歳近くの応召兵で、その頃の私には、老人のように思えた。国に帰れば、池袋に近い私電駅の駅前の八百屋の主人である。物腰の優しい穏和な人柄で、息子が海軍兵学校に入っているのが自慢だった。
私は、戦後、まだ静岡にいた頃、勤め口探しのため上京したおりに訪ねたことがあったが、気の毒なことに、息子を海軍兵学校のあった江田島で、空襲により亡くしていた。
下士官は大体優秀で頼みになるものが多かった。特技のある人もいて、弾薬係のK兵曹のごときは、洞窟堀のハッパを扱わさせれば、風貌からしてまったくの飯場の親方であった。
兵の方は、少年兵出身は別として、だいたいが補充兵で、生きがいいとはいえなかった。なれない世界に引っぱり込まれ、下積みで追い回されていれば、できることもできなくなるというものだ。これらの補充兵諸君も、しまいには全員下士官に昇進したのだが、後の補充がないので、いつまでも新兵の仕事をしなければならなかった。
少年兵組は中学上級生くらいの年齢で、兵曹長諸氏のアイドルで、従兵を順番にやらされていた。
私の履歴書によると、「19年7月18日、第41警備隊附に補す」とある。サイパンにあった中部太平洋艦隊司令部が消滅して、編成替えがあったのであろう。この時第46防空隊の名はなくなり、部隊は夏島の41警備隊の傘下に入ったのだが、実際は防空隊のときと全く変わりはない。ただ、隊名は隊長名でよぶK隊となった。
5 対空戦闘
赴任当初は、トラック島には連日、B24の空襲があった。B24は4発の大型爆撃機で、陸上基地から來る。
昼は数10機の編隊でたいてい西南方向からきた。隊では〇〇定期便と呼んでいたが、今〇〇 の名前が思いだせない。地図を見ての方向からいえばニューギニヤかアドミラルティ諸島であるが記憶を呼び起こすような発音の地名が見当たらない。 注 後に述べる理由で、私の方向感覚は180度逆で、東(南)方向の誤りあったかも知れない。そうすれば2月に米軍に落とされたマーシャル諸島クエゼリン方向と一致する。
編隊飛行の爆弾は、たいてい夏島の海軍基地付近に落としていくから、当方には被害のおそれはない。しかも、こちらから斜め正面にみえ、高角砲を撃つには絶好の方向だから、赴任したばかりの頃、私の指揮ではなかったが、1回に30発近く打ったことがある。しかし、弾丸の補給がなくなることがわかってからは、こういう撃ち方はできなくなった。なにしろ保有は100発足らずになっていたから。
昼の空襲では、東からくるものもあった。これも、いま『諸戦記』でみると、マーシャル諸島のクエゼリン島あたりからであろうか。夏島の向こうにある竹島の飛行場が爆撃されたときの光景がよく記憶に残っている。というのは、竹島爆撃では飛行機が東か西へ飛ぶのがこちらからは真横からみる形になる。
やや遠いのでこちらは黙って見ているだけだが、夏島の高角砲が撃つ着弾位置がよくみえて参考になった。夏島の砲台は、12.7センチ2連の、館山砲術学校で訓練を受けた海軍の代表的高角砲で、わが隊の砲にくらべればはるかに精度もよく弾も豊富にもっていたようだが、竹島の零戦がいなくなるとともに竹島爆撃もなくなった。
夜の空襲は、たいてい単機でくるが、偵察でもしているようにあちらこちら飛び廻り、あげくに爆弾を落としてかえっていく。こちらは、打つ気がなくても、配置に附いている。相手は爆撃目標が一定していないから、いつ自分のところへ落とされるか厄介である。
1度、至近距離に落とされたことがあった。爆弾の落下音が聞こえるときは大丈夫だなどと聞いていたから平気でいたが、至近弾でもザーと短い音が聞こえる。ただ、掩体(えんたい)の外に落ちる限り、岩肌が少々えぐられるだけで、掩体の中は無事である。
もっとも、これは知らずにいるからの強がりである。
それからずっと後、射撃の実施を制限してからのことだが、昼間、大型機が単機で偵察兼務の爆撃でやってきた。こちらは射撃するつもりはないが、義務で1門くらい配置に着けて、双眼鏡でみていると、どうやらこちらへ向かってくる。と、見上げて真正面ちょうどと思われる位置にきたとき、ぱらぱらと爆弾を落とし始めた。いけないと思う。
大型双眼鏡で覗いている観測員がいうーー
「あっ、落ちてきます」
K隊長もそうみたか、
「退避」
というが早いか、指揮壕にいる全員が壕の内壁に掘ってある伝令員用の窪みへ小さくなって潜り込んだ。
聞きなれない命令に、砲側からは伝声管の声で
「何か、何か」
と訊きただしている。
指揮壕では隅の伝令のはいる穴で、皆丸くなって、いまかいまかと爆弾が落ちてくるのを待っている。しかし、案に相違して、爆弾は遠く谷間に落ち、互いにほっとしたり、ばつが悪かったりした。本当に爆弾が頭に落ちてくると思えば平気でいられるわけがない。
注、B24とは、コンソリデーテッド4発大型爆撃機、米陸軍機。マーシャル諸島クエゼリンの陥落(昭19、2)により、トラックはその爆撃圏に入った。戦闘機は、航続距離の関係で、後述のロッキードP38があらわれるまで、機動部隊のもの以外は、トラックにはこない。
6 夜間戦闘機と探照灯
夜の敵機は、前にも述べたようにB24が単機で来て偵察でもするようにやや低空であちこちを飛び回った末(夜間の偵察など当時の日本では考えられないことではあったが)、不特定の処に爆弾を落として行くから始末が悪い。
ところが、ある時から春島の航空隊から「月光」という新鋭の夜間戦闘機が1機、これを迎えて飛び立つようになった。この飛行機は、斜め上と下をむいた(どちらか一方か?)20ミリ機銃を持っていて、大型機の後方、上か下から併行して打ち掛け、各地でなかなかの成績を挙げてたいようだ。
ただ、レーダーをもっていないのか、あっても性能が悪いのか、名前どおり闇夜では相手が見えぬらしい。敵機の来襲を迎えて飛び立っても、地上で爆音を聞いていると、敵機と反対の方ばかり飛んでいるようにおもえた。
こういうとき、探照灯の登場となる。探照灯が敵機をとらえると、「月光」は初めて獲物を発見し襲いかかるわけである。探照灯は、わが隊を含め、夏島その他に2、3ヶ所あった。
わが隊の探照灯で知るかぎり、目標を探しだす方法は極めて原始的であった。すなわち耳で爆音を聞きながら、敵機のおよその見当をつけ、その方向の空をめがけて上下左右に光芒を振りまわして探しだすわけである。
この照射索敵作業は、探照灯に付いている兵員が手動で直接操作する(遠隔操縦装置があったが、以前の空襲で被弾して動かなかった)のであるから、指揮官は、離れた指揮所で「照射始め」を命令するだけで、後は探照灯に付いている兵員まかせである。
双眼鏡を使うと、夜間でも視界が多少明るくなり機影を見ることができると、前任のN兵曹長はいっていたが、私は成功したことはなかった。真っ暗な空で爆音を聞いていると、爆音の位置に気が惹かれ、その前方にあるはずの機をとらえられない。
わが探照灯員も、いつもなかなか敵機を探しだせずにいると、よその探照灯に名手がいるとみえて、うまくとらえて敵影を映しだしてくれる。そうなれば、こちらもそれに合わせて照射できる。1度うつしだされた目標を追い続けるのは容易である。かくして、あらぬ方を飛んでいた「月光」に見つかり、その餌食となる。
遠くの海上に落ちた敵機の燃料が、静寂の闇の中で、いつまでも燃えつづけているさまは神秘的である。
だがいつも、そううまくいくわけではない。探照灯につかまると、敵機はあわてて爆弾を落として退散する。その爆弾が、わが砲台の下の方の、陸軍の大隊長がひそむ谷に落ちたことがある。翌朝、大隊長から探照灯照射にクレームをつけてきた。
やがて、敵の夜間爆撃もなくなって、この大隊長の心配もなくなった。
7 春島の同期生
着任後、しばらくしてから、春島に館山砲術学校3期予備学生の同期が2人いることが分かった。MとIといい、どちらもそれぞれ飛行場に近い対空機銃の部隊にいた。
彼らは、館山をでるときの教官の忠告を守って、航空機に便乗し、結局輸送船の私よりも無事かつ早く着いた。おかげで、4月29日の米機動部隊来襲に間にあったのである。
離れているので、滅多に会うこともなかったが、あるとき近い方にいるI少尉がこんな情報を持ってきた。トラックの状勢が悪いので、われわれの内地との交替はないよう、司令部が海軍省に断ったというものである。
じつは、われわれの間では、早期卒業組(館山砲術学校)は次期予備学生の教官要員として、内地へ呼び戻されるであろうという希望的予測が秘かに流れていたのだが、いよいよトラックに居座る覚悟をきめなければならなくなった。
8 高角砲の射撃
(測距儀)
第46防空隊の12センチ高角砲陣地を始めて見て、驚き、かつ、がっかりした。第1は、攻撃目標までの距離を計る「測距儀(そっきょぎ)」がないことである。第2は高角砲射撃の頭脳となる「射撃装置」がなく、機銃についているような、傘型(かさがた)の照準器で直接目標を狙うものであることである。これは無茶な装備であるが、こうなっているには理由があったという。
わが防空隊は、この年の2月、ちょうど米機動部隊来襲の直前に、輸送船で兵器とともにトラックに着いた。兵員は無事上陸したが、大砲など兵器は荷揚げが済まないうちに、18日の空襲で船もろとも沈められてしまった。それで今の兵器をなんとかかき集めて設置したというのだ。
この装備が無茶だというわけを説明するには、高角砲の射撃操作法を少し説明しておかなければならない。
目標を狙うには方向と距離を定めなければならない。まず、上空の動かない目標を撃つと仮定しよう。大砲の弾丸の方向、つまり砲身の方向は、砲身の両側の座席にいる射手と旋回手が、照準用眼鏡で目標を狙ってハンドル操作して決める。(射手は砲身を上下方向に、旋回手は砲全体を水平方向に回転させる。)
また、距離を測るのは、測距手が測距儀によって行う。距離・高さが決まれば、信管手は信管(信管は弾丸本体内の炸薬(さくやく)を破裂させる起爆装置)に内蔵されたタイマーに、弾丸の速度に距離による時間を乗じた目盛りを仕掛ける。射手が引き金をひけば信管を付けた弾丸が空間を飛んで、目標(の近く)で炸裂する。(高角砲は、弾丸を目標に貫通させるのでなく、目標の手前で破裂させ、砕片を周囲に散らして目標に当たる範囲を広げるような方式の砲弾を使う。)
つまり距離の測定は、方向を決めるのと並んだ最重要事項である。これを測距儀なしで、たとえば10キロ先の飛行機までの距離を決めようとするのは、下界から富士山頂測候所までの距離を目測で決めようとするようなものである。
つぎに動く目標を考える。目標は水平直線飛行するもとする。弾丸の速度を秒速700メートルとしよう。10キロまで届くにはおよそ14秒かかる。300ノットの飛行機では2、100メートル余り動く時間である。つまりこれだけの方向・距離の修正が必要である。
目標の将来位置決定の「原始的方法」ついては、館山砲術学校で、操法の計算をしたり、針金に吊った模型飛行機を前にして、模擬射撃の号令を掛けさせられたりしたことは前にも触れた。(目標までの距離をあらかじめ設定しておいて打ち始める方式。)
しかしこれでは仮に測距・方向がいかに正確であったにしても、待ち伏せ・出会い頭の確率が問題である。かりに弾を込めて発射するまでのインターバルを3秒として、そのインターバルの間に発射があったとしても、それだけでも目標と破裂点とのずれは、計算上、0から450メートルの範囲に及ぶ。この待ち伏せ法に、測距離、方向、目標速度推定の誤差を重ねると万が一の僥倖をたのむのもはばかられる結果になる。
(射撃装置)
開戦後、シンガポールや何処かで、イギリス軍、アメリカ軍の「射撃装置」を分捕り、これをコピーした「ーー式射撃装置(ーーは失念)」が登場した。砲術学校の最後の教程ではこれを習い、仕上げの実弾射撃もこれが使われた。戦中、「大和」「武蔵」が大改装したのもこれだろう。
「射撃装置」は、四角な郵便ポストより少し大きめの、方位360度回転できる箱型の計算機と考えればよい。箱の両側に、高角砲と同じように照準用眼鏡がついていて射手と旋回手が目標を追ってハンドルを操作する。別に、弾丸の速度は既定値として設定されており、測距手から報告された目標の高度が設定される(水平飛行を前提)。
射手、旋回手が目標に照準を合わせつづけておれば、目標の現在位置の仰角と方位およびそれぞれの速度が連続的に入力されることになる。射撃装置はこれらの入力データから目標の将来位置の仰角、方位角、到達時間(距離)がリアルタイムで連続して算出できる仕組みになっている。
今のコンピュターなら、自動的に、これらの将来値をアウトプットすることができると思うが、この装置では途中の計算をするためになお2、3人の操作員が箱の側面の窓を見ながらハンドル操作をするのである。
アウトプットデータは、セルシンモーターという伝導装置によって、砲側に回転する針の動きとして傳えられる。砲側の射手、旋回手はハンドル操作して自分の針をこれにあわせておれば、砲身は常に必要な方向を指していることになる。信管手は同様に信管時間装置を操作し、時間は弾丸を込める時に機械的に信管時計に刻まれ、同時に発射される。こうして打続ければ、弾丸の破裂点は原始的待ち伏せ方式と違い、少なくとも目標機の飛行線にそって現れる。
これが、12.7センチ連装高角砲と連動する「射撃装置」であり、夏島の砲台も多分これであったと思う。
米軍はこの射撃装置と組み合わせたレーダーを戦前の段階でもっていた。日本は真似をしても、ついに射撃用レーダーは作れなかった(筆者が館山砲術学校で学んだ限り)。米軍は戦争中VT信管を開発して、レーダー付射撃装置で目標に接近させた砲弾を、確実に破裂させることに成功した。これについては次項で触れることにしよう。
(傘型照準器)
これに対し、第46防空隊の12センチ高角砲は、射撃装置の代わりに、傘型照準器で目標の将来位置をきめる方式である。傘型照準器とは(映画の飛行機銃撃場面によくでる)照星が蜘蛛の巣のような同心楕円の輪になっている照準器で、機銃で使われる方式である。
目標までの距離は照門(手前にある照準穴)と蜘蛛の巣状の輪の間隔によって調節する。蜘蛛の巣の同心円が敵機の時速を表す。同心円の外側のものほど速い時速を示す。敵機が相当する時速の同心円上にあって、機首を同心円の中心になるように照準を定めればよい。
これは仰角が適当な角度のばあい、原始的射撃法より勝っていよう。実際、仰角が小さい場合は目標はまだ遠方にあり、もっと近くまで来たら撃てばいい。目標が蜘蛛の巣の右か左から中央に向かう場合は進路が左右にはずれたままだから、撃っても無駄だ。また仰角が大きすぎる場合とは撃ち方やめの体勢(目標が頭上を通り越す)であろう。
しかし距離を固定する「待ち伏せ・出会い頭」射撃方法は、原始射撃法とおなじである。しかも、たとえばこの照準器では、10キロ先の目標の飛行機を照準用眼鏡ではなく機銃のように肉眼で狙いを付けようというのであるから、あまりにも粗末すぎる。
機銃の傘型照準器の場合は、目標までの距離が数百米で、しかも曳光弾といって撃った弾筋が目にみえる弾が何発目かに入っているから、ホースで水を掛けるように撃ちながら射撃方向を調節できる。機銃は機敏な操作が必要だから、むしろ簡単な照準器が適している。高角砲とは根本的に違うのだ。12センチ砲の作成者がそれを知らないはずはない。とすれば、この高角砲は、戦争末期のご他聞に漏れず、窮余の末、員数合わせに造られたものであろう。
照準器も照準器だが、測距儀がないということは高角砲台としては絶望的な欠落である。目標までの距離の測定が高角砲の射撃精度の基本になることはすでに述べた通りであるが、10キロメーター先の空飛ぶ飛行機までの距離を目測で決めるなど言語道断のむちゃくちゃである。
第四艦隊司令部は何をしていたのか。トラックには陸海あわせて何万という将兵が送り込まれていた。しかし高角砲台は私の知る限り、わずかに2箇所、しかもその1つは、測距儀も持たないのだ。 第46防空隊が置かれた昭和19年の前期の時点で、日本海軍がいくら貧していたとはいえ測距儀の1基、2基調達できぬはずはない。
だが、いまになっては内地からの補給はまったく望めない。いろいろ考えたすえ、つぎの方法を案じた。
指揮所にある大型双眼鏡には視野に分画目盛りがでていて、見たものの視角を計ることができる。目標のB24の翼長がわかっているから、距離と視角の関係表を作っておき、観測員に正面からくる敵機の翼の分画を読みとり次つぎ報告させ、距離を求めるという方法である。この測距法の精度は甚だおぼつかないものであるが、それでも、弾丸が破裂したときの煙が飛行機とはまるで違った方向にでることだけはなくなった。
9 レーダー見張所
本部建物の隣、同じ山頂の一画に(四艦隊所属の)レーダー(電波探信儀、略して電探と言う)の見張所があった。ここも360度見晴らしの効く絶好の位置にあり、50キロ(もっと遠くからであったか?)圏内の機影はくまなく捕らえることができた。
私がトラック島にいる間に、軍事的にみてこの見張り用レーダーほどトラック島の将兵に貢献したものは他にあるまい。なぜならば、毎日の空襲の都度この見張り所からの通報で、われわれ対空部隊が配置に着くことはもちろん、あちこちのほかの陸海軍将兵はそれぞれの防空壕に退避することができたのである。これがなければ、離れたところでの芋作りなぞおちおちできなかったであろう。
どういう訳か、この見張り所は、戦争が終わるまで、無事に活躍し続けた。もし米軍がこの事実を知っていて、ここのレーダーアンテナを爆撃しておれば、トラック島の日常行動はまるっきり惨めになっていたにちがいない。
面白いことには、米軍の編隊爆撃では、飛行中かならず空中にアルミ箔らしい金属片をばら撒いていた。ある爆撃の時、見張り所の洞窟でレーダー画面を見せてもらったことがある。画面を見ていると、まづ編隊が現れ、やがて近づいた編隊から金属片が撒かれ、つぎに止まっている金属片群を残して離れていく飛行機の陰がよく分かる。
これは明らかに、レーダー射撃を妨害しようとしているものだが、わが方はレーダー射撃のような武器は持ち合わせないのだから、買いかぶられたものというべきか。(彼らにはレーダー射撃が常識の時代になっていたのだ。)
ともかくも、ここでも米軍との差を思い知らされた。
館山砲術学校の射撃装置教科のとき、「射撃装置」の箱の上に得体の知れない箱が重ねてあるのを見たが、教官からこれは電探用だが、まだ使われるとこまできていないと聞かされた。アメリカの原型では電探と連携していたが、日本の技術では何処かが複製できないでいたのだろう。
レーダーによる測定は、夜はもちろん、昼でも距離の観測は測距儀より優れているらしい。測距儀のような光学的測定法では遠距離になるほど、また機械の巾が狭いほど、誤差が大きくなるが、電波によるレーダー測定では、測定可能な範囲内では誤差は一定であるという。
『諸戦』(阿川弘之著「軍艦長門の生涯」・他)によると、アメリカの対空火砲の技術は、レーダー射撃の他、砲弾に付けられたVT信管の登場によって飛躍的に高まった。VT信管の存在を日本が知ったのは戦後のことだが、アメリカが最初に使ったのはガダルカナル戦の末期(昭和18年1月)である。
この信管は自ら電波を発信、反射波を受信し、目標の一定距離に入ると自動的に砲弾を破裂させる仕組みになっているという。あらかじめ時間を設定するタイマー付き信管より、爆発のタイミングがはるかに高い命中確率であることは容易に納得できる。
私の知識では、高角砲は水平飛行の爆撃機を相手にするもので、急降下で突っ込んでくる目標には機銃しか手がないと思っていたが、アメリカの5インチ対空砲弾(わが12センチ高角砲弾と同じ大きさだ)は、レーダー付射撃装置とこのVT信管の威力により、突っ込んでくる日本機を決定的に捉え葬ったのであろう。
10 ゼロ戦とタコ足爆弾
トラックの航空戦力は、この年の2月と4月の米機動部隊の来襲で大損害を受けた上、航空機は陸上兵力と違って移動が早いから、戦局の移るごとに変わってしまう。私が赴任した当初は、ゼロ戦(零式戦闘機)が20機位はいたようだ。しかしまもなくサイパンあたりに駆り出されていってしまったのだろう、敵爆撃機編隊がきて、応戦に飛び立つことがあっても2、3機にすぎなくなってしまった。
このころのゼロ戦の戦闘方法は、敵編隊の上空から急降下して空中で破裂する焼夷(?)爆弾を投ずるものであった。地上から見ていると爆発すると空中に白い煙が蛸の足のようにひろがるので、われわれは、タコ足爆弾とよんでいた。
編隊の大型機が打ち出す機銃弾が烈しいので、よほど遠くから爆弾を放すためであろう、爆弾は見当外れで破裂し、蛸足が編隊を捕らえるようにひろがったのを見たことがなかった。
私が初めて春島について22航戦司令部に泊めてもらった翌朝の食事の際、司令部の上官から「防空隊の高角砲は、もう少し飛行機の飛んでる方向に撃つようにしろよ」とひやかされた。これから着任する隊のことではあるがいささか恥ずかしかった。
それがいまや零戦のタコ爆弾にあてはまる言葉になってしまった。
しかし、修理し直しては飛び立ったであろう1機2機のゼロ戦が、大型機編隊に立ち向かうさまは、見ていて痛々しかった。そして、まもなく飛び立つ戦闘機は1機もなくなってしまった。
11 サイパン、グアム陥落
防空隊には、日々の戦闘情報のようなものは流されてはこなかったが、毎日夏島に公用使(文書類受取りの兵士)を派遣していて、ときどき第4艦隊の艦内新聞というガリ版刷りのニュースが渡された。マリアナ諸島(サイパン、グアム等)に対する米軍の攻撃もこれで大略の模様はわかった。
いま、『諸戦記』によって戦局の日付けを辿ってみると次の通りである。
昭和19年(1944)
6月11日、 米機動部隊、ロタ、サイパン、テニアン、グアムを空襲。
同15日、 米軍、サイパン島に上陸開始。
7月9日までに3万の日本軍全滅。(大本営発表は7月18日)
7月21日、米軍、グアム島に上陸。8月11日、占領完了。
7月23日、米軍、テニアン島に上陸。8月3日、占領完了。
私がトラック島に着任したのが5月20日であるから、着任当時の毎日の米大型機トラック来襲はマリアナ攻略の準備であったわけだ。
当時、マリアナの戦闘の詳細は知る由もないが、艦内新聞で、日本軍は、米軍の上陸前、徹底的に艦砲と爆撃により攻撃されたとあった。1カ月前に見たサイパン島の海岸に置かれた、ほとんど裸の野砲陣、道路際に野積みにされた物資の山などから、およその戦闘の状況が想像できた。
『諸戦記』(児島襄、「太平洋戦争」)には、現地軍司令官のとった作戦は、『水際撃滅戦法』だったと書いてあるが、あの防備は兵員と物資を陸揚げしたにすぎない。
連合艦隊が数カ月前まで泊地としていたトラックでさえお粗末な防備である。サイパン、グアムがまともな防衛戦ができたとは到底考えられない。上陸から占領完了まで1、2ヶ月かかっているといっても、広い島内の掃討に時間を要したのであって、戦闘が継続したとは到底考えられない。それを中央の参謀総長は、「サイパンは難攻不落です」などといっていたというから、送り込まれて戦わされたものらの無念さを思うと言葉もない。
12 サイパン島補遺
前章(トラック島へ着くまで)の原稿コピーを、新潟の病舎にある学生時代の先輩S氏に、無聊の慰めにもと送ったところ、受取のはがき中に、「貴文中、サイパン島に寄りしところで思いだしたが、七生寮(われわれの高校当時の剣道部の合宿)の寮生中、サイパン島玉砕に散華したWはその頃、サイパンに駐在していたかどうか判らないが‥‥ 」と、あった。
それで次のことを思いだした。
私はトラック島へ出発する直前、そのころ静岡に住んでいた両親に別れを告げにいった。ついでに市内の親戚に挨拶に立ち寄ったところ、偶然にもW少尉がそこに下宿していて、いま連隊に出勤中だという。W氏は、七生i寮の先輩である。早速、静岡35連隊を訪ねた。
なりたての海軍少尉がおそるおそる営門に近づくと、衛兵に大声で「敬礼」と直立敬礼され、どきっとしたのを覚えている。衛兵所の前で待っていると、カーキ色の軍服姿のW少尉が、特徴のあるテクテク歩きでやってくる。日差しのまぶしい日であった。
何か勤務中らしく、短い立ち話で分かれたが、きっと部隊の出発前で、忙しかったのであろう。2人とも同じ方向へ行こうとしていたにもかかわらず、その時互いの行き先を話した覚えはない。
『諸戦記』を見るとサイパン守備部隊に第43師団第135連隊というのがある。静岡の35連隊と似ているから、W氏の所属はここだったかもしれない。
「(米攻略軍の)砲爆撃の轟音のなかで、敵の上陸を迎える斎藤中將は、まったく自信がなかった。中將の着任は5月下旬。‥‥ 第43師団の殿(しんがり)7000人は、5月30日に館山を出発、ようやく1週間前に到着したばかりだった。」(小島 襄「太平洋戦争」)
とすれば、私はW氏の到着よりわずかに早くサイパンを立ち去ったことになる。なんともへたくそな、無責任な戦争にかりだされたものだ。