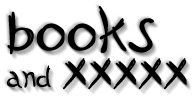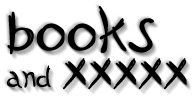|
『うるさい日本の私』を読み終えた。
「スピーカー音恐怖症」である著者は、否応なく耳に飛び込んでくるスピーカーによる騒音が我慢ならない。そこでそれらの「発音源者」──交通機関、企業、商店、自治体、省庁など──に抗議に出向いては議論また議論の日々……。
この本は、そんな著者の戦闘の記録であり、また「音漬け社会」を許す日本人へ向けての提言の書でもある。
確かに、日本はうるさい。
駅で、電車やバスの中で、デパートで、銀行で、商店街で、その他いたるところで、お礼やら注意やら禁止事項やらご案内やらBGMやらが絶えまなく流され続けている。
著者の言うとおり、それらのほとんどは不要なものだと、私も思う。
しかし残念ながら、私は著者の味方ではない。むしろ対極に位置する者のひとりである。
疑いようなく(著者の言うところの)マジョリティである私は、垂れ流しの音の中を毎日平気で歩けるのだ。選挙カーや布教活動や竿だけ屋など、ほんの一部の例外を除いては、あまり気にならない。へたすると、耳にすら入っていない。
どのみち聞こえちゃいないものなのだから、あってもなくてもいいよ。
世に溢れるお礼やら注意やら禁止事項やらご案内やらBGMやらを不要だと思ったのは、つまりそういうわけである。
こうした私のような鈍感な耳を持つマジョリティに対しても、著者は厳しい目を向ける。
日本が「音漬け社会」から脱出できないのは、音を流す側と同等もしくはそれ以上に、受け取る側に問題があるからなのだ、と。
電車の中で鳴る他人の携帯電話には神経質なくせに、「携帯電話は御遠慮ください」という車内アナウンスには寛容でいられる私は、言われてみればなるほど、我ながら充分おかしい。
そして、この歪みは日本人が美徳とする「語らず察する」態度から生じたもので、パブリックな場で「自分自身の個人的立場」から何かを「語る」ことができないことこそが無駄なアナウンスの氾濫に繋がっているのだとする著者の意見にも、一理ありと正直思った。
だが、著者の未来はこの先も当分暗澹たるものだろうことは想像するに難くない。
「音漬け社会」から脱するために“日本人は「察する」美学から「語る」美学への変換を遂げるべきだ”“日本古来の礼儀や美徳をかなぐり捨てよ”と著者は言う。“それが実行できぬならあなたは「音漬け社会」の加害者だ”とも。
けどなぁ。
何にせよ、意識の変革って難しいよ。仮に日本人が「語る」美学への変換を遂げられたとして、それっていったい今から何年後の話だろ? よほどの起爆剤がないかぎり、突如一斉の変化なんて無理だよなぁ……。
それと、私が思うに、「察する」美学ってこれからどんどん消えていくんじゃないかな。でもって「語る」美学も築かれないまま、世の中には「対話」も「議論」もない「自己主張」だけがはびこっていくんだ。他人の話なんてますます聞かれなくなるから、いたるところのスピーカーは今以上に声を張り上げる方法で気を引こうとするに違いない。
あ、でもそうなったら、さすがにマジョリティからも「うるさい!」という苦情の声があがるかも。おおっ、もしかしたらそれが、脱「音漬け社会」に繋がったりして。いや、繋がらないか……。
……なぁ〜んてことを仕事の帰りにつらつら考えながら歩いた。気が付いたら家だった。
その間の──改札口の、ホームの、車内の、駅前広場の、商店街の、スピーカーから流れていたはずの音を、案の定、私は何ひとつたりとも覚えてなかった。
|
 |
|