なお右上に見えるのは爪楊枝の頭です。
彼らの大きさをご想像ください。
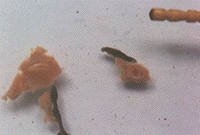
1997.4.29
エサを与えてみた。「切っても切ってもプラナリア」によれば通常は週に1度でいいらしい。飼い易くて助かる。
近所の鳥肉屋で新鮮な鶏レバーを買ってきた。適当に小さく…米粒大くらいに切って3、4片を水の中にポトン。プラナリアたち、はじめのうちは「何これ?」風に、横を通り過ぎたり、上を滑ったりしていたが…。
あっ、1匹張り付いた! よぉし、食ってる!
その後徐々に、しかし次々と寄ってきては張り付いて、やがてレバーの破片がプラナリアの塊と化した。なんだか嬉しいぞ。おーい、おまえら、ここのメシは美味いかー?
それにしても。
プラナリアの口は、実は頭部ではなく(私たちの感覚で言うところの)腹部にある。つまり彼らは、腹でエサに食らいつくのだ。本で読み、既にそういう仕組なのだとは解っちゃいたが、目のあたりにしてみると、やはりけっこう妙な風景。
おおっ! レバーに腹をくっ付けたまま、頭浮かせて揺らしてら。それってもしかして「美味しい〜」のポーズか? そうかい、そうかい、そりゃあよかった。
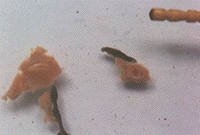
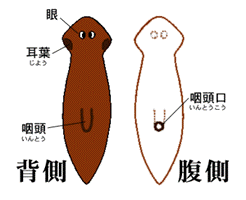 |
咽頭と呼ばれる部分がプラナリアの口&肛門(一緒かよ、おい)。その穴の出入口は腹側にあって、これを咽頭口というそうだ。 |
1997.5.9
さてさて、そろそろ、切ってみようか。しかしその前に準備が必要。「切っても切ってもプラナリア」に従って、まずは道具を一式揃えた。
皿(発砲スチロールのトレイが便利らしい)。飼育用の水。ろ紙(なければコーヒーのフィルターでも可だそう)。スポイト。カッターナイフ。虫めがね。ティッシュペーパー。
よしよしOK。で、その先。
皿に飼育用の水を注ぎ、それを冷凍庫へ。何故そんなことをせにゃならんのかというと、被験プラナリアをおとなしく寝かせるためである。彼らは冷やすと動けなくなるんだそう。手術台には氷が最適、というわけだ。
皿の水が氷ったら準備完了。あとはいよいよ…なのだが、ここで忘れちゃいけない留意事項をひとつ。プラナリアは1週間ほど絶食状態にしておくこと。エサを食べたばかりのプラナリアを切ると溶けて死んでしまうらしい。切り口から消化液が大量に出て自分の体も消化されちゃうんだって。う〜む、その様子も観察してみたいところ(残酷?)だけれど、なにせ初めてのオペだからね。マニュアル通りに行かせていただきます、はい。
1997.5.10
さあて。いよいよなのだ。
「切っても切ってもプラナリア」の「プラナリアのきり方」頁をしかとお手本にして、わくわくどきどきの切断実験に取り掛かった。
(1)冷凍庫から氷の張った皿を取り出し、上にろ紙を数枚敷く。ここでろ紙を敷く目的は2つ。プラナリアが凍ってしまうのを防ぐため、そして、切り終えた後のプラナリアを手間なくきれいに水に戻すため(ろ紙ごと水に運んでチャプチャプするだけ)だそうな。
(2)プラナリアをスポイトで吸い、ろ紙の上に載せる。
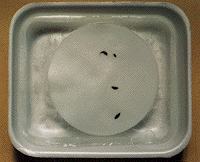 (右)冷却され動かなくなったプラナリア。麻酔にかかった患者のごとく、おとなしく切られるのを待つ。 |
(左)氷にろ紙を敷き、その上にプラナリアたちを載せる。実はここで早くもトラブル発生。スポイトでの吸引・運搬に失敗し、プラナリアが切れちゃった〜!(一番上のプラナリアがそれ。チッ!)
|
(3)虫めがねで見ながらカッターナイフで3つに切る。切断箇所は咽頭の前と後ろ。できるだけ切り口が傷まぬよう、スッと刃を手前に引く感じで切るといいらしい。体中から出る粘液が刃に付くと切れ味が鈍るので、切る毎にナイフをティッシュで拭く。

 切断直後。なんだか生ダコかナマコの切り身みたいだな〜、が率直な感想。 |
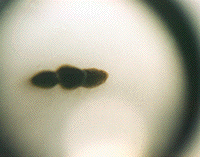
|
(4)水の中でろ紙をチャプチャプ。プラナリアたちを戻す。
