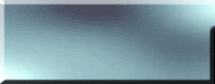 |
|
| �b�z�[���b�j�[�Y�b�����b�v���t�B�[���b�g�s�b�N �g�s�b�N |
�g�s�b�N
�M��@�������u���v
�@�@�`�v���̖ڂ��ꌾ�`
�����ҕی��͌��׃V�X�e���v
�@����20�N5��1���t���Łu�������N�ی��ҏv�Ȃ���̂�
���������B
�@���̕ی��͈ȑO�̕ی��ƊO�ς�������
�i�n�K�L�����菬���������傫���̂��̂�
2�܂�ɂ������̂ł������j
�g�тɂ͑S���s�����Ȃ��̂ł���B����
70�ɂȂ�������ł���B
�@���̌��Ë@�ւɍs���Ďx�������ɂ͈ȑO���玝���Ă���
�u�������N�ی���ی��ҏv�Ɠ�����2�������Ȃ���
�ی��Ƃ��ĔF�߂��Ȃ����ƂɂȂ����B
�������A1�����S���̊�����3���ňȑO�ƕς�肪�Ȃ��B
�ڋq�ł��鎄���Ë@�ւ̑�ς��ɑ���
�S���z��������Ă��Ȃ���ɂǂ��֍s���Ă��A�N���[����
�S���t���Ă���Ȃ��B���̃X�g���X�̒��܂邱�ƁB
�@���̏�A����2������̊Ԃɓs���a�@�A���ܖ�ǂ�
���Ȉ��3���ňꕔ���S���̊�����1���ƊԈႦ��
��ōēx�x�����s�����Ɨ̎����������Ďx�����ɍs��
�Ƃ������ʂȂ��Ƃ��N�������B
��Ë@�ւɑ�����̕s�O�ꂳ��
���炩�ŁA����ł͍�������Ҕ����N����̂�
���Ȃ������B
�@���������邱�Ƃɋ��X�Ƃ��Ă��q�l�̂��Ƃ�
�̂�ɂ���Ƃ������������ؕԂ����҂��Ă����Ƃ���
�Q�l�ɂȂ����B
�ǂ�����̍��̃g�b�v������ҍ����̖ڐ���
����������Ɛ錾�����̂͑f���������Ƃ���
�O�r���������ꂽ�B
�@����A���Ԋ�Ƃł͂���Ƃ�����̕���
�V�t�g���������Ă��Ă��邪�A����ł��܂�
�s�ˎ����₦���A�c�O�ł���B
���q�l��̂�ɂ���A�ڐ�͂�����������
���������悤�Ɍ����邪�A�Ō�͔j�]���邱�Ƃ�
�ڂɌ����Ă���̂��킩���Ă���̂ɁA�Ȃ��B
�@���q�l�͐_�l�ł��B�_�l�Ɋ��ł��������B
�_�l�̐�(�N���[��)�͕Ƃ����l������
�o�c�����݂̊�Ɣ��W�̂��߂̓N�w����
�������Ƃł��B
2008�N6��26��
��A�i���O�J�����ɂ��Ă̑̌��k�v
����A���j����ʐ�㐅�w�̍\���̎ʐ^��
�B���ė��Ă���ƈ˗�����܂����B
�Ƃ��낪�A�������ꂽ�f�W�^���J�������s����
�ʐ^���B��܂���B
����Ăċߏ��̃X�[�p�[�X�g�A�Ń����Y�t�t�B����
�u�ʂ��ł��v�����߂Ď��Ȃ��܂����B
���́A��N���I�����Ă���ƌÂ��A�i���O�J������
�\���o�Ă��܂����B�������S�~�ƈꏏ�Ɏ̂Ă܂�����
�Ō��37�N�O�ɔ�������Ԓl�i�̍����i�����ŏ\���~��j��
�J������1�c��܂����B
�H�t���ŃJ���������܂��Ƃ����Ŕ������̂�
�v���o���A�����֎����Ă����܂������^�_�ł����������
����܂���ł����B
����Ȃ�̑傫��������A�������҂�Ɏ̂Ă�ꂸ
�v�Ă��Ă���܂����Ƃ���A���I�X�ɍs�����ƂɂȂ�
���I�X�̐l�Ȃ�g���Ă���邩������Ȃ��Ǝv��
���n�̃K�C�h�Ɂu�g��Ȃ���Ύ̂ĂĂ�������v��
�����������ēn���܂����Ƃ���A�������߂Ă��܂�����
�{���Ƀ|�C�Ƃ��Ă��܂����B�i���I�X�ł͂܂�
�|�C�Ǝ̂Ă���j
���傤�ǁA�����ő吨�̌��n�l���ʐ^��
�B���Ă��܂������A�S�Ă��f�W�^���J�����ł����B
�ǂ̊ό��n�ł��t�B�����͈�ؔ����Ă��܂���B
���N�O�܂ł͎R�قǔ����Ă����̂ɁB
����Ȕ��W�r�㍑�ł��A����̗���̑�����
�������܂�Ă��邱�Ƃ�m������܂����B
�v���J�����}���͕ʂƂ��āA���̓��{�ł܂��A�i���O�J������
�����̂ł��傤���B�����������߂��X�[�p�[�ɂ�
�u�ʂ��ł��v��4�`50�u���Ă���܂�����
�N��������ł��傤���B�ǂȂ��������Ă��������B
���ōl���邾���łȂ��A�u���n�ŁE�������E�����I�v�Ɋς�
�Ƃ������Ƃ����߂čĊm�F���܂����B2007�N6��11�� 10:49:25
�����
�u���̘b�@���̂Q�v
�@�v���̑��͔|�Ǝ҂���V�C�^�P�̋ۏ�(20���������j����Ăɖ���Ĉ�ĂĂ���B�H�ɏ\���{�̎��n�����������A���̌�s�^�b�Əo�Ă��Ȃ��Ȃ����B
�@�����̃v���Ɂu����ł����܂����v�Ɛq�˂��Ƃ���u�܂��܂��o���v�ƌ����A����̂����������Ă�������B
�@���܂ɂ͊�1�����܂łǂ��Ղ萅�ɂ��邱��
�A���x�����߂����₵����A���x�����������邱��
�B����ł��o�Ȃ�������A�_�łЂ��ς�������
�ȂǁA�v������u�����Ǝh����^�����v�Ƃ����w���ł������B����ꂽ�ʂ����Ă݂�ƁA�܂��܂��~�ɂȂ��ď\���{�o�Ă����B
�@�H�Ɛ��i������Ă��鎄�����͂ǂ����Ă�[�œK����]�Ń��m�������悤�Ƃ��邪�A�������͂���ł�[�����炿]�ɂȂ��Ă��܂��A���s����Ƃ������Ƃ���������B
�@��Ƃ��g�D��[�C�L���m]�Ȃ̂ŁA�����炿�łȂ��A��Ɏh����^�������Ȃ���Έ炽�Ȃ��Ƃ����A������O�̂��Ƃ�g�������Č�����B2004�N12��10�� 12:27:04
�ȏ�
�u����肪��ł��v
�@�ŋ߁A�I�V���C�����Ƒ��̂����ɂ��Ă��܂��B
�@�����̖ʔ����͑傰���Ɍ����A�������̂Ƃ��낪���邩��ł��B���Ԃł͓ő����A�����łȂ����ƂQ�ґI���ł����݂Ă��܂��A���ۂ̓O���[�]�[��������A��ؓ�ł͂����܂���B���������ď����H�߂��������ŁA�����Ƃ��ȉ��������܂��B
�@�ڂɌ����Ȃ��^�ۂ̏W���̂Ȃ̂ɁA�w�ǂ��ۓƎ��̎P�ƕ��̂���1�����̂̂悤�Ȍ`�ɂȂ�̂��s�v�c�ł��B�Ƃɂ����s�v�c�Ȑ������ŋ������s���܂���B
�@���āA�H�c������s�Ŕ_�Ƃ�����Ă���m�l�̉Ƃ�q�˂܂�����.�B�L�����ɕ������A���Ă���܂����B�����̓u�i�̖̊��ɐ�����Ǝv���Ă������͂т����肵�܂����B�u����ŃR���̏\�N������N�Ő͉̂҂��܂����v�ƒm�l�̕فB�傫�ȏ������̍H�ꂪ�����āA�����ł��I��ɂ��ċۏ�������ł��Ėc��ȗʂ̕��������Y����Ă��܂����B
�@�ꕔ�ő�������Ă��āA20�Z���`�������炢�̋ۏ���1���y�Y�ɖ���ĉƂɒu���Ă������Ƃ���A�H�ɂȂ�Ƒ����ė��h�Ȑ��ő����\���{�̂�܂����B�~�Ɍ������Ă܂��܂��̂�Ă��܂��B���킢���Ă��킢���āA���̒ő��͔|�ɂ͖ڂ������܂���B�ő��̓z�_�ō͔|�������̂Ƃ���v���Ă������ɂƂ��āA���̒��̕ω��̑����ɋ������܂����B�u�z�_���ƂQ�`�R�N�|����̂N�ŏ�������̂ł���v�Ƃ̂��ƁB
�@�P�O���Q�O���ɓ����r�b�N�T�C�g�őS���_�ƍՂ��Â���܂����B�s���Ă݂��Ƃ���A���̈�p�ɑ��͔|�̃u�[�X������܂����B���������ƂɁA�����ł���ʉƒ�ŋۏ��ɂ����͔|�̐�`�����Ă��܂����B�}�C�^�P�E�G�����M�E�q���^�P�E�n�^�P�V���W�E�i���R�E�V�C�^�P�E���}�u�V�^�P�E�^���M�^�P�E�}���l���^�P�Ȃǂ̋ۏ��̍����ƍ͔|���@�������ꂽ�p���t���b�g�������Ă���܂���.�B
�@�_�ƂƂ����ǂ��Z�p�v�V�̑����ɁA�����͋Z�p�v�V�̎d���̃n�V�N���ɋ���Ǝ������Ă������ɂƂ��Ăт���������A���̒m��Ȃ��ɋ��J���𖡂킢�܂����B
�@������(�����܂߂�)�̎��ӂɂ́A�������W���n�ɂȂ��Ă���P�[�X�𑽂��������܂��B�ł��A���̌��ς̎���ɂ͏���������ς�����A,�H�v�����肷��ƂĂ��傫�ȃr�W�l�X�̎킪�]�����Ă��邱�Ƃ�m��܂����B2004�N11��27�� 11:36:27
�ȏ�
�u�R���d�r�Ԃ͋��ɂ̒���Q�Ԃ��v
�@�ŋ߁A�}�X�R�~���ŋ��ɂ̒���Q�ԂƂ��āA�R���d�r�Ԃ����グ���Ă��܂����A�{���ɒ���Q�ԂȂ̂ł��傤���B
�@�ԂƂ��Ă͐��f��R���Ƃ��āA�_���G�l���M�[�ɂ���āA����r�o���邾���ł���Ƃ����Ӗ��ł͒���Q�ł��傤���A�R���܂Ŋ܂߂��S�G�l���M�[�V�X�e���Ƃ��ẮA�����Q�V�X�e���ł͂Ȃ����Ƃ����A���ɂ͎v���Ȃ��̂ł��B
�@�����̐��f�����o���ɂ͈ȉ��̂Q���@�����Ȃ��͂��ł��B
�@�@�@�����琅�f�����o�����@
�@�@�A�L�@������(���ΔR��)������o�����@
�@�@�̕��@�́u�����琅�f���Ƃ��Ă܂����ɖ߂��v�Ƃ��������ŁA�����P�ɃG�l���M�[�̏z�������邾���ŁA�G�l���M�[���p�ɂ͂Ȃ炸�A���R������G�l���M�[���[���Ȃ���Ȃ炸�A�����G�l���M�[���X�̗ݐϕ������������ƂȂ��Ă��܂��܂��B
�@�A�L�@�������̕��q���琅�f�����o�����@�ł́A�������q�͑��ΓI�ɒY�f�������A���̐��f�𒊏o���ꂽ���q���ǂ��������邩�͂킩��܂��A�Ō�͓�_���Y�f�����������ƂɂȂ�܂��B
�@���f���o�V�X�e�����̂��͍̂����Q�V�X�e�����Ǝ��͎v���̂ł����A���̂��Ƃɂ��ă}�X�R�~��[�J�[���ł͈�،��y����Ă��܂����B
�@���̗�̂悤�ɁA���̒��ɂ͖ڐ�̗��v�̂��Ƃɂ����A�S�̂Ȃ����Ⴊ��ϑ����Ǝv���܂��B�����̏��r�W�l�X�̐��E�ł��A����Ȃ��Ƃɂ��܂���Ȃ��悤�ɒm���Ă����܂��傤�B
�@�ǂȂ����u�R���d�r�Ԃ͑S�n���V�X�e���I�ɂ��A���ɂ̒���Q�Ԃ���Ƃ������Ƃ����킩��̕��A�����ĉ������B2004�N7��27��
15:35:01
�ȏ�
�u�����̊X�A�����_��ȓ��Ԃɂāv
�@�V�����{�ɁA���E�̓������Ƃ����钆���_��ȃV�����O�����֍s�������łɂ��̂܂����n�̓��Ԃւ��s���܂����B�`�x�b�g�ɋ߂��X�ŁA���͒m��Ȃ������̂ł��������̈��W�ϒn�ŁA���̏W�׃V�X�e�����_�Ԍ��邱�Ƃ��ł��܂����B�C���R��ā`�S��Ăɂ����āA��ʂ̏��тł��B���{�̐ԏ��Ƃ͂����ԈႤ���ł��B
�@�܂��n�߂ɁA��������������Ă���Ƃɉƒ�K�₵�܂����B���t���ʂ��Ȃ��āA���������܂���ł���������̂���SLDK���炢�̉Ƃł����B���̒���ɂS�l�M�̔{�ȏ�͂���v���X�`�b�N�e�킪�T�`�U����A��������t�ɏ������O���[�h��������ē����Ă��āA��(�Ǝv����)�ɐZ���Ă����܂����B�����ȗe����Q�`�R����܂����B
�@��ɂȂ�ƁA�����l���l�Ɣw���Ă����ς��ɏ�������ꂽ������\���l�ƁA�r�j�[���܂ɉ����������ꂽ��������R�O�`�S�O�l���A���̒��S��T���H�̏��ŏ������L���A�O���[�h�������Ȃ���A�������~�̎�������Ă��܂����B�����l���吨�ŁA��ςȌ����ł����B
�@�H�����̎R����ʂ������̂Ƃł����A�O�𑖂��Ă��������h�N���[�U�[���e�я�ɐ��������Ă��܂����B�яꂩ��͎Ⴂ�j�̎q�������̓������r�j�[���܂������Ēǂ������Ă�����������Ă��܂����B
�@���Ȃ݂ɁA�s��ł͓��{�ł͔���Ȃ��O�ϕi���̈����������P��������80��(1000�~���j�`300��(��4000�~�j���炢�ł��������Ă��܂����B���������̏W�׃V�X�e���̐����ɂ͂т��������܂����B
�@���{���̔��V�X�e�������łȂ��A��ה_�Y���E������ƍH�Ɛ��i�E���Ë@�B�Ȃǂ��W�׃V�X�e�����č\�z����A�C�O�⍑���̎s��������Ɗg��ł����Ǝv���܂����B2004�N7��21�� 10:56:54
�ȏ�
�u���E�̓������A�����_��ȃV�����O�����ɂāv
�@7��7��(��)����10���Ԃقǐ��E�̓������Ƃ�����A�����_��ȃV�����O�����ɍs���Ă����B
�@��R�Ɉ͂܂ꂽ�~�n�ɍ��R�A�����炫����A����͂���͕ʓV�n�ł��������A���傤�ǁA�����̊w�Z�̉ċx�݊J�n�Əd�Ȃ�A�w����Ƒ��A�ꂪ�吨���Ă��āA�������Ƃ͂��悻���͋C���������ꂽ��ςȍ��G�U���������B�K�C�h�̘b�ɂ��ƁA2�N�O�܂ł͎����̋߂Ă��闷�s�Ђ̈��������l�̔䗦�͂T�O���ȉ��ł��������A���͂X�X���������l�ł����Ƃ̂��Ƃł���B����1�`2�N�̊Ԃɒ����l�̗��s�M�͔����I�ɑ����A���̂������傫�Ȏs��ɂȂ��Ă��Ă���Ƃ̂��Ƃł���B
�@�V�����O�����̒��̒��S���ɂ́A���{��100�~�V���b�v�Ɠ����A1���i13�`14�~�j�V���b�v������A���A(2���V���b�v�E3���V���b�v�E�E�E�Ƒ��킠��)�@�������i�Q��L���ȂǓ��{��100�~�V���b�v�Ƃقړ����ł������B���͌C����1��������2�`3���Ă݂����A�܂��g�������ł���B
�@���������ƂɁA�^�L�K���Ƃ������{�u�����h�̒ނ莅���u���Ă������B���{��100�~�V���b�v�͖w�ǂ��������ł���ƕ����Ă��邪�����͂܂��ɃO���[�o�����̈�[���Ƃ������Ƃ��킩�����B�G�ݓ��̐��E�ł��u���������������̂ł͂Ȃ��A���{�����Ďキ�͂Ȃ��̂��v�Ƃ������Ƃ�m�����B���s�M���O���[�o�������B
�@�����̉��ݕ������łȂ��A���n�ł��傫�ȕω����N���Ă����B�����̐l�����������A���{�̐����Ƃ͏��ĂȂ��A�Ȃ�Ă������B�e�X�̋��ݎ�݂�₢�������Ƃ������O���[�o�����ł���Ǝ��������B
�@���A���{�l��A��C�ɂȂ���A�������K�N�F���B 2004�N7��20�� 13:30:18
�ȏ�
�u���ʂ����Ŏd����]������Ɓv
�@����A�������x�Œ����Ԃɂ킽��A�吨�̌x�@�����E�����т̃m���}�B���̂��߂ɁA���U�̑{�����ނ��쐬���Ă����Ƃ������������o�����B���ʂ����Ŏd����]������ƁA�����Ȃ�͓̂�����O�ŁA���������܂�x�@�ł��A�����Ȃ��Ă��܂��B
�@�ŋ߁A��Ƃł��O���[�o�����̈�Ƃ��āA���܂ł̓��{�̔N������^�̞B���ȕ]���V�X�e������������A���ʂŎd����]������V�X�e�������s���Ă���B�������A���ʂ����Ŏd����]������ƁA��L�̌��x�̂悤�s���߂����N�邵�A�`�[�����[�N���j�Q�����P�[�X���N��B���ɁA���{�l�͌l��`��_��Љ�Ɋ���Ă��Ȃ����߁A���ʎ�`���������{�̊�Ƃ́A�K�������v�����悤�Ȑ��ʂ��������Ȃ��ŁA��킵�Ă���悤���B
�@�g�D�̏�ʎ҂͌��ʂɑ��ĐӔC�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A��������̂܂܉��ʎ҂ɉ����t����悢�Ƃ́A�P���ɂ͂����Ȃ��B���ʎ҂ɂ͎d���̂����Ɏw�����o���A�悢�d���������邱�ƂŁA���̎d���U��ɑ��ĕ]�����Ă����Ȃ����^���x�̂悤�ɂȂ�B
�@����œ����Ă���l�́A���ʂ̂��Ƃ͈�Ԃ悭�m���Ă���B�떂�������Ǝv��������ł��ł���B����������Ȃ����߂ɁA���d�ȊĎ��V�X�e��������Ă��Ԃ̖ڂ͂������邵�A��p�������ށB��������A�悢�d��������Ă��邩�ǂ���(���C�E�l�Ԑ������܂�)�@�ŕ]�����邵���Ȃ��B�Ƃ��낪�A����̂��Ƃ��킩��Ȃ���ʎ҂́A�A�����悢�d�����������w���ł��Ȃ��ꍇ�������B�I�O��Ȏw���ł͂悢���ʂ͐��܂�Ă��Ȃ����A����̐l�Ԃ���}�����B
�@���́A�d���̂����̕]���̎d�����A���Ԃł͑�ϓ�����ƂɂȂ��Ă���B���{�ȊO�̍��ł́A���������������i�Ƃ��āA�l�Ƃ̌_��ɂ���Č��ʂ̕]�������Ă��邪�A�W�c��`�Ō_���ȓ��{�ł́A�\�ʓI�ɊO���̐^�������Ă��A���̐S�܂œǂ݂���Ȃ���A���s����͖̂��炩�ł���B
�@���{�͂��̂ނ��������u�d���̂����̕]���v���A���܂���邽�߂̃m�[�n�E��z�����Ƃɒ��킵�A���E�ɓ��{�I�o�c���f���Ƃ��Ĕ��M���邱�Ƃ�S�|���čs�������Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�@���̂��т̎����ŁA����Ȋ��z���������B2004�N7��5��
12:51:33
�ȏ�
�u�j�[�Y�̖����z���J���������͔̂���Ȃ��v
�@�@���N���́@�S�̖����@�l������
�@����͂ǂȂ����̐���ł����A���̐���Ɠ����悤�Ȍo�������܂����B
�@����A�^�f�B�X�J�E���g�X�g�A�[�֎��v�ɍs�����Ƃ���A�ׂł��q�l�ƓX���̉�b���ʔ��������̂ŁA�������𗧂Ă܂����B
�@�ڋq���E���\���~�̒u���v���w�����āu������������������͖̂����́v�@�X���u����Ȃǂ͔@���ł��傤���v�@�q�u�����Ƃ����̖������ȁv�@�X���u����͂����������������A����Ȃ��Ƃ�����Ȃ��Ƃ��ł��鍂�@�\�i�ł��āA��A���������Ǝv���̂ł����v�@���̓X���́A�ꌩ���Ċw�Z�𑲋Ƃ��ĂQ�`�R�N�ځB�ǂ����Ă��A�E���\���~�̒u���v���߂ł鐶�����������Ƃ��������Ƃ͖��炩�B�������A���̋q�͔���Ȃ��ŋA��܂����B
�@���̎��A���鎄���R���T���e�B���O���������[�J�[�̊J����c�ŁA��Ҍ����̐H�i�����H���Ă����V�������������C�ɓ���Ȃ��Ɩ��̏C�����w�����Ă����̂��v���o�������܂����B
�@��1��J����c��ʉ߂��A�ŏI�J����c��GO�������肻���ȁA�N���Ƃ������i���j�[�Y�������Ȃ����V�A�����������c���������Ă���Ɂu��҂ɂ͔���Ȃ��v���Ƃ����͌���̌o�c�w�̊�{����A�m���Ȃ��ƂƂ������邪�@���E�E�E�B2004�N5��18��
9:48:58
�u���ׂ��͑P�v
�@����A�����̑��q���u�����A��s�֗a�������낵�ɍs���ē��ɂ�����B100���~�̔��N����ŗ�������������9�~����B����ňꕔ������������萔����315�~�����������B
�ׂ���Ȃ��ƌ����ĉ�X���炱��ȕςȌ`�ŋ��������グ��ꂽ�̂ł͂��܂�Ȃ���B���������Ɩׂ��āA��X�ɃT�[�r�X���サ�ė~�������v�ƁA��s�����ڂ����B
�@�����A���{��`�ł���Ƃ��u�ׂ��Ă�����Љ�ɊҌ��i�T�[�r�X����j����v�̂��P�ł���B
�@���A�\�����v�Ƃ��Ŕ_�ƁA��ÁA����A�X���A���H�A���Z�A���Г���������Љ����悤�Ƃ��Ă������ߋ��ɐ��������Љ��`�I�P���������o���Ȃ��Œ�R���Ă��鐨�͂��o���Ȃ����R����q�ׂ��ĂĂ���B�������A����ɑ����̃}�X�R�~��L���҂Ə̂���A��������Ă���̂͗����ɋꂵ�ށB
�@�u�ׂ��ĎЉ�ɍv������v���Ƃ�������X�ɉʂ����ꂽ�`���ł���ƁA���q�̂Ȃɂ��Ȃ���s����m�炳�ꂽ�B2004�N4��29��
10:00:09
�ȏ�
�u���߂ׂ̍����ƌ����v
�@���{���������Ȃ����̂��v���o���āA�ʂ肪����̂��傫�ڂ̃f�B�X�J�E���g��X�֊�����B���{���͑�ʂɒu���Ă��������A�S�Ă��L���ȏ������̏��i�ŁA�����ȑ����̎��i�n���j�͈�ؒu���ĂȂ������B�m���ɁA�������Ĕ�������Ȃ��āA�d����Ɏ�Ԃ��肩�����Č����̈����n���������̂́A�����Ƃ��Ă͎ד���������Ȃ����A�q�ł��鎄�ɂƂ��ẮA���Ƃ����͂̂Ȃ��X�Ɗ������B
�@�A���Ă��āA�V�����L����ƁAM�S�ݓX���u�S���L���w�ّ��v�Ƃ����`���V�������Ă����B����̓����V�hK�S�ݓX�̑S���w�ّ��͑吷���ł��̓�Ԑ������Ǝv���邪�A�L���ƕt���Ƃ��낪�C�ɂȂ����B
�@���s����������Ƃ́A���s�����d���̂����Ȃ��Ď�����Ȃ���Ζ��ɗ����A��������͐��������邽�߂���ςȓw�͂��������Ƃ�A���x�����������s�������������\������Ȃ����߂ɂ��܂艞�p�ł��Ȃ����A����Ă����܂��s���Ȃ����u����i��������)�͓���Ȏ��Ⴞ�����v�Ɠ����Ă��܂��̂������ł���B
�@K�f�p�[�g�̐����͔��N�E1�N�O����|���ٓ����o���Ă����ׂȉw�ى��ɓ��Q���A���������Ƃ��ĎQ��������Ƃ����͂Ȃ͂������̈������Ƃ�����āA���߂ēX�̖��͂����߂������ɉ߂��Ȃ��ƕ����B
�@��ƌo�c�͌����d�����K�{�ł��邪�A���ꂾ���ł̓_�����Ƃ���������_�Ԍ����Ė�����B2004�N1��29��
10:40:27
�ȏ�
�u������Ƃ����ӎ��̂��ꂪ���낵���v
�@�����̋������E�t�߂ɓV�Âɂ��鎟�j�̉ł̎��Ƃɏ�����āA��T�s���ė��܂����B
�@���̂��łɁA���˂��ˋ^��Ɏv���Ă����u�����l�͂Ȃ��������Ƀi�[�o�X�ɂȂ�̂��v�Ƃ����̂��m�肽���āA���낢��Ȑl�ɕ����Ă݂܂����B����Ɣނ�͋t�Ɂu�Ȃ������l������������_�ЂɁA���{�̑�����b���s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��v�Ǝ����Ԃ���܂����B������s���s���Ȃ������̒P���ŊȒP�Ȗ��ɁA���݂��������荇���Ȃ��āA�Ȃ��s���Ⴂ���������̂ł��傤���B
�@���������˂�����ŕ����Ă݂܂����B�u���̓V�Âɐ�v�҂̃��j�������g�͂���܂����v�Ɖł̕��e�ɕ������Ƃ���u�L��܂���B�����i����U�j�s���Ă݂܂��傤�v�Ƃ̕Ԏ��ŁA�����s���Ă݂܂����B�傫�Ȑ�������̕Ћ��ɁA�����P�O���͂��낤���Ƃ������h�ȃ��j�������g�ł����B��������͑吨�̐l�łɂ�����Ă��܂������A���j�������g�̎���͐l���q��l���܂���ł����B�u�����⌚���L�O���ɂ��̂�������ʂ̐l�����͎�����킹�ɗ��Ȃ��̂ł����v�u���܂���B����ȕ��K�͂���܂����v�Ƃ̂��ƁB�u�M���͐�c�̕�Q��ɂ͍s���Ȃ��̂ł����v�u�s���܂����v�Ƃ����Ԏ��ł����B�����A�������Ƃ�k���ɋ���30�Α�̒m�荇���̒j�ɕ����Ă݂܂������A�ނ��S���ł̐e�Ɠ������ł����B
�@�ł��A���{�̃}�X�R�~��{����͂���ȏ������͓��Ă��܂����B�^�u�[�Ƃ��ĐG�肽���Ȃ��̂ł��傤���B���摗��ł���ˁB�u����Ȃ̂����������ƂȂ��B�����Ă��������A����������v�ł����B
�@��Ƒ����̒����ł́A���N��1��ꑰ�Y�}���W�܂��Ĕh��ȕ�Q���s�Ȃ��ƕ����Ă������́A�傫�Ȍ�������Ă��܂����B����Ŏ��̋^��_�͕X�����܂������A�U��Ԃ��āA�r�W�l�X�̐��E�ł�����Ȃ��Ƃ����X�U������邱�ƂɋC���t���܂����B
�P�@����Ƒ�ȂƂ���ňӎ�������Ă���̂ɁA�������Ǝv������ł��܂��āA�N���[���ɂ���B
�Q�@���q�l�̃j�[�Y���킩���Ă���Ǝv���Ă��邱�Ƃ������ȏ��ň���Ă��āA�ڋq�����������Ȃ��B
�R�@�{���A���Ȃ�������Ȃ���ĉc�Ƃ�PR�������Ƃ��āA�������Ă��܂��B
�S�@�������Ղɍl���āA�摗��ɂ����傲���ɂ��Ă��܂��B
���Ȃǂł��B
�@����̗��s�͑�ώQ�l�ɂȂ�܂����B2004�N1��28��
10:59:58
�ȏ�
�u�G�͑S�Ė����ł���Ƃ������f���v
�@�����V�ÂɏZ��ł��鎟�j�̉ł̗��e����t�߁i�����̋������j�̏��҂�����A��T�s���ė��܂����B1�N���O�ɂ��s�����̂ł����A���̊Ԃ̕ς��悤�ɂ͂т����肵�܂����B
�@�V�Â̔ɉ؊X�͓����̋����V�h�ȏ�ɂ���ꂽ�X�������A���{�����܂߂����E�̃u�����h�i�����{���̋U���A�����ɓ��{��̂Ђ炪�Ȃ�J�^�J�i�������Ă��錻�n���̏��i�����ӂ�Ă��܂����B���ɂ́A���{�̎Ⴂ�����^�����g�̎ʐ^�t�̃��b�e�����\���Ă���~�l�����E�I�[�^�[������܂����B���Ă̓��{�l���������≢�Đl�̗e�p�������������Ǝv�����̂Ɠ������o�œ��{������f�������n�ł͌��Ă����悤�ł��B����ق����݂̒����ł͓��{�̕������s��Ɏ�����n�߂��Ƃ������Ƃ������t�����܂����B���̕ω��ɁA�����͋��G�Ǝv���Ɠ����ɁA���炵�����͎��ł�����Ɗ����܂����B
�@�����łӂƋC�������̂ł����A��Ƃ�l�ɂ��������Ƃ����Ă͂܂�̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł��B�Ƒ��̈�l��l�����̃��C�o���ł���Ɠ����ɋ��͎��ł�����܂��B��Ƃ����C�o���Ƃ͉ʊ��ɐ���Ă��܂����A���鎞�͋������������Ă��܂��B
�@�G�͑S�Ė����ł���Ƃ������f�����\�z����������◠��ȂǁA��Ƃ⎄�l�ŔY��ł������_�̂������͉������@�������Ă����Ƃ������Ƃ�m��܂����B���ɂƂ��Ă��炵�������ł����B 2004�N1��27�� 13:31:35
�u��Â̐��E�̊Ǘ��ɂ��āv
�@����A�a�@�Łu�h�{�w���v�Ə̂�����̂�������ꂽ�B
�@���́A�i�N�̍������Ǒ�Ƃ��č�N�P�����猌���l�Ǘ�����炳��Ă���̂������̈�Ƃ��Ẳh�{�w���ł���B
�@�c�����E�P�זE�����I���i�̎���1�̂��Ƃ����ƌ�����A�Ƃ��Ƃ���̂͂���Ȃ�ɂ��̂���2�ȏ�ɂȂ�Ɨ����Ƃ��o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�@�����l�Ǘ������ƌ����āA1��3�E���E�[�H�O�������l�̃f�[�^���̂�A�H����1��1,600���������ɂ���ƌ������ƂȂ̂ŁA���H�̐H�ׂ����e�Ɨʂ��X�ɃJ�����[�\���ɂ��Ă���B���̑��ɂ��A�^���ʂ��ߑO�E�ߌ�E��ɕ����������v�̕����Ńf�[�^�����A�̏d�����N���Ă������肵�Ă���B�����̃f�[�^��S�ĕ\�ɂ��A1�ڂł킩��悤�ɂȂ��Ă���B
�@�����l��80�`140mg/d���Ɏ��߂�Ƃ̂��Ƃł��͈̔͂Ȃ�ΐF�ɁA���I�[�o�[�Ȃ物�F��200mg/dl�ȏ�Ȃ�ԐF�ɓh�蕪���Ă���B�����āA�ΐF���͈͂��O�ꂽ��킩��͈͂ł��̌������L�����A�v�����Ώ�������ł����B�����܂ł��ƈ�҂̂ق����т����肵�Ă���ȂɃo�J���J�ɂ��K�v�͂Ȃ��A�͂���l���������炢�L���Ă��C�ɂ��Ȃ��ŁA�S�̗̂����}����Ηǂ��Ƃ̂��܂�ꂽ�B
�@�i���Ǘ����̎��Ƃ���A�O��l�͕s�Ǖi�ł��菭���ł����炷�ׂ��A���̌��������A������̂��Ǘ����Ǝv���Ă���̂ŁA��Ƃ̐��E�ƈ�Â̐��E�̊Ǘ��ɑ���l�����̈Ⴂ���܂��܂��ƌ����t����ꂽ�B���̒��x�̃f�[�^��͂ł������炷��A�܂��܂��Â������l�Ǘ����Ǝv���Ă���̂ɁA��Â̐��E�͂���Ȃ��e���ȊǗ��̍l�����ŗǂ��̂��낤���Ǝv�����B
�@���̂��ƂɁA���łɉ����Ǘ������Ɩ��߂��ꂽ��2�ȏ�̂��Ƃ͓����ɂ��Ȃ������̎��ɂƂ��Ă͖����Ȃ̂ŁA�ǂ��炩����ɂ��Ăق����ƈ˗������B�ł��A�悭�悭�l���Ă�����������Ǘ��͑�̒j�ɂƂ��ĂƂĂ��o����㕨�ł͂Ȃ��ƋC���t�����B�܂��A�����̃f�[�^�͂ǂ�����������̂��낤���B��p�������獡�̂Ƃ���v�����Ȃ��B�܂��āA���l�������Ȃǂ�����̂��낤���B
�@���̂��Ƃ���҂Ɍ����ƁA����Ȃ̊ȒP�ŁA�h�g�ɂ���ݖ��������ɂ���Ƃ��A���[�����̏`�����܂Ȃ��Ƃ�����Ηǂ��Ƃ̂��ƁA����Ȃ̊Ǘ��ƌ����̂��낤���B
�@�َ����̐��E���_�Ԍ����Ė���ĕ��ɂȂ����B2004�N1��15�� 15:11:20
�ȏ�
�u�������ƒ��ՎU�v
�@���U�ł̑̌��ł��B���q�ɂ������āuJR�����{���U�P��������P���~�ؕ��v���w�����A���˂��烌���^�J�[���g���ď\�a�c�Ε��ʂ̉������n�V�S���Ă��܂����B
�@�����̓����w�ł̌��i��JR�����{�̐V�����z�[���͒������A���C���V�����̏�q�͒��ՎU�ł����B�������̏�����u�͂�āE���܂��v�͑S�Ԏw��Ȃɂ�������炸�A���Ȃŏ���Ă���l�Œ������A�����Ⓦ�C���V������1���ɐ������x��������Ă��炸�A��ƌo�c�̈Ⴂ�̍����܂��܂��ƌ��������܂����B
�@�����Ɠ��Ōv�Z���Ă݂āA���ւɌ��ς����Ă�1�Ґ��Ő�l�ȏ�̍�������A3���Ԃ�30�Ґ��������Ƃ��āA���̊Ԃ̎������͂R���~�ȏ��ɂȂ�܂��B�^���Ƃ̓����j���O�R�X�g(�ϓ���j�͖w�Ǘ�ł�����S�����ׂۖ��ł��B
�@�����悤�Ȃ��ƂŁA���˂̖k�ɍ����ƕ��s�ɑ����Ă��鍂�����H�͒��ՎU�A�����͒��a�ł����B�����ƍ����������������āA�����𑖂��Ă���Ԃ��̂���A�����j���O�R�X�g�̓[���ɋ߂��̂ł���������������邾�낤���Ǝv���܂����B
�@�ȑO�Ɣ�ׂāA�ŋ߂͋ɒ[�ɃC�j�V�����R�X�g(�Œ��j�̔�d�������Ȃ�A�ȑO�Ƃ͈�������i�ݒ���@��C�x���g�ݒ肪�K�v�ɂȂ��Ă��Ă������Ƃ��A���N�̌��U�ɕ����܂����B2004�N1��5��
13:08:13
������l�̊Ǘ��őz�������Ɓv
�@���N�̏��߂ɋ��̕a�łR��������@�����B�މ@���Ɉ�҂��碌����l�̊Ǘ������������u�����A�������[�H���O�Ɍ����l�𑪒肵�ĂW�O�`�P�T�Omg/dl�Ɏ��߂邱�ƁB�H����1��1600Kcal�Ƃ��邱�ƁB���̃f�[�^�͒ʉ@���Ɉ�t�Ɍ����邱�Ɓv�ƌ���ꂽ�B
�@����ꂽ�H���̐ێ�ʂł́A�ێ�J�����[�ƌ����l�͂܂��������ւ������A�f�[�^����邽�тɢ����͑��߂��邩�ȁA����Ƃ����ȉ߂��邩�ȣ�������̗\���͂���o�����A��ɋ����Ă����Ԃł����B
�@�a�@�ł̐H�������̍u�`�ɂ́A�Ɠ���������킳�ꂽ�������A�Ɠ��������ɐ_�o���g���Ă��邪�A�p�ɂɌ����l�I�[�o�[�ɂȂ��Ă��܂��B����Ǝ��͢�o�J�����[�B�_������Ȃ�����Ƒ吺��グ�u���̐g�̂̂��Ƃ́A�����R���g���[������v�ƚV��������āA���̌�͎������R�ɂ���Ă���B���x�͉Ɠ�����M���_������Ȃ��̣�Ƃ���B�܂��Ǘ��ӔC���������l�Ԃ����܂������Ȃ��ƁA�ǂ₳���̂ł����B
�@��Ƃ̊Ǘ��ɂ��Ă��������Ƃ�������B��܂��ɂ͌����ƌ��ʂ̈��ʊW�͂킩���Ă��邪�A�����ȂƂ���ł͑����̌��������ݍ����Ă��āA�v�����ʂ�̌��ʂ��o�Ȃ��̂����ʂł����B����̑�P���̐l��������Ԃ悭�������Ă���̂�����A�Ǘ��͂��̐l�����ɔC���āA��i�͑及��������O���̖ڂŃA�h�o�C�X������̂��ǂ��Ƃ������ƁA�����̈Ϗ��ɂ��āA������O�̂��Ƃł͂��邪�A�g�������đ̌������B2003�N9��6�� 11:50:09
�u�����Ȃ�����҂������v
����̐g�͕̂s���ҁv
�@�w���Ɉ�a�����������̂ŁA��҂Ń����g�Q���ʐ^���B�������ʁA�e�������҂͑�ς��ƌ����ē��@������ꂽ�B�����͂܂��������o�Ǐ�͖����A���邳�E�ɂ݁E�M�E�P�EႂȂLj�ؖ����A��̂��Ƃ����������Ђ��ɂ��ꂽ���A�ǂ̃f�[�^�������l�ȊO�͐���Ŏ��Â̂��悤���Ȃ��A��҂͖����Ă��܂����B
�@�ۂ��E�C���X���^��(�J�r)�Ƃ����G�̂ǂꂩ�ɐg�̂��I�܂�Ă���̂ɁA�M���P���o�Ȃ��Ƃ������Ƃ����̐g�̂��s�������ēG�Ƃ������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B
�@�Ⴆ�ACRP�Ƃ������t�̌���(�̂̌����̂悤�Ȃ��́j�ł͑�ς悢�l�ɂȂ��Ă��āA�G�����Ȃ����瓬���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��킩��B���̐g�̂̑�{�c�ɂ͓G�����Ȃ��Ƃ�������`����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B
�@�����Ńn�^�Ƃ����������B���l�̌��N�����łȂ��A�������̎�������f�t���ɐN����Ă����Ƃ��S�Č��ʂ͑�ς��Ƃ������Ƃ͂킩���Ă��Ă��A�G�̏��S�R�킩�炸�A�����ʂɖ��͂Ȃ��A�G�������Ȃ��Ƃ������Ƃ͋��Ȃ��Ƃ������Ƃ��ƍ��o���N�����A�̂�т�\���ēG�Ƃ܂��������Ȃ��Ƃ����s���Ɋׂ��Ă���̂��Ƃ������Ƃ��킩�����B
�@�Ƃ肠�����A���̎厡����������Ȃ��ŗl�q�����Ă��̂܂܃����g�Q���̉e���Ȃ��Ȃ��Ă����Ζׂ����́A�����ƂЂǂ��Ȃ�ΓG�̐��̂��킩�邾�낤�A�Ƃ����҂��̐�p�����ߍ���ł���B���������ӂ̎�������f�t�����̊�Ƃ�����ȉ����@�����Ȃ��̂��낤���B2003�N5��31�� 12:50:07
�u������(����)�ƃX�L���V�b�v�v
�@������Ƃ������̕a�ň�Ғʂ������Ă��邪�A�厡��Ƃǂ����Ă����܂����킸��J���Ă���B �Ƃɂ��������Ƃ��M���W���Ȃ��B��҂Ɗ��҂̊W�͐M���W�����Ƃ����Ă���ԑ���Ǝ����͎v���Ă����̂����A�ǂ����Ă��C���ł��Ȃ��ł���B
�u���������A���U�Ƃ͉����
�@JR�����{�Ō��U���A��������Ԍ����g�����H�c���̓c��Ύ��ӂ̘I�V���C�ɐZ�����Ă����B
�u�������Ŏ������[�����v
�@����A�������֍s���@����B
�@�����R�[�̈ꌬ�h�̉��قɓ��h�����Ƃ���A���H�Ɏ������[�����o���B�h�̏����ɢ�����{�̗��قɂ��Ă͔[�����o��Ȃ�Ē���������Ƌ^��𓊂��������Ƃ��뢂����A�S�N���O�Ƀh�[���̈�ق̉��������ɓ������痈�Ă����E�l����w�[�����o���Ă���x�ƌ����Ă��o�������Ƃ���A��ϊF����Ɋ��āA���ł����q�l�̂W���͂��H�ׂɂȂ��Ă��܂���Ƃ����Ԏ����Ԃ��Ă����B�@�O���̗[�H�̎��ɗׂɍ������A���p�c��s�A�X�𒅂�����ƕ��̂��Z�����Ƙb����������o�g�n�͖k�C������k��֓�������n���Ɠ����{����L�͈͂ɗ����l�����������B�{�Ђ͓����������ł���B�h�͂����������݊֘A�̐l�����Ŗ��t�ł������B
�@�O���ɔ��܂����w�h�̖��h�̐e�����u�ŋ߁A���Ƃ̎d���������Ȃ��āA�y�n�̓y�H�������֍s�����܂��āA�����Ă����ł����v�ƌ����Ă����B�����ꏊ���Œ艻����Ȃ��Ť�����I�Ȃ��Ƃ͂悢���Ƃ��Ǝv������n���E��ɂ�炸�Z�p�ƋZ�\�������Ă��Ȃ��ƐE�ƑI���̏�ŃX�|�C��������Ƃ������Ƃ��A������O�̂��ƂȂ�����߂Ď��������B2002�N12��20�� 9:24:56
�u��s�ׂ͒��(���Ƃ��ׂ�)�v
�@����A����̓��������t�H�[�������B�����������̂ŋ�s���������邱�Ƃɂ����B
�@�����A�ؗp�؏��������i�ɂȂ����u�L�����S���Ɏ��M�Ŏ菑���ŏ����Ă��������v�Ƃ����B�u�Ȃɂ����B���̃p�\�R���S������Ɏ菑�����g�I�v�u�����A����̂��B���ł��v�u�����A���̋K���ɘa����ɂ����v
�@�P�O�N�O�Ɏ肽���́A������S���L�����Ă����u�����Ɏ���������Ă��������v�����������B
�@�T�N�O�Ɏ肽�����u���O�̋L���������M�ŏ����Ă��������v�u�ق��ق��B��������p�Łv�u���̖����Ɏ���������Ă��������v�u�o�J�����E�b�B���̓T�C�������̂������B���̏�n���R�Ƃ͉������b�B�����A���E�Ńn���R�g���Ă��鍑�Ȃ˂����v
�@��l���K���ɘa�̎���ł����͂�����������Ȃ��̂́A�킩��B���A��Ƃł́u���I�ɕς��˂v�ƌ����Ă��邭�����܂��A�O���n�̊�Ƃ������Ă͂قƂ�ǂ���ӂ��g���Ă���B
�@���ꂩ��IT�̎���ƌ�����̂����{�ł͂Ȃ�Ɩ��ʂȂ��Ƃ𑽂�����Ă��āA�����܂߂����܂�ɐg�߉߂��邩�炩�A����ɋC�����Ȃ��l���吨���邱�Ƃ��킩�����B
�@�܂��܂��A�������̐g�̉��ɖ��ʂ��S�}�������邱�Ƃ�m��A�������Ȃ����B2002�N12��16�� 17:20:01
�u�o�c�҂�A��Ђ̖��������v
�@����(11��25��)�̒����V��1�ʂɁu���c����̍������H�A���ݓ����P/�V�ȉ��v�Əo�Ă����B
�@�y�؊֘A�̐v�������ɋ߂Ă��鎄�̑��q�͂��̐V�������āu�����̃g�b�v�͐�s���̌��ʂ��������Ȃ�����A�N���̃{�[�i�X�͏o���Ȃ��Ƃ����Ă����B�������Ɏd�������������t���Ă����Ă��v�ƁB
�@�u���̂܂܂ł͉ߘJ������̂ł͂Ȃ����v�ƐS�z����قǐe�̎����猩�Ă����q�͂悭�����Ă���B�Z�u���C���u���ǂ��납�A���V���߂��ɏo�čs���Ė钆��12���߂��ɁA�����I�d�ŋA���Ă���B���ɐ���͓O��Ə̂��ĉƂɋA���Ă��Ȃ��B�y�j���قƂ�Ǐo�Ă���B���̂����A�c�Ƒ��50���ԑł���ŁA��̓T�[�r�X�c�ƂƂȂ�A�c��̕S���\���Ԃ͎c�Ƒオ�[���ł���B
�@�u���ꂩ��͍��Ɨ\�Z������A��Ђ̌o�c���W���n�ɂȂ�̂͂킩���Ă���̂ɁA�g�b�v�͉������Ȃ��B�����V�������Ƃ��N�����ł��Ȃ��A���ꂪ�����Ȃ猀�I�Ɏ��Ƃ��k������Ƃ��A��X�ɑ��ĉ��̃R�����g�������B�ނ�͎����̒�N�܂łɉ�Ђ��ׂ�Ȃ��Ⴂ���Ǝv���Ă���̂��낤�B���摗������A�Ⴏ������͂��܂�Ȃ���v�ƒQ���ĉ�Ђ֏o�čs�����B
�@�U��Ԃ��Ă݂�ƁA�����܂ߓ��{�̂قƂ�ǂ̌o�c�҂����q�̉�Ђ̃g�b�v�ƁA�قƂ�Ǔ����ł��邱�ƂɋC���t�����B���Ȃ��Ƃ��A���{�̌o�c�g�b�v�́u�Ⴂ�]�ƈ��ɖ��������v�K�v���������������B2002�N11��25�� 10:36:01
�u�{�c�@��Y�ƈ�[��W�v
�@����A�����̓����]�˔����ق֍s���āu�{�c�@��Y�ƈ�[��W�v�����Ă����B��ςȍ��݂悤�œW���������傱���ƌ���̂�����Ƃ������B���z���ꌾ�ł����A���̊w������͔@���ɕ��S���ʂŕn�����������Ƃ������ƂƁA�@���Ɋ�]�ɔR���Ă������Ƃ����������v���m�炳�ꂽ�B
�@�����A���]�ԂƂ����Ό��݂̂S�֎Ԉȏ�ɋM�d�i�ŁA����ɕ��Ɏ����R���^���N�̕t���Ă���A���ɖ{���������@�t�����]�Ԃɏ��߂ď�������́A�����ƍK�����͖Y����Ȃ��B�u�����y���B���������Ȃ��Ă��悢�̂��v�ƁB�܂��A�w�Z����e�[�v�N�������˗�����A��t�ɋ��锌���̏��֍s���āA�����ǂł����e�[�v���R�[�_�[�𑀍삵���������v���o�����B�u�����M�L�����Ȃ��Ă����B�m�[�g�����Ȃ��Ă������v�B
�@�Ƃ���ŁA������|���Ă݂�ƁA���������ׂĕ��Ɋւ��Č����A��ϕ֗��ɂȂ����悤�ȋC�͂��邪�A�{���I�ȕ����͉����ς���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�u�p�\�R���͕֗�������ǁA���̑��쐫�̈����͉����B�����ԁA����͐l�E���̋��킾���B���Ȃ��Ƃ����t�͐l�E���͂��˂��v�B�܂��܂��u���v�͕n�����B����u�S�v�̕��͓����Ɣ�ׂ悤���Ȃ����炢���C�������B�������u�ߋ��̉��l�ς͑S�ă_���B�ς��čs���ɂႠ�v�������̂��u�ߋ��͂悩�����B�ł��ς��čs���ɂႠ�v�Ƃ�������ɕς�����B���ꂪ���̌���ł���B�u�����������ɕς��悤�v�u���܂ł���ŗǂ������B�ς���̔��v�ƂȂ�B
�@���ɂ��u�ߋ��̂�����݂Ɏ�����ȁB���s�������ȁv�Ƃ����ꎺ������A�����Ƃ��Ă͂����v���Ă����Ȃ��悤�Ȏa�V�I�ȏ��i�⎸�s�������i�̓W������ψ�ۂɎc�����B���Ɏ��s���i�������Ƃ��ɂ́u�悭�W�����Ă��ꂽ�v�Ɨ܂���قNJ��������B
�@�u�o�c�҂̊F����A�������ɓI�ɂȂ�߂��Ă��܂��B���s����m�[�x���܂����܂�邻���ł��ˁv�B�ł��u���͐̂ƈ���āA�ق�̂�����Ƃ������s�ł������ɂȂ��ł���v�Ȃ�Č�����ƁA�ԓ��ɋ����邪�B2002�N11��24�� 11:47:51
���p�A���ۋ����͑�3�ʁv
�@����̐V���ɂ��ƁA��p�����ۋ����͂ő�3�ʂƂ������B����A���{�͍�N�̂Q�O���ʂ���14�ʂɂȂ����Ə����Ă������B
�@���́A���̐V�����\�̐����O�ɁA�d���ő�p�։F��̎��ȗ��A���炭�U��ōs���Ă����B��p�̕ς��悤�͎v���Ă����ȏ�ŁA���ɕ��������{�ƂقƂ�Ǖς�薳���A�т����肵���B����̍H��������Ă���������A�݂�ȃN���[�����[���ɂȂ��Ă��āA���w���͑S�Ėh�o���𒅂���ꂽ�B�O��Ɍ��w��������v�����g������H��ł́A���܂݂�̏��ō�Ƃ����Ă��āA�v�킸�N���[�����[���ɂ��Ă͂ǂ����ƃA�h�o�C�X�������̂��v���o���A�u���̊������������B
�@���w��������H��ł́A�ݔ�����͂Ől�Ԃ͂܂�ɂۂ�ۂ�Ƃ����������A�]�ƈ���400�����A150���̑呲�t�B���b�s���l��30���̃^�C�l�Ƃ����\���ł������B�܂��A�ʂ̍H��ł́A2�N�O�܂ł̓S���t�o�b�O�̐����H��ŁA���̂܂�2�N�O�܂ł͖a�эH�ꂾ�����Ƃ�����������ł���B�S���t�o�b�O�H����a�эH����݂Ȓ����֍s���Ă��܂����Ƃ��B��p�͍��A�ڂ̑O�ɑ咆��������A���{�ȏ�ɋ����i��ł��邱�Ƃ��܂̂�����Ɍ����Ă�������B�Ƃ��낪���������ʂ̐l�X�A�o�c�ҁA�]�ƈ��݂Ȃ����ό��C���悢�B����o�c�҂��u�������r�W�l�X�`�����X�v�ƌ������A����]�ƈ����u���̍H��ɗ���2�����ځA�������N�r�ɂȂ�����܂��ʂ̏��֍s���v�Ƃ������炩��Ƃ��Ă����B�ω��ɋ������A�ϋɓI�Ɏ��g�ގp���ɂ͊��S������ꂽ�B
�@����u���{�́v�Ƃ����ƁA1990�N�ȍ~���[���Ɓu�����������A���{�������v�Ɛl�̂����ɂ�����u���͎����������A�����Ɗ����Ă�����̓��A�D���Ƃ������邳�v�Ə��ɓI�ɂȂ��Ă��܂��Ă���B������{�ɗ�������̊O���l�����u���{�͕s�i�C�Ƃ������A����炵�����̂���������Ȃ��B�{���ɕs�i�C�Ȃ̂��v�Ǝ��₳��A�ԓ��ɋ������B�����Ă��̊O���l�̖ڂŒT���Ă݂�Ɓw�n���s�s�̒��S�X�̃V���b�^�[�X���A����X��z�e���̑�������̏��Ȃ��A�����������فE���p�َ��ӂ̃u���[�V�[�g�X�����x���グ���邪�A����ƂĂ��s�i�C�̂����łȂ����킯�łȂ��A�\���̕ω��ɕt���čs��������������������ł���B
�@����A��p�ɍs���Ă݂��u���{���s�i�C�Ȃ͓̂��{�l�̌��C�̖������̂��̂ł���A�����ƌ��ʂ��t�ł���v�Ƃ������Ƃ�m�����B���̑ŊJ��Ƃ����u���炪�ω����邱�Ƃɓw�͂��˂v�ƌ�����B2002�N11��17�� 10:56:55
�u�܂��܂��A�C�x���g��ԂȂ����́�������ɐ��L(��Q�e)�v
�@�������̂悤�ɁA�S���I�^�N�̑��q�ɗ��܂�Ė^�w���u�C�x���g��ԂȂ����́������v�̎w�茔���ɍs�����B�P�O�������ɊԂɍ����悤�ɂX�����ɓ������A�P�O���W���X�g�ɃL�[�C�����Ė�������A��͂薞�ȂƏo�Ĕ����Ȃ������B����̃C�x���g��Ԃ͂P�Q���Ґ��łP��Ȉȏ゠��̂����A��_���b�Ŗ��ȂɂȂ�Ƃ͐M�����Ȃ��B�����A���s�Ђ��O�ȂĔ�����߂Ă���Ƃ����l�����Ȃ��B���̏؋��ɁA�L�����Z���҂��𗊂�ł����ƁA���Ԑ����O�ɂقڊm���Ɂu�L�����Z�����o�܂����v�Ƃ����d�b������B
�@�Ƃ��낪�A���̃L�����Z���҂����˗�����̂͑�ςȂ��ƂŁA�قƂ�ǂ��f����B�����������������ɗ���ł��A��Ԃ��|�����Ėʓ|�������̂ŁA�����ȏ�͎t���ĖႦ�Ȃ��B�u���q���~�����ƌ����Ă���̂ɁA�����Ă���Ȃ��v�Ƃ����������o�c�҂͒m���Ă���̂��낤���B�m���Ă���Ƃ��āA�ǂ��w�����Ă���̂��B��P�����u�ʓ|���������甄��Ȃ��v�Ƃ����̂������҂������̂łȂ��A�o�c�̖���ł���B���������Ȃ��b���Ǝv���B
�@���̎���͗B�P�ɓS�������łȂ��A������Ǝ��Ɍ�����B�X�[�p�[�}�[�P�b�g�Łu�������i�͂ǂ��ɂ���܂����v�ƕ������猙�Ȋ�����Ă����ŃA�b�`�B���X�Ŗ{�������ĂȂ��Ƃ����̂Ţ���ĖႦ�܂�����Ƃ����ƌ��Ȋ������X������B�������œ��낤�Ƃ���ƐȂ��ꕔ�Ă���̂ɢ���Ȃł���ƌ����Ģ���҂��������v�Ƃ�����Ȃ��B�T�[�r�X�Ƃ����łȂ��A������A���Y���̐��E�ł��u����̂��ʓ|�����甄��Ȃ��v�Ƃ����Љ��`���̂悤�Ȃ��Ƃ��A�܂����̕s�i�C�ŕ�������Ȃ�����ɓ��{�ł��c���Ă���͎̂c�O�ł���B2002�N10��4�� 11:59:59
��ςĂ����ȕi���ۏv
�@1�N���O�ɁA������̕S�~�V���b�v�Ŗڊo�܂��^�C�v�̒u���v�����B�b���݉������傫���̂ƁA�o�b�e���[�̏オ�肪��������ǁA���Ԃ͐��m�œd�r�����̂Ƃ��ӊO�͎����������������Ƃ������B���ł��g���Ă��邪��ϖ��������Ă���B
�@�}�ɉƓ������s�p�ɖڊo�����v���~�����ƌ����o�����̂ŁA���̕S�~�V���b�v�ŏ��^�̖ڊo�܂����v�����B�d�r�����i�g��Ȃ������ȓd�r�ŁA�ʔ��̂��߂����100�~�o���Ĕ������B�ƂɋA���ĊJ���Ă݂���u���̎��v�͂P�����x�̕s�Ǖi�������Ă���̂ŁA�s����������甃�������֎����Ă���A��������v�ƈ������Ă����B�g���Ă݂��Ƃ���A���j���s����Ȃ̂ƒx�ꂪ�Ђǂ��̂ŁA���������֎��Q���Č������Ă�������B�����Ă���1�T�Ԍ�ł��������A�������̕i���������A������P�T�C�Y��̎��v�ɂȂ����B����͓d�r���P�S�g�p�Ŏ���ɂ���B���ւ������͂܂��g�p���Ă��Ȃ��̂ŕi���ɂ��Ă͂܂��킩��Ȃ��B
�@�s��Ɂu�P���s�Ǖi���o���i�`�p�k�P���j�v�Ƃ����i���ۏ�QC���Ƃ��ĉ������ւ�Ă����ȋC������B�����Ă���̂Ȃ�o�����Ȃǂ��Ďs��ɏo���Ȃ���悢�Ǝv�����A����100�~�ł͏o��������ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�ł��A�������o���ĕi���ۏ����Ă��邱�Ƃ͂悢���Ƃ��Ǝv���B
�@��Ԍ������āA��ʔ���g���āA100�~�̏��^�d�r���g���Ȃ��Ȃ��āA�����100�~�~�����炵���Ƃ������Ƃ́A���͊��q����̒��҂ɖ߂����悤���B�i���q����̒��҂��A���Ƃ������K��吨�̐l�v�ɒ��������ĒT�������Ƃ����̎�������j
�@�S�~�V���b�v�̕i���ۏƂ͉����B���ꂩ��ǂ�ǂ��������Ȃ邪�A�����������i�̕i���ۏƂ͉����Ƃ������Ƃ��l��������ꂽ�B2002�N9��20�� 12:43:31
�u����ς�i��(���n���Ɛ��j�v
�@���ς�炸���Ƃ̌o�c���������}�X�R�~�Ŗ��ɂȂ��Ă���B������n�������ʂɏオ���Ă��邪�A�X�[�p�[���̏����Ƃł͐��i�{�C�R�b�g���s���Ă���B�ł����n�����i�͈ꕔ�̔̔��X�ōŋ߁A�{�C�R�b�g�����ɓ����������B�������̐��i�͖����ɂ������ʂ�X���Ɍ�������݂̂ő傫�ȃ_���[�W�������Ă���B
�@���ЂƂ��ƊE�_���g�c1�ʂ̐H�i��Ђł��邪�A���̍��͉����Ƃ����ƁA�g���u���̌������i�����ł��邩�ǂ����Ƃ������Ƃł���B�����_���[�W�ł��i���g���u���͔@���Ƀ_���[�W���傫�����Ƃ������Ƃ�����͕�������ꂽ�B2002�N8��26�� 11:49:39
�u�T�b�J�[W�t�t�����X�v
�@�T�b�J�[�̃��[���h�J�b�v�ŁA�S�N�O�̑O��D���`�[���ł���t�����X���A�P�����ł����ɗ\�I�������Ă��܂����B�T�~�b�g�ɏ��l�߂�̂͑�ςȂ��Ƃł��邪�A�]��������̂ɉ��Ƒ������Ƃ��B
�@�s���ɂ��Ă͂��낢�날��Ǝv�����A�f�l�̎����Ƃ₩�������邱�Ƃł͂Ȃ��B�����A���Ԃł͂��������ꍇ�A�u遂�v�Ƃ�����S��Ƃ������t�ŕЕt���Ă��܂��P�[�X�������B��ƌo�c�ł����l�ł���B�����A���͂��̒��x�̔��Ȃ�s�����͂ł́u�����ęh�̏�����߂棒��x�̑�������ł��Ȃ��B
�@�X�|�[�c�`�[������Ƃ����������čs�����ƂɈӖ�������Ƃ���A���������̎����玟�̂��Ƃ��l���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ォ�玟�̒����ڎw���ɂ́A�K����x�͉�����~��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂�A���܂ň�ԑ�ɂ��Ă������̂��̂Ă�(�E��)�Ƃ������Ƃł����B����͎w���Ҏ��g��畏����Ă��܂����A�܂��Ď��͂���͖Ҕ�����B���܂ōō��ł��������̂��̂Ă�(�E��)�̂ł��邩��B
�@���t�̃t�����X�����Ď����g�A�̂Ă�i�E��)���Ƃ̑������������B2002�N6��12�� 11:33:20
�u�����X�^�C�����呍��v
�@���ǂ��̑@�ێY�ƂŁA�����z���𐔕S�����M�����傩��v�������悤�ȁA�������̊�Ƃ����{�ɑ��݂���Ƃ͒m��Ȃ������B
�@���̊��呍��̃j���[�X����A�����Ԃł��낢��c�_����Ă���A�o�c�Ƃ������̂ɂ��čēx�l���Ă݂��B�@��Ќo�c�Ƃ́H�B�A��Ђ͒N�̂��́H�B
�@�@��Ќo�c�̖ړI�͗��v���o�����Ƃł���ƈꉞ���Ԃł͌����Ă���B�ł��A���v�̏o���������ł����Ǝ��͍l���Ă���B�Ƃ�����Ɛ��Ԃł́A����̗�̂悤�ɗ��v��S�Ċ���ɊҌ�����������悢�Ƃ����A�A���O���T�N�\���I�ȒZ�����v�l����`�̍l�����Ɋׂ�₷���B�ł��A�q��ł͂���܂����A��X�����҂����Ђ������ɂ킽���Ď��n�ł���u���̐���v�ł����ė~�����̂ł���B�܂���Ђ͉i���̔��W�Ƒ�����ړI�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�A�C�G�X�E�m�[�̕Ԏ��ő�\�����A���O���T�N�\���l�̒P�זE�I�_���猾�����u��Ђ͊���̕��v�Ƃ����l�����͒P���ŕ�����Ղ��A�Ή������₷���B����A���{�l�̕��G�I�����܂��_������傾���ł͂Ȃ��āA�]�ƈ��⒲�B���ڋq�Ȃǂ̂�������̐l�̕��v�ƌ����l���������邪�A���ꂾ�Ɖ���������������Ȃ��Ȃ�A�����ɑΉ�����B
�@�����A���̇@�̒������v�Ҍ��Ƃ����l�������炷��ƁA�������̈�ԑf�������傾���ɖڂ��������o�c�͐��藧�̂��낤���B�����A�ł��邾������ɓ������Ȃ��o�c�����͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤���B2002�N6��12�� 10:45:37
�u�C�x���g��ԂȂ����́�������ɐ��v
�@�S���I�^�N�̑��q�ɗ��܂�āu�C�x���g��ԣ�̍��Ȏw�茔���ɍs�����B
�@�P�����O�̒��X������A�w�ɍs�����Ƃ���A���̃C�x���g��Ԃ̎w�茔�����Ƃ����q�������U�l�������B�ׂ�B�w�ɋ}���ōs���ƁA��q�͂܂����Ȃ������̂ŁA�����J�n���ԂP�O���W���X�g�ɃX�C�b�`�I�����Ė�������A���ȂƉ�ʂɕ\������w�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�O�D�O���b�̏����ɑ����̉w���͂U�O�O�Ȃقǂł́A���������Ȃ�ł���ƕ��R�Ƃ��Ă����B�ނ̘b�ł���C�x���g��ԁv�ł����܂ɂ͔���c��̂����邪�A�唼�����̂悤�ɏu���ɔ���Ă��܂������ł���B
�@��C�x���g��ԣ���P�Ґ����点��ɂ͑�ςȘJ�͂�������A���̔�p���v�Z������A���ȂɂȂ��Ă��̎Z��͂ǂ����킩��Ȃ����A���q�l�i���̏ꍇ�}�j�A������������Ȃ��j�Ɋ��ł��炦�邱�Ƃ͂��炵�������ł���B
�@��������Ɛl���A���܂Œʂ�̍l�����̂����P�ɑ�ʐ��Y��ʔ̔������ł́A���i�����Ɋ������܂�čŏI�I�ɂ͔���Ȃ��Ȃ�̂͂킩���Ă���B����������q���g�Ƃ��ă}�X�ł͂Ȃ��ăj�b�`�̃��[�U�[��ΏۂɁA��Ԍ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���߂ׂ̍������́i�m�b�j�ŏ��������Ƃ��l���Ă݂�K�v�������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����B2002�N5��23�� 12:27:47
�u��Ƃ̃f�B�X�N���[�W���[�v
�@���T�̓��j���V���ɉƓ��A���q�ƂR�l�ʼn��{��֍s�����Ƃ���A�ČR��n�̈�ʊJ��������A�����]�҂��PK���ȏ�����ւ̗�ŕ���ł����B�Ɠ��Ƒ��q���ȑO�A�ČR�̍��ԃL�����v�ɍs�������Ƃ�����A�����̂��Ƃ��v���o���āA����͂���͊y���������Ɖ����������Ă����B���E���̍��̒��ň�ʂ̐l�������̌R����n�����ĖႤ�Ƃ����������ɂ��邩�ǂ����m��Ȃ����A�č��̉��̐[���ɂ͊��S�����B
�@����A���{�̊�Ƃ̉����ɓ����Ă݂�ƁA��Ƃ̓��O�ɑ��Ă����u����Ɛ肵�Ă������v�Ƃ����l�܂��͑g�D�̐��݃j�[�Y�����ɂ��A����閧�Ƃ�����`�����ʼnB���Ă����P�[�X�����ɑ����B�����̌o�����玄�͂��q�l�ɂ����f�������邱�ƈӊO�́A�閧�ɂ��Ă���ƂɂƂ��ĉ��̃����b�g���Ȃ��Ǝv���Ă���B
�@���A���{�����{�͉�X�l�ɑ��A�Ԑڋ��Z���璼�ڋ��Z�ցA���~�����ȐӔC���Ƃ��Ĕ��ł�����Ə��サ�Ă���B���X�N�ɐӔC�������Ă����Ɩׂ��銔������Ƃ������Ƃ����A��X�f�l�ɂ͏��͂قƂ�NJF���ŁA�v���ɕ����Ƃ����Ă����Q�W���������邽�ߐM�p�ł��Ȃ��B�Ƃ���ƁA���������I�Ԋ�Ƃ͢�ׂ����ƣ�ł͂Ȃ��āu�D���Ȋ�ƣ�Ƃ������ƂɂȂ�B�u���͂��Ȃ����D���ł��B�����ƎЉ�̖��ɗ��d�����ǂ�ǂĂ��������B���̂��߂̊��������Ƃ��Ă����₩�ł������̂������g���Ă��������v�Ƃ������Ƃł����������ł��Ȃ��B���̂��߂ɂ́A���������قꍞ�ނ��߂̏�����ė~�����̂��B
�@��Ђ̏����̐헪�������������Ƃ���Ɓu����͊�Ɣ閧�ł��B���C�o���ɒm����ƍ���܂��v���ƌ����Ă����Ђ����{�ł͎��ɑ����B����ȉ�Ђ͂��ꂩ��͐�������c��Ȃ��Ǝv���B2002�N4��9�� 9:47:56
�u�傫������Ƃ����ĕ|���Ȃ��
�@���˂��ˁA��Ƃ̌o�c�̂���`�������Ă��ċC�ɂ��Ă������Ƃł��邪�A���Ƃł͑g�D���傫���Ȃ�߂��ď��̂Ȃ��肪�x���A�g�b�v�̌��f���x���Ƃ��ݏd�^�ɂȂ��Ă���B����ɂ��S�炸�A���{�̑���ƂƏ̂���Ƃ���ł́A�傫���Ȃ���ΐ����c��Ȃ��Ƃ���ɍ������J��Ԃ��Ă���B�Q�P���I�̌o�c��IT�i���j�푈�̎����ł���B����ɏ����Đ����c�邵���Ȃ��B����ɂ͑��f�����A���s�����g�y�^�̊�Ƃ��������c��Ȃ��B�����Q�O���I�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ���Ƃ̌o�c�҂͂킩���Ă���̂��낤���B
�@�������ƑΏƂ����Ƃł́A���Ƃ��P���Ă���Ƌ����Ă����B�������A�����Ȋ�Ƃ����邱�Ƃ��R�قǂ��鎞��ɂ��S�炸�A���ς�炸�̂Q�O���I�I�o�c�ɌŎ炵�Ă���B
�@�P��Ƃ��āA���āA�������ɐ����X�X�ł��������̒��̖������X�X�́A���X�[�p�[�ƃf�B�x���b�p�[�ɐZ�H����Ė����Ȃ��Ă��܂����B�x���͋x�ނ́A�z�B�͂��Ȃ��́A�p�b�N�̓���ڂ͑傫���́A����ł̓X�[�p�[�Ƃǂ����Ⴄ�̂��B���������炱���@�q�Ƀ��[�U�[�j�[�X�ɑΉ��ł����̂ɁA�����̓s�������ŏ������Ă͂��͂�Q�P���I�͐����c��Ȃ��B
�@���o�V���S���T��(��)P�R�R�u�o�ϋ�����ɖ���I�I�v�R�w�@��w���������̕ӂ̂Ƃ����G��Ă��邪�A���̒ʂ肾�Ǝv���B
�@�݂��ً�s�̂��܂͉����B�P���̃V�X�e���֘A�̐l�Ԃ͒m���Ă����͂����B���ꂪ���茠�̂���㕔�܂łȂ���Ȃ��������Ƃɂ��ߌ��ł���B
�@�o�c�D���̊�Ƃ͑g�D�͕K�R�I�ɑ傫���Ȃ��Ă��܂��B�Q�P���I���g�D��傫�����Ȃ��Ƃ������Ƃ��傫�Ȍo�c�ۑ��ɂȂ�̂ł͂Ȃ����B
2002�N4��8�� 9:53:50
������Ƃ������i�
�@����A�������Z����̒��Ԃ̌������ɏo�Ȃ��āA��Z�̉��t�̃X�s�[�`�����炵���Ċ��������Ƃ����ċA���Ă����B
�@�X�s�[�`��E�Ƃ̈ꕔ�Ƃ��Ă��鎄�ɂƂ��ẮA��ϋ�������������b�ł���B���͘b����������ŃX�s�[�`�ɂ͑�ϋ�J�����Ă���B�����A���q�l�̃j�[�Y�ɂł��邾�����킹��悤�ɂ��悤�ƍl���Ęb�������Ă����B�Ƃ��낪���q�l�͂��ꂾ���ł͖������Ă��Ȃ��悤�ł���B���������܂����������ȂƎv���X�s�[�`�͈ӊO�Ɣ������݂��A���s�X�s�[�`�Ǝv�����b�Ɂu�搶�B���̘b���悩�����棓��ƌ����ĂƂ܂ǂ��Ă���B���q�l�͎����̃j�[�Y�������́A�������l���Ă����Ȃ������b�������҂��Ă���̂��A�܂芴�������߂Ă���̂��A�Ƃ������ƂɋC���t�����B�u����͓���I�����ē������v�ł���B
�@�����A���{�̌o�ϒ���Ђǂ��Ƌ���Ă���B���{�i���E���܂߂�)�̌o�ς��}���ɐL�����������U��Ԃ�ƁA���̒��O�ɑ傫�ȃp���_�C���V�t�g�i��{�I���l�ς̌���)���N�����Ă���B���{�̐��̌o�ϐ���������q�l�͐_�l�ł���Ƃ����p���_�C���V�t�g�ɂ���ċN�������B���{�̌��݂̕NJ��Ŕj�ɂ͐V���ȃp���_�C���V�t�g���K�v�ł���B�������_�l�Ɋ������v�Ƃ������ƂɂȂ�B�j�[�Y�z�����A�v���Ă����Ȃ��������҈ȏ�̊����I�ȏ��i(�n�[�h���\�t�g��)����邱�Ƃ��Q�P���I�̉�X�o�c�҂̂˂炢�Ƃ������B�������ǁB2002�N2��10�� 9:51:52
��������Ƃ̃N�I���e�B�[�v
�@�u���{�̐l��������v�Ƃ������ƂŁA���{�Y�Ƃ̃G�[�X�����Ƃ��������ӂ֍H����ړ]�����Ă���B���ɓ��{�̔N���������̔N����20�{�Ƃ���ƁA����Ƃ���������20�{�̌o�ϓI�L�������ێ����悤�Ƃ���Ƃ�����A��������20�{���ȏ�Ɏd���̎������߂čs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ʂ�1��24���Ԃł����Ȃ�����A�����̍��͂����������Ƃ͂Ȃ��B���ł���B
�@�u�M���̍�����Ă���d���́�����20�{�ȏ�n�C�N�I���e�B�[�A�n�C�O���[�h�ł����v���������łȂ���A���̓��{�̎Y�ƂɁu����Ԃ��Ė���Ă���v�킯�ŁA��������̂܂ܑ���������ɒǂ��グ���邱�ƂɂȂ��B
�@��Ƃł́A�����̂̐l�X����g�b�v�Ɏ���܂ŁA�S�����������Ƃ̎������ߑ����邱�Ƃ�i�߂čs���Ȃ���A�����ɕ����Đ������т��Ȃ��B
�@�����̐l���ό��œ��{�ɗ��āu�킠�A���{�͕����������ĂȂ�Ă��炵�������v�ƌ���ꂽ��A��Ԃׂ����Ƃł��낤���B2002�N1��4�� 10:37:20
����[����40�~�̎���v
�@26��(��)�̓��o�V������o�ώ����c���f�t��2003�N�x�E�p�i�������㏸�ɓ]����)�Ƃ̌��ʂ����������j�v�Ƃ����L�����o�Ă����B���������Ă���20���I�㔼�͑�2�����E���̌�n���Ɨ��̉e���Œn���K�͂ł͕��s���������A�g�����h�Ƃ��ăC���t���̎���ł������B������40���N�O�A�����w������̂���̓��[����1�t40�~�̎����ł������B����500�~�ȏサ�Ă���B
�@20���I��������21���I�ɂ͂���ƁA���̏I���Ɠ����ɓ��A�W�A�A����A�W�A�A�����Ȃǂ̍��X�̐��Y�͂��オ��n�߁A�n���K�͂ł͕��]��̎����ɂȂ����B���ꂾ���o�ς��n���K�͂ɂȂ��Ă��܂��āA���͂⍑�ƍ��Ƃ̐푈�����邱�Ƃ��s�\�ƂȂ������݁A21���I�̑O���̓g�����h�Ƃ��ăf�t������ƂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B�o�ώ���ψ�����ƌ������ƁA40���N��͂܂��A���[�����P�t40�~�ɂȂ���������Ȃ��B�o�c��(�ƒ���܂�)�͂��̂��Ƃ͊o�債�Čo�c���Ȃ�����Ȃ�Ȃ��B
�@21���I�͒m�b�̎���ł���B���ꂩ��̒m�����Љ�ł͗D�G�Ȑl�ޕs���̎����ɂȂ�B���{�l���O���l���L�Ȑ����𑱂��Ă䂭�ɂ́A����i�w�Z�A��Ɠ��A���Ȍ[���j���x���̌��������Ȃ��B�����ȘJ���͂ōs����x���g�R���x�A�[���Y��������A���i�폭�ʐ��Y�ɑΉ��ł��A���x�Ȓm�\��K�v�Ƃ���Z�����Y��������{�̕����̌��_�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�R���x�A-���͊C�O�ֈϏ����A���́A�̔��́A�}�l�W�����g�͂Ȃǂ̑����͂����߂邽�߂̒m�b�����W����V�X�e����肪���{�̐����c��̗B��̓��ł���B
�@����ɂ��Ă��A���̓C���t�����f�t���������̈����Ǝv���̂����A�����̌o�ϊw�҂̊Ԃł͓����ł͂Ȃ��A�C���t�����f�t���̂ق�����舫���Ƃ����悤�ȕ���������̂͗����ł��Ȃ��B2001�N12��27�� 11:01:51
�u�g�b�v�B�I�}���A���V�����t�A�u�b�V���A����v
�@����̃A�t�K�j�X�^���ɊW�����u�g�b�v�̑Ή��̎d���v����ƌo�c���l�����ő�ώQ�l�ɂȂ����B
�@�A�t�K�j�X�^���i�^���o���j�ō��w���҃I�}���͏��Ă����Ȃ��ČR����Ɂu�����敐�������Đ킦�v�ƌ����č���łڂ��Ă��܂����B���V�A�ɏ������Ƃł��v�����̂����낤���B����A���V�����t�A�p�L�X�^���哝�͍̂����̑唼���u�A���`�č��v�ɂ�������炸�A���̎��Ƃ���č��̎�݂ɕt������ŁA�č�����̉����������o���Ă���B
�@�u�b�V���哝�̂͢�������犽�Ă̐��ɑ����āv�A�t�K�j�X�^�����s���A��Ȃ�����n���Ă���B���{�̏���͊O���⍑����������Ȃ���A���ς�炸�̖{���ƌ��O���g�������Ă���B���{�ɐ헪���݂�̂�疳���̂��B���O������s�C�������Ă���B
�@�����̑��ӂɏ]���̂��g�b�v�̖�ڂ��B���āA���{�ł���悫�ɂ͂��炦��I�o�c����̌o�c���f���Ƃ��đ��݂����B����u�ׂ��ׂ����ȁA����ɂ��Ă����v�I�o�c�����݂����B�ŋ߂̓��{�̑�^�|�Y�̗������ƁA���̓|�Y���R�͑O�҂������A��҂������̂悤�ȋC������B����̗̋�̂悤�ɍ����Ƃ�ׂ�����A��点����A�唎�ł�ł�����A�O���s�M���N�������肵�Ȃ����߂ɁA�g�b�v�͂ǂ�������悢�̂��낤���B
�@�u�ĕS�\�v�̌̎��ł͂Ȃ����A������]�ƈ��S���ɂ����ƕ����Ă��炢�A�ꂵ���Ƃ��g�b�v�ƍ�����]�ƈ��S������ۂƂȂ��Ēm�b���o�������Čo�c���Ă����V�X�e�����\�z�����̂��x�X�g�ł͂Ȃ����B2001�N11��22�� 10:56:27
����N�̕�\�Z�ɂ��āv
�@���N�̕�\�Z��č��̃e�����������������Ƃ����A�u�����Ƒ��z����v�Ƃ����o�ϊw�҂̈ӌ����������B�P�C���Y���ɂ��������������ƂɂȂ�̂�������Ȃ����A��������u�i�C��������̂���Ƃ����ۏɂ��ẮA�N�����Ƃ�����Ȃ��B�O�̂��̍��́u�C���t���ڕW�l��ł��q�ׂ����A�o�c�̐��E���猩��ƌo�ϊw�̂��Ƃ͂ǂ����悭�킩��Ȃ��B
�@�悭�悭�l���Ă݂�ƁA�o�c�̐��E����Ƃ̌o�c���P�����悤�Ƃ���Ƃ��ɂ́A���Y���̌��オ��ȖړI�ƂȂ��B���̂��߂ɂ͉��}��ƍP�v�I�ȑ�Ƃ����邪�A�o�c�w���҂̊Ⴉ�猩��Ɓu�o�ϊw�͉��}�������w���v�ł͂Ȃ����Ǝv����B�\�Z�����X�����������Ƃ���ō��Ƃ̖{�����ς��Ȃ���A�i�C�㏸�Ȃǂ͈�ߐ��ŏI����Ă��܂��B���{�̂P�X�X�O�N��͂܂��ɂ��̓N��ł����̂ł͂Ȃ����B
�@�o�c���P�Ɏ��g��ł����������́u�ł��Ȃ�������͂���ȁB�ǂ��������j�Q�v������菜���āA�V�������P���o���邩�l���悤�v�Ƃ����̂��S���ł������B���A���Ƃ̐��Y�����グ�悤�Ƃ������ɁA�����w�����闧��̊������c�m���������āA���̋@�\���v�Ɂu�o���Ȃ����R�v�������Ă���ق����A��\�Z�Ȃǂ���قǖ��ł͂Ȃ����B
�u�č��c��P�[�ɂ��āv
�@�A�����J�Ƃ������͂��������ł��ˁB����̃e�������̂悤�ȁA�������������v�^�̌���̏��ł��K���A��������l�ł�������l�������̂ł��ˁB
�@�����̊�ƂŃR���T���e�B���O�₢�낢��Ȓc�̓��̑g�D�ł��܂�Ă������̌o�������u�����v�Ō��܂������Ƃ͌�ɂȂ��Ă݂�ƁA�낭�Ȍ��ʂɂȂ�Ȃ��v�Ƃ������Ƃ���O�Ȃ�������̂ł��B
�@����ȌÂ��̂ł͂���܂����u�R�����ꗱ���O���������Ȃ��v�Ƃ����c��������c���̖����v�łȂ���܂������A���ꂩ�炢��������Ȃ��������E���O�A�C�����h�Ńp�[�ɂȂ������ƂȂǂ�������ł��ˁB
�@���āA���鏬���Ȍ������̕ҏW�ψ�������Ă����Ƃ��ɁA���鎖��Łu���̎G���̃l�[�~���O��ς��悤�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂����B�ҏW�ψ��S�����^���Ƃ������ƂŁA������^���ł������A�ȏ�̂悤�ȗ��R����}篁A����l���f�B�y�[�h�I���z�Ǝ�@�ŖҔ��ɉ��܂����B���ŏI���\��̉�c���A�钆�܂ł�����܂����B
�@�ł��A���̂Ƃ��̋c�_�̋c���^�����̌��������s�̃R���Z�v�g(�w�j)�Ƃ��āA�����ɖ𗧂��Ă��܂��B�ҏW��̂��Ƃł��߂�Ɓu�c���^�A�c���^�v�Ƃ����ăo�C�u���̂悤�Ɉ����Ă��܂��B
�@��Ɠ��̉�c�ł��A��ɖ����v�ɂ��Ă͂����܂���B��ŕK���A������邱�Ƃ��N���܂�����B
��C���t���ڕW�l�v
�@���݂̓��{�o�ς̕Ǐ�Ԃ�Ŕj���邽�߂Ɂu�C���t���ڕW�l�������v�Ƃ����o�ϊw�҂̈ӌ����������B���͌o�c�̘b�Ȃ玩�M�������Ă��邯��ǁA�o�ς̘b�ł���Ȓ�Ă��o�Ă���ƁA�o�ϊw�̂��Ƃ͉����킩���Ă��Ȃ��̂��Ǝ��M�����Ă��܂��Ă���B
�@�u�f�t���ڕW�l�����߂���Ƃ����̂Ȃ�킩��B�u���N�������͂���ʂ̃f�t�����ɁA���N�㔼���ɂ͂���ʂ̃f�t�����ɁA�ŏI�I�ɒ����Ƃ̕����i��������ʂ��v�Ƃ����̂Ȃ�킩��B�u��X�����͂��̂��߂ɉ������A�����o�傹�˂Ȃ�Ȃ����B�w���҂͉������Ȃ���Ȃ�Ȃ����v�Ƃ����i�H���������Ƃ��ł���B�f�t���X�p�C�������|���̂ł͂Ȃ��B�}���ȃf�t�����N����̂��|���̂ł����B�C���t�����f�t�����ǂ����Ƃł͂Ȃ����A�܂������[���Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��̂Ŋɂ₩�Ȍ`�ɂ��čs�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��̂��B�f�t���X���̎���ɂȂ��C���t���ڕW�ȂǂƂ����o�������Ȃ��ڕW���f����̂��B
�@�Ԏ��̑�����Ƃ������ڕW���f����̂Ƃ͑S�R�Ӗ����Ⴄ�Ƃ������Ƃ��o�ϊw�҂͂ǂ��l���Ă���̂��낤���B�i�Ԏ��͈��A�����͑P�j(�C���t�����f�t������)
�u�j���[���[�N�A���V���g���̑�S���v
�@�@���āA���{�̒�͂Ƃ��ꂽ�u�a�������đ����ƂȂ��v��u�o��Y�͑ł�����v�Ƃ������K���A���̂P�O�N�Ԃ̓��{�̌o�ϒ�Ō�������u�����Ǝ��Ȏ咣���v�Ƃ��u�O���[�o�����v�Ƃ��u�������Ƃ͂������Ƃ��v�Ƃ������l�ςɕς���Ă��܂����B�ł��u����������v�Ƃ������l�ς��A����̂��̎S���ŃO���[�o���Ȍo�c���f���ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��ؖ�����Ă��܂��܂����B
����ɥ���̉ԉΑ������́v
�@���Ɍ����Ύs�̉ԉΑ��ő����̊ϋq���������ꂽ���ƂɁA�ނ�ł������Ƃ���������\�������܂��B
�@�����A���ς�炸�̃}�X�R�~�Ɏ���̌Â��������܂����B�m���ɁA���̋@�ւ̑Ή��̂܂����͂������ł��傤���A�S�Ă�������ɂ����Ă����̂͂����ɂ����{�I�ł͂Ȃ��ł��傤���B�č��ł́A�}�X�R�~�́u�����ƁA�l��l��l�������̈��S�ɑ��Đg�����w�͂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����ɂɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@���A���{�͍����ɗa���������Ȃ��ŁA�����Ə��サ�Ă��܂��B����䂪�ƂM�p���ɂ̊O���������܂����B�ޞH���u���܂ł͏�i����A�a����������ė����ƌ���ꑱ���Ă��܂������A���x�͓����M����Ƃ����܂����B���܂łR�O�N�Ԃ��l�I�ɂ��t�����������Ă������������q�l�ɁA���{�̕ۏł��Ȃ����i�������߂��邱�Ƃ́A�茘���ŐM�p�Ă������Z�@�ւ̈���Ƃ��āA�ƂĂ��ł��Ȃ��v�Ƃ��ڂ��Ă��܂����B
�@����̍\�����v�́u������l��l�����X�N���A��������ɗ�����v�Ƃ������Ƃł��B�\�����v�Ɏ^�����Ă���}�X�R�~������ȌÂ����������Ă͍���܂��B�}�X�R�~�����܂��\�����v�����ė~�����̂ł����A���ɗ���ȁA�����ɗ���ȁA�x���̐��ɗ���ȁA�}�X�R�~�ɗ�����Ƃ������Ƃł��B
�@������������l��l�����X�N���A�m�b���o���A�悭�V�сA�悭�w�сA���������ē����A����Ȍo�ϓI�NJ��ȂNJȒP�ɐ��������̂ł��B�u�E(������)����������ǂ����悤�B�R�����l�M���i������)����������ǂ����悤�v�Ɗ��������������Ƃɂ��т��Ă��邩��A���͉����܂ł����Ă��������Ȃ��̂ł��B
��ƌo�c���܂����������ł��B
�u�x�R���������̃R�[�����j�������
�@����A�x�R���̏������Ńp�L�X�^���l�̌o�c���钆�ÎԒu����ɁA�R�[��������ē����̂Ă��Ă����Ƃ������Ƃ���A�{�����p�L�X�^���l��������⌧���Ƀf���ōR�c������Ƃ����������������B
�@���̐V���L���̎ʐ^�����āA�f�����d�|�����p�L�X�^���l�������炪�z�����Ă������������̂ɂт����肵���B���܂��ܐ��N�O�ɐV�����V�Îs�Ńp�L�X�^���l�Ɠ��{�l�̌������ɏo���킵�āA���̂Ƃ��̃p�L�X�^���l�̑����ɋ������̂��v���o���A�n���s�s�ł������炪�v���Ă���ȏ�ɊO���l�������Ă���Ƃ���������m�����B
�@������⌧���̐E���͎v���Ă��݂Ȃ������ٕ����Ƃ̖��C�ɂ�����т����肵�A�Ή��ɋꗶ���ꂽ���ƂƎv����B��X���{�l�̖w�ǂ̓R�[����(�̖{)�͕��ł���A�p�L�X�^���l�ɂƂ��Ă͐S�ł���B���̕����M���b�v�Ɏn�߂ďo���킵���Ƃ��ɂǂ����Ă悢���킩��Ȃ��̂����ʂł���B���ꂩ����{�ł͂���Ȃ��Ƃ������ƕp������ł��낤�B�������C������邽�߂ɂ�����ƌ����āA�O���l����{����ǂ��o�����Ƃ͂ł��Ȃ��B���C���������Ă����̓s�x���Ƃ��������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ȃɂ���A���{�l�̎g�������ÎԂ��p�L�X�^���l�����V�A�l�ɔ����Ă���Ă���Ƃ�������Ȃ̂�����B
�@����Ɠ������A��Ƃł��O���l�����ȏ�ɑ吨����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ԃ��A�O���[�o�����Ƃ����Ӗ��Ŕ����Ēʂ�Ȃ��B���̎��A�z�������Ȃ��悤�ȕ������C�ɕp�ɂɏo���킷�悤�ɂȂ�ł��낤�B���̂���`��������Ђł��A�@���b�J�̕������킩��悤�ɍH��̏��̎傾�����Ƃ���ɖ���t���Ă���A�A�H���ł̋����̓n�����̋V�����s�������̂ɂ��Ă���i�ؓ�������ŏ������������ȂH���邩)�A�B�i����͒����l�̘b�����j�H��̐H���̏L���ɑς����Ȃ��̂ŕʂ̕����ŐH�����ł���悤�ɂ��Ă���(���{�l���炷��Β����̐H���̂ق������{���L���������Ǝv���̂���)�ȂǁA�����͂ǂ�����\�l�S���̗v���ŁA�S���҂��炷���ΐM�����Ȃ��悤�Ȗ��ɂт����肵�Ă����B
�@�����̃M���b�v�͌���������A�����W�������肷�������x�͗\���ł��邪�A����ł��ł��Ȃ����̂̕��������̂ł͂Ȃ����B�����ł���Ȃ�A�M���b�v�������������ɂȂ����A���邢�����������Ƃ��ɓ������łȂ��A�ϋɓI�ɑΉ�����̂���Ԗ������̋ߓ��ł͂Ȃ����B���ꂪ�܂����{(�l)�ɂƂ��ăO���[�o����m��Ƃ����Ӗ��ł���ԗL���ł͂Ȃ����Ǝv���B
�u���{�̌l���叧����
�@�������������x�����āA���Z�@�ւ��ۗL���Ă��������u��������@�\�v������Đ��{�������Ă�낤�A�Ƃ����b���o�Ă����B��������Ƃ��Ă���ȃi���Z���X�Șb�͂Ȃ����A����ɂ��Ă͂����ł͐G��Ȃ��B
�@���������{�̕s�i�C�����Ƃ����悤�Ƃ�����̈�Ƃ��āu�l���叧�����Ƃ����̂��o�Ă����B�Ő���x��ς��Čl�������₷�����悤�Ƃ����̂��˂炢�ł���B���O���Ɣ�ׂē��{�̌l�̊������L���ɒ[�ɏ��Ȃ��B�l�̌����͖w�ǗX�֒����ɉ���Ă��܂��A���Ƃ����Ȃǂ̒��ړ����ɉ���Ă��Ȃ��B������A�����Ɗ����Ƃ������Ƃ炵���B���{�͍����ɔ��ł�����Ə��サ�Ă���̂��B�ł��A�X�֒������s���ʗa���ł��y�C�I�t�������č��܂ł̂悤�������̓��X�N��Ȃ��ō��Ɉ��S�����҂���̂͂������f���A�Ƃ̂��Ƃ炵���B�ł��A����ȌƑ��Ȏ�i�ō��̊����������ł���Ǝv���Ă���̂��B�����āA����Ȃ��e���Ȋ������x�ł������̎��オ�������̂��B���������������{������s��Ƃ��������o���A���̖������悤�ɂ��邱�Ƃ��{���ł���B�����Ζׂ���Ƃ������Ƃ��킩��A�����͔����̂��B
�@��ƂŖ������̂���`�������Ă���ƁA���낢��A�C�f�B�A���o�Ă��āA���͂Ȃ�قǂƎv���̂����A�����g�ݍ��킹��ƑO�L�̊�����̂悤�ȕ��������Ή������ׂ���I�ȃ{�^���̂����Ⴂ�������邱�Ƃ�����B����������ɂ͂Q�̕��@������B
�@��́A����I���@�ŁA�Q�P���I�̖�蔭���̗v���͕��G�����I�ɂȂ�A���̉��͕����ɂȂ�B�]���āA��̉��ɋÂ�ł܂�̂ł͂Ȃ��A�����̉����������镡��I�Ȍ������K�v�ɂȂ��Ă���B
�@��ڂ́A�]���̃I�[�\�h�b�N�X�Ȃ����𒉎��Ɏ��s���邱���ł���B���������Ăăf�[�^�Ō�����Ƃ��邱�Ƃ�����B��Ƃł͂�������Ɖ�������s���A�������ɂ��Č������Ȃ����Ƃ������B�f�[�^��͂͏d�v�ł���B���{�̈�ʍ���������Ȃ��̂́u�o�u�������Ɋ��Ɏ���o�������āA�o�o�����܂���đ呹��������ꂽ�l�������ɑ����������v�Ƃ����f�[�^������Έ�ڗđR�ł���B�܂��A���{�Ō��������̑唼�͘V�l�ł���B�����u���̔N�ɂȂ��āA�ア������Ȃ��̂ɋ��ׂ����Ă݂Ă��A����Ŏ����čs����킯�łȂ��A�����葹���������Ȃ��v�ƌ����̂������ł���B�u�킩��Ȃ������畷���B�������^�Ɏ�ȁB�{���͉����v�u�ŋ�������邩�犔��Ȃ��A�Ƃ͉������������̂���m�ꣁu�ŋ��������̂����₾����A���������Ȃ��v�Ȃ�Ă����l�����邾�낤���B
�u�}�c�_�v�Ɓu�}�C�J���v
�@�u���߂��v������ĉ߂��āA���Y���ǂ����܂ōēx�������~�ɂ��������ł��邪�A���͂܂��H�ׂĂ��Ȃ��B�u�˂ƕĂł͐H��������Ȃ��Ĕ��������̂��Ȃ��v�Ƃ悭����闝�R���킩��Ȃ��ł���B
�@�����ԉ�Ђ́u�}�c�_��ƃX�[�p�[�̢�}�C�J���v����]�ސE�������Ƃ���A�킸���P���Ƃ������ŖڕW��B�������Ƃ����j���[�X���āA�ʂ̈Ӗ��ł悭���ꂽ���R�Ɏ��͋����Ă���B�I�g�ٗp���ɑ���ӎ�����҂����ł͂Ȃ������Ј��ɂ������ɗ��ċ}���ɕ��Ă��Ă��邱�Ƃ��킩��B�����̌o�c��̕ω��̌������Ƀg�b�v�͂��čs���̂���ςł���B
�@��]�ސE�҂���ƁA�D�G�Ȑl�Ԃ��玫�߂čs���B�c�����l�ԂŌ������Ă����ƂȂ�A�]���ʂ�̂����ő����Ă����̂ł́A�l�ޒቺ�Ƃ����_�ł��܂��s���Ȃ��Ȃ�̂��ʗ�ł���B�O������D�G�Ȑl�ނ������������Ă��邱�Ƃ��ł��Ȃ��ƂȂ�A�����̐l�Ԃ�D�G�Ȑl�ނɈ�ďグ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂�A���܂ňȏ�ɋ���Ɋ�Ƃ̃g�b�v�͗͂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��낪�A����͂����ɂ͌��ʂ��o�Ă��Ȃ����A����Ȃ�ɔ�p��������B��]�ސE�҂���Ƃ�����ԂɂȂ����Ƃ��̊�Ƃ̌o�c��Ԃ͎��ԓI�ɂ���ȗI���Ȃ��Ƃ͌����Ă����Ȃ����A����ɔ�p��������]�T�������B���̍��܂ł̌o������A�w�ǂ̌o�c�҂͂킩���Ă��Ȃ��炻���̂Ƃ���ׂɉ߂����Čo�c���W���n�ɂ��Ă��܂����������������B��Ƃ͐l�Ȃ��B�l�ޖ������Čo�c�����B
�@��������̌o�������u�S�Ă̐l�Ԃ͐��ݓI�ɂ͗D�G�Ȃ��̂������Ă���v�Ƃ������Ƃ�m�����B�u���̐l�͎g�����ɂȂ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����l��������ˑR�A�D�G�Ȑl�ނɕϐg�����P�[�X�����x�����ڂɂ������Ă���B�]�ƈ���D�G�Ȑl�ނɈ�ďグ���Ȃ��̂͌o�c�̐ӔC�ł���B����Ƃ����Ƃ����AOff-JT�i�W������)���v���o�����AO-JT(�E��̎d�������Ȃ���o���鋳��)�̕�������(����)�A��p(����)�A����(���ɗ���)�Ƃ����ϓ_������x�^�[���Ǝv���BO-JT����������߂����B���ꂩ��͏I�g�ٗp�������āA�l�ނ̈ړ����������Ȃ�ł��낤���A������ƌ������u�l�ދ����a���ɂ����o�c�͐��藧���Ȃ��v�Ƌ��������Ă���B
�u�̃S���t�
�@�S���t�͎��͂��Ȃ����A�x���Ɏ��S���t�����͎̂��l�Ƃ��ē��R�Ȃ��Ƃ��Ǝv���B�܂��A�}�X�R�~�ł͂Ƃ₩�������Ă��邪����̎����̃��x���ł́A�A�����Ƃ�Ȃ���S���t�𑱂������Ƃɑ��Ă��A�ʂɔ����悤�Ȃ��Ƃł͂Ȃ������Ǝv���Ă���B���@�ɋ}���Ŏ���ĕԂ��Ă����Őw���w����������̎��̂̏��������D�]�����Ƃ͍l�����Ȃ����A������b������Ƃ����ĂQ4���Ԏd�������Ȃ�������Ȃ��킯�ł��Ȃ����낤�B�ߔN���@�킪���B���ăS���t�����Ȃ�����������鎞��ɂȂ����B��Q��A��R��𗘗p���Ă��ꂩ��s�����N�����Ă��A����̏ꍇ�͕ʂɖ��͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�����o�����̂������ŁA�ƂƂ̘A���ɂ͂���Ȃ�ɋC���g���Ă���B���S�ȃG�}�[�W�F���V�[�ł���A���f�͊ȒP�ł��邪�A�����ȃP�[�X�ł́A���u�������������āv�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@����͂����ł͂��邪�A����̏ꍇ�͐ɂ����`�����X���킵���悤�ȋC������B�f�����s�����N�����A�w���w�����s���A�����͐l�C���ɂȂ����̂ł͂Ȃ����B�����������l�C���Ƃ����ϓ_����A�������������ȃP�[�X�ł͍s����f�����N�������ق����ǂ��Ɣ��Ȃ����B
�@��ƃg�b�v�̕��A���������������P�[�X�ɑ��X�o���킵�Ă�����Ǝv���܂����A���ӌ��������������������B
�u�ǂ��f�t���E�����f�t���@�ǂ����������E�������������v
�@�f�t���╨��������ǂ��Ƃ������Ƃ��A���鉿�l�ςŌ��ߕt���Ă��܂����Ƃɂ͂���������R�����邪�A���̂��l����Ƃ��̐����Ɏg������A�\�������肷��Ƃ��ɂ͕֗��ł���B���̂悤�ȗ��R���炱�̌��t���g�킹�ĖႤ�B
�@�R���T���^���g�Ƃ��ĉߋ���\���N�ԁA���ɂ��̂P0�N�Ԃ͌����ጸ�̎w���𑽂��̊�Ƃł���Ă����B�������G�Ђ��i��(���ۂ͂܂��r�V���r�V���̔G��G�Ђł͂��邪)�悤�Ȏv���ŕK���ɓw�͂����Ă����B���ꂪ�����ɔ��f���Ă����Ō����ǂ����������A�܂�ǂ��f�t���ɋ��͂��Ă����ς�ł���B���{��`�ɂ����Ắu�����ጸ�͐�ΓI�ȑP�v�ł���ƍl���Ă���Ă����B�Ƃ��낪�����ɗ��Đ��Ԃł́u������������Â���f�t���X�p�C�����͈��ł���B���{�����̓C���t���ڕW�������v�ȂǂƂ����y���o�Ă����B
�@���ꂩ��͍D�ނƍD�܂���ƂɊւ炸�A�O���[�o���Љ�̎���ł���B�o�ςŃO���[�o���ɐ��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ɂȂ����B�܂袍��̣���碃I�����s�b�N��ɔۉ������o�ꂷ��悤�Ȃ��̂ŁA�����G�������T�Ƌ���B
�@���{�͊O���Ɣ�ׂĕ����������Ƃ����Ă���B�܂��A�l��������̂ŊO�����i�Ƌ����ł��Ȃ��Ƃ����Ă���B���Y���_�������l��������߂ĊC�O�Ɉڂ��Ă���B�ł��u���j�N���v�⢃}�N�h�i���h�������I�Ȓቿ�i�ő傫�ȗ��v���o���Ă����B����́u�悢���������v�ł��邪�A���̃R���y�`�^�[�͐����c��������ĉ��i�j��ɒǏ]���Ă���B���ꂪ�ǂ����������Ȃ̂��A�������������Ȃ̂��͂킩��Ȃ��B���̓��A���čs���Ȃ��Ȃ�����Ƃ͓d�b����������ĂȂ��Ȃ邾�낤�B����͈������������ł��邪�A���{��`�̝|�ő�������ł����Ȃ��ƌ�̂��̂��L�т��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B���̍�����Ƃ݂̂������c��ɉh�ł��邽�߂��A���{������܂ł̃C���t���̎��ŕt�����C��b�𑁂��킬���Ƃ����߂ɂ��A�f�t���X�p�C�����劽�}�ł���B����܂Ő��\�N�Ԍ��̂ɂ��ގv���ł���Ă����j�̊ϓ_����A�K���ɓw�͂�����Ƃ݂̂��~����Ƃ������{�ɂ������B
�u�V��v�ۉw�̓]���~�������
�@�ŋ߁A�C�̖œ���b���肪�V������킵�Ă��邪�A���̒��ł����̎�����m�������͌����悤�̂Ȃ����������������B�悭�X���ő��l�ɂ���܂ꂽ�肵�č����Ă���l�����Ă��A���ӂ̐l�͌��Č��ʐU������āA�N�������Ă����Ȃ��P�[�X����������B�������X���S���Ă��̎����ɓ��荞�ނ��Ƃ����邪�A�w�ǂ͌N�q�낤���ɋߊ�炸�ōς܂��Ă��܂����Ƃ������B
�@����̎������P�ӂ��ʂ��Ȃ��āA�S���̎��Ƃ����`�ŏI����Ă��܂������ƂɁA���̐��ɂ͐_�����������̂��Ƃ����������A���������������B
�@�������A���ʂ��猩��A������������Ȃ������̂�����A�����ȍs���Ƃ������ƂɂȂ�B���������G�}�[�W�F���V�[�������ɁA�Ƃ����̔��f�ōs�����N�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���ƁA��Ƃł͂ǂ�ȌP�������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��낤���B����͌l�̐��܂���̃Z���X�̖��ł����āA�P�����@�͖����̂��낤���B��Ɠ��̈��S�Ǘ��̒���KYT�Ƃ����̂����邪�A����Ȓ��x�̂��Ƃ����Ȃ��̂��낤���B
�@�܂��āA�o�c�̃g�b�v�͏�ɏ��Ȃ���炷�₢���f��v��������B�ЂƂ��ъԈႦ��ƁA���[�̎҂܂ő傫�Ȕ�Q����B�o�u�����Ɏ���L���锻�f�������g�b�v���o�c���Ă�����Ƃł͍��A�l�ꔪ�ꂵ�Ă���Ƃ��낪�����B��@�Ǘ��Ə̂��ĉ�������Ă���Ƃ��������悤�����A�v�́A�����������������G�}�[�W�F���V�[�̗\����ςݏd�˂čs���A����ɑΉ�������@���������Ă����ȊO�ɂƂ����̎��̔��f�͂�{���Ă����ȊO�ɕ��@�͖����̂ł͂Ȃ����ƁA�l���������鎖���ł������B
�@�ǂȂ����A���Ă���������Ă������������B
�u���l���̕s�ˎ��v
�@���N�̐��l���̍r��͗l���V���Ȃǂ̃}�X�R�~����킵�����A�T�ˊe�}�X�R�~�Ƃ���������҂�����_���ł������B�����ꕔ�̑������A����ٌ삷��C�͂��炳��Ȃ����A���̑��������Ƃ������ƂɐG��Ă݂����B
�@�S���I�ɂ��낢�날�����炵�����A���ɍ��m���ƍ����s�̗Ⴊ�����ɕ��ꂽ�B���̂Q�̋��ʓ_�͎l���ł��邱�ƂƁA�����̂̎̍u���ŋN�����Ƃ������Ƃł���B�l���Ƃ������ɂ��ẮA���͕s���ʼn����m��Ȃ����A�̍u���Ƃ������Ƃɂ��Ă͂��������т����肵���B���������w�̍��A�n�Ǝ���I�Ǝ��Ɏ����̂̎��b�������ɗ������A�ǂ���܂�Ȃ��ĐÂ��ɂ��Ă͂������A���̒��̓u�[�C���O�ł������B���������l���̂Ƃ��͂ǂ����̑�w�̐搶�������Ǝv�����A������܂�Ȃ��b�ł������B�����A������o���Ă���̂́u��l�̐��E�ł́A�S�Ă����ꂢ���łł͕Еt���Ȃ���B�����������͂���ȍl�����őΏ�����Ƃ�����v�Ƃ�������������������b�������͊o���Ă���B���̎��A�ǂ�Ȃ܂�Ȃ��b�ł��A������̕�����̃Z���X��������A����Ȃ�Ɏ����̖��ɗ����̂�����̂��ƒm�����B���̍l�����͂����̔��ʋ��t�Ƃ��Ď����̂��̌�̐l���ɑ�ϖ�j�ɗ����Ă���B
�@�����A���l���Ɏ����̂̎��o�čs���Ƃ͎��̂S0���N�O�̌o�����炷��Ƃт�����ł������B�Ȃ�Ǝ�Î҂̊��͂̂Ȃ���B������̓��[�U�[�ł���B���q�l�ł���B���q�l�Ɍ}������K�v�͂Ȃ����A�j�[�Y�ɍ��킹��A�^�ɂ��q�l�����߂Ă��邱�ƂɑΉ�����Ƃ������z�����S�Ɍ����Ă����̂ł͂Ȃ����B�����Ă��A���炵�Ă��A���肪���������Ƃ����v���_�N�g�A�E�g�̍l���ɋÂ�ł܂��Ă����Ƃ�����ꕔ�̎�҂ɓ˂��ꂽ�̂ł͂Ȃ����B���͐�y�����u�Q�l�ȏ�̒��u�҂������肵�Ă����炻�̍u�`�A�u���͎��s�������Ǝv���v�Ƌ�����ꂽ�B���ꂭ�炢�̊o��ŁA�v���Ƃ��Đ^�������ŗՂ߂Ƃ������Ƃ��Ǝv���B
�@�����������鏤�i�i�n�[�h���\�t�g��)�ɑ��āA���͂̏d�v�������߂čĔF�������B
�u����ς�i���v
�@�ŋ߁A���Ƃ̐��E�ł����낢��ȕs�ˎ������`����Ă���B�������̔j�]�A�_�C�G�[�̃g�b�v����Ȃǃo�u���̃c�P���\�ʉ����Ă����̂ł��낤�B�C�g�[���[�J�h�[���_�C�G�[�㍂�Œǂ��z�����Ƃ��A���̃C�g�[���[�J�h�[���W���X�R�����v�Œǂ��z�����Ƃ��A����2000�N�͏��Ɖ�ŕω��̉ߓn���ɒ������Ă���悤�ł���B
�@���̒��ŁA���j�N���̃t�@�[�X�g���e�C�����O���ٍʂ�����Ă���B������̂����ɔ��㍂�ł͂�����Ȃ��C�g�[���[�J�h�[��藘�v�����������ł���B���ӂ̐l�ɕ������Ƃ���ɂ��ƁA���j�N���̏��i���i���͂܂��܂��ł���Ƃ����B���͂��āA�����Ⓦ��A�W�A�̖D���Ƃɂ�������������Ă������Ƃ����邪�A���n�ŕi����ǂ����鎖�͎���̋Ƃł������B
�@�P0��23��(��)�̒����V���[���P�ʂɑn�ƎҖ��䐳��������̋Z�p�ł��A���ꐻ�i�����葱����Εi���͂悭�Ȃ�܂��v�ƌ����Ă��邪�A�i����ǂ����鎖�͂���Ȑ��Ղ������̂ł͂Ȃ��B�����̓w�͂����Ă���͂��ŁA���͂����̂Ƃ��낪��Ԓm�肽���B
�@�Ƃ͂����A�������͕i���ʂł܂��܂��̏��i������悤�ɂȂ��Ă����̂��m���ł��낤�B�ǂ���ɂ��Ă��A�����Ăࢂ���ς�i�������{�ł���ƌ������Ƃ����߂ĔF����������ł���B
�u�O�H�����Ԃ̃��R�[���B�����v
�@����̖������߂͈�S���҂܂��͂��̒����̏�i�̉�Ђ���낤�Ƃ���P�ӁH����N�����������ł���B�Ƃ��낪��Ƃ̑召���킸�g�D�͂����e�F��������ւ��̂܂ɂ�����B���ꂪ�g�D���������ł���B���̌��ɂ��Ă͐����Ƃ̂Ƃ���ŏq�ׂĂ���̂ŏȗ�����B
�@�Ƃ��낪�A�����Ɉ�l�̈��ӁH�̐l�Ԃ������B�����������̂ł���B��ʂɁA��l�̖����҂ɑ��āA�S�l�̖����\���R������Ƃ����Ă���B�ߍ��A�}�X�R�~�ł����������ɂ���Ė���݂ɏo�������Ǝv������̂����ɑ����Ȃ��Ă����B�����h���ɂ́A��������������Ηǂ��̂����A��Ƃ͐������ł���ȏ�A�@���Κ����o��͖̂h���悤�������B���̎q��(�Љ�l�j�͉ƂŐH���̎��Ɏ��X�����̋߂Ă����Ђ̋�s�����ڂ��B�����čŌ�Ɂu���̉�Ђ̓����̈ꕔ���O���Ƀ`�N���A��Ђ��ԈႢ�Ȃ��ׂ�邺�v�ƚ����Ă���B
�@���̖����������邱�Ƃ͂قƂ�Ǖs�\�ɋ߂��Ǝv���邪�A�B��̕��ւƂ����K�X��������������ł���B�O���Ƀ^���R���O���Г��Ƀ^���R�����g�D������Ēu���Ȃ����낤���B�@���̑��q�̈ӌ����ƁA��Ђ̖��ɗ��ӌ��������Ԃ�����Ă���̂ł����˂��B
�u���V�A�����ƕv
�@���V�A�����̃j���[�X�ŋ��������Ƃɂ́u���ꂾ���̃j���[�X���悭��X�̂Ƃ���ɓ͂����ȣ�Ƃ������Ƃł���B������܂ł̃��V�A�ŌR���{�݂̃g���u�����͑S�ČR���@���Ƃ��Ĉł���łɑ�����Ă����͂��ł���B����̌������V�A�̍����ɂƂ��āA�ŋ߂̏��`�B�̃p���[���܂��܂��ƌ����t�����Ăт����肵���̂ł͂Ȃ����B
�@�����玟�ւƔ��\����鍂���̏����͕����Ă���f�l�ł��܂������M�p�ł��Ȃ��悤�Ȗ����������e�ŏ���i���ł���Ǝf�����B�����ɑ���͂قƂ�ǖ����A�ސ��ɂ������������B�Ⴆ�A�n�b�`�ɂP�l����Ƃ������\���L�������A�ǂ����������Ɋ�Â��Č����Ă���̂��A�܂������s���ł������B�܂�A�����̎��_�܂œ����ƌ�M���A�ǂ̂悤�ȓ��e�ł��������ȂǁA�܂���������������Ă��Ȃ��B
�@�����A���������{�̊�Ɛl���������ҁA����҂Ƃ����̓_���B���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������悤�Ɏv����B
�@�@�@����͎������ސ����B
�@�@�A�ސ��Ƃ���ǂ����������Ɋ�Â��Ăǂ����_�������ʂ��B
�@�@�B�ň��̎��Ԃ͂ǂ��Ȃ邩�B
�Ƃ������Ƃ������A�b���ق����S�����Ęb���悤�ɂ��˂ƁA����̌��������Ŕ��Ȃ��B
�u�����Ƃ̕s�ˎ��v
�@�����Ƃւ͎��͒��ڕi���Ǘ��̎w�����������Ƃ͂Ȃ��̂ł����A���Ǝ���̂�������Ƃւ͐�����������Ă��܂����B�����̂ǂ̊�Ƃ̕����u���͂��炵���B���{�̐H�i��Ђ̒��ł̓i���o�[�����̉�Ђ��v�Ƃ���������Ă����܂�������������̉�Ђ̈ꕔ�̃f�[�^�ɂ͂��̂悤�Ȏ������ǂݎ��܂����B�Q�O�N���O�ɂȂ�܂����A�������~���N�̂��ƂŐ��̎В����ĂɃN���[�����������Ƃ�����̂ł�������̂Ƃ��̑Ή��̎d�������Δ����Ă��܂����B�����Ƃ�������e�i���j�Ƃ����B�R�Ƃ����ԓx�Ŏ����[���̂��������Ă���܂����B���͕i���Ǘ����ł��̂ŁA�Љ�`�̂��߂ɃN���[���͐ϋɓI�ɏo���̂ł�������̒��ł��N���[���Ή��͐�_���g�c�i���o�[�����ł����B���ꂪ�������сA�i���Ǘ��Ƃ����A�N���[���Ή��Ƃ����A�Ȃ�Ƃ��e���ȁB
�@�������̎��̎w����ЂŁA���Đ��i�ɎG�ۂ�����Ƃ����e�[�}�Ō����Nj����������Ƃ�����܂����������̂悤�Ƀo���u�ɔ��������������Ƃ����P�[�X��������������܂����B����قǃv�����炷���A�o���u�ɎG�ۂ��t���₷���Ƃ����̂͏펯�ł��B�ł��A���̖�������������Ђł͂P�O�N�o�Ƃ��̃g���u����m���Ă���l�͔����ȉ��Ɍ����Ă��܂��܂����B������K���ɂȂ��Č����ׁA��ςȎv�������ă}�j���A�������܂������A�}�j���A���̑��݂���m��Ȃ��l�������ȉ��ɉ����̊Ԃɂ��Ȃ��Ă��܂��Ă��܂��B
�@�������������ɂ́u�O��v�ł��B��肪���������Ǝv�����Ƃ��Ɏ~�߂�̂ł͂Ȃ�������ƃ_�C�i�~�b�N���p�����Ă䂭���Ƃł��B�p���͗͂ł��B�i����肪���������礍��x�̓R�X�g�E���_�N�V�����Ƀ`�������W����̂ł��B�u�����ƈ����ł��Ȃ����B�����Ǝ肪�����Ȃ����v�ƓO�ꂵ�ĒNj����čs���A�������}�j���A���ɕς��čs���܂��B�Y����Ă��܂����Ƃ͂Ȃ��Ȃ�ł��傤�B
�@�N���[���Ή��ɂ��Ă��A��@�Ǘ��̖��Ƃ��Ă��܂��������������Ǘ��̖�肾�Ǝv���܂��B�g�b�v�ɂ͈������͓`���ɂ����Ƃ����̂��A�g�D�̓����ł��B�܂��A�g�b�v�͏�Ɍ���ɏo�čs�����ƁB�����āA�w������J���Ĉ�������_����ɑS���̋��ʔF���ɂȂ�悤�ɂ��Ă������Ƃ���ł��B���{�͂P�O�N�O�܂łɁA�i�����̂����ǂ���ׂ͒��܂������A���̌㤋}�ɃR�X�g���ɕς��܂����B�ł��A���̓O�ꂳ���s�\���ł��B�W�O�N��ɂ��ꂾ���i�����ɑ吨�̐l�̒m�b�����W�������̂��������X�O�N��̃R�X�g���_�N�V�������ɑ吨�̐l�̒m�b���Ȃ����W�ł��Ȃ������̂ł��傤���B�����ȊC�O�V�t�g��X�g���Ə̂�����ŃR�X�g��������̂ł��傤���B��������͉������Ă���g���u�����N�����Ă͉��ɂ��Ȃ�܂���B
�@�W�O�N��̂悤�ȁA��Ђ̈�������_���]�ƈ��S���̋��ʔF���Ƃ��A�S���̒m�b�������W������悤�ȃV�X�e�����\�z���������̂ł��B
�u����̑I���v�ƁuIT�v���v
�@����̏O�c�@�c���I���Ŏ��̑I����ł́A�h�s�����͂ɐ����i�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ̑啨��b�����I���܂����B�I�����Ԓ��͂����Ђ����疼�O�����̘A�āA�A�Ă����ł����B
�@���܂�̂��邳���ɁA�Q�O��̒��j�̓z�[���y�[�W�ɋ������悤�Ƃ��܂������A�z�[���y�[�W�ɂ̓A�N�Z�X�ł��܂���ł����B���j�́u�Ђ���Ƃ���Ɨ����邩���v�ƌ����Ă��܂������A�Ă̒肻�̒ʂ�ɂȂ��܂����B
�@���āA�A�Ă͑I�����Ԓ��̉^���Ƃ��đ�ϗL���Ȏ�i�ł����B�u���̐搶�͊撣���Ă���Ă���悤������A1�[����Ă�邩��ƘA�ĂƂ������Ȃ����̒����玄�����͔����ȃj���A���X��k������ē��[�����Ă��܂����B
�@�������A������̉Q�ł��B�h�s�Ƃ�����i���g���Ύ����̌l�咣�͂��܂˂��`��鎞���ɂȂ�܂����B���̐�[���s���Ă��炢���������Ƃ���Ԓx��Ă���̂��A����̑I���Ō��Ƃ����قnj����t������܂����B
�@�������̊�ƂɂƂ��Ă��u�����̊Ԃ܂ł͗L���Ȍ����̂悢��i�ł��������̂��A�����Ƃ������ɒ������Ă��܂����낵���������v�i���ɂh�s���p�̐��E�ł�)�Ƃ������Ƃ��u���R�̐v�Ƃ��Ċ̂������Ēu���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍ���̑I���ŋ����܂����B
��O���l��Ƣ�_�̍��
�@���t�A��������|���Ėʓ|�����Ă���30�Α�O���̌�yS���碃��[���A�h���X���ς��܂�����Ƃ������[�����͂���܂����̂ŁA��ύח������܂�����Ƃ����Ԏ������[���ł��܂����B
�@�Ƃ��낪�A������S���玄�̒��j���Ăɢ�����Ƃ͉����B���O�̐e��������������Ɖ��Ƃ����룂Ƃ������[�������܂����BS�͎��̒��j�Ɛe�������Ă����̂ł����A���̕Ԏ��ɂ͈��R�Ƃ��Ă��܂��܂����B���ɂƂ��ĉ��̂��Ƃ�炳���ς�킩��܂���B�܂��A���j�ɕ����Ă݂܂����B������������H��u�����A����������B�����ƊȒP�ɂ��Ȃ���v�����ȏ�Z���Ȃ�Ȃ��棢�Ⴄ��B�e���Ƃ͘b���ɂȂ�˂���Ƃ������Ə����Ă��܂��܂����B
�@���ɍ��ꂪ���ӂȒ����ɕ����܂����B������Ƃ������t�͂����̂��l�����̐l�Ɏg�����t�ł��̃P�[�X�ł͂ƂĂ�����ȕԎ���B�{�l�����S���Ă���͓̂��R�棢�ł��A�l�͖ڏ�̐l�ɂ��g���Ă��邯��ǁB�̎��A�y�̗p�ꂩ�����Ⴄ���ĂB�ǂ����������Ă������킩��Ȃ���Ƃ�͂蓦�����Ă��܂��܂����B
�@���悢�掄�̓��̒��͍������Ă��܂��܂����B�������Ƃ������t���g���Ă����f�������Ă����Ђ̕��Ɏӂ肩��������b���A�ӌ����Ă݂Ȃ����B�F����ʂɁB�����Ƃ��C�ɂȂ�܂���棂Ƃ������Ⴂ�܂��B�������A�T�ŕ����Ă���Ⴂ�l�͎������������A�ɂ���Ə��Ă��܂��B���̐l�B�ɢ�g�������������ł�����ƕ����Ƣ���������ł���u�ǂ����B�Ȃ��v�u���[��B�킩��܂���v�ƌ����Ԏ������Ԃ��Ă��܂���B�ǂ����A30�Α�㔼�����ɕ]�����قȂ�悤�ł��B
�@�����������Ă��邤���ɢ�O���l���_�̍����肪�������܂����B���ɂ��Â���a���̂��錾�t�ł��B�����ł��B���ƂȂ��킩���Ă��܂����B�Ⴂ�l�ɂƂ��Ģ������Ƃ������t���Â���a���̂��錾�t�������̂ł��B���̌��Ɋւ��ẮA���ɎӍ߁A�P��̈ӎu���Ȃ��̂Ɠ��l�ɁAI��y�AM��y�����l�ł��傤�B���t�̐���ԃM���b�v�Ƃ����̂͋��낵���ł��ˁB
�@��������1���@�Ƃ��Ģ�܂��l(���q�l)�ɕ�����Ƃ����̂��S���ł����A�l�ɕ����������ł͖��͉������܂���B�����T�̂����Ƃ���܂Řb���Ă����̂ł����A��������܂��B�ł��A�������͂�͂�A�l(���q�l)����悭�����Ƃ��납��n�߂āA���Ԃ��A�悭�l����(�m�b������)�̂��������Ƃ������Ƃ�������܂��Ǒ̌������܂����B
| �z�[�� | �j�[�Y | ���� | �v���t�B�[�� |