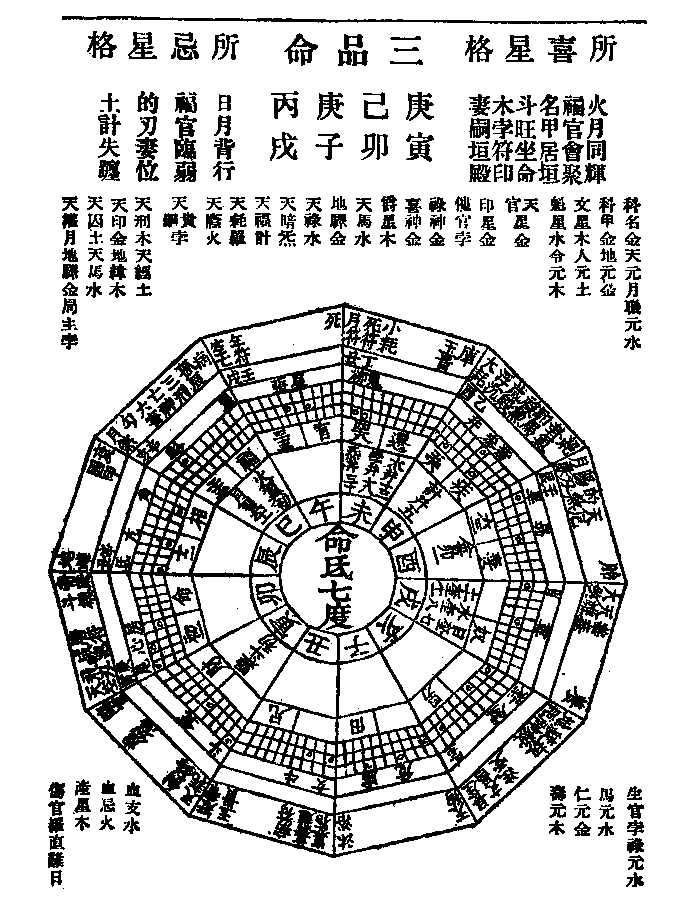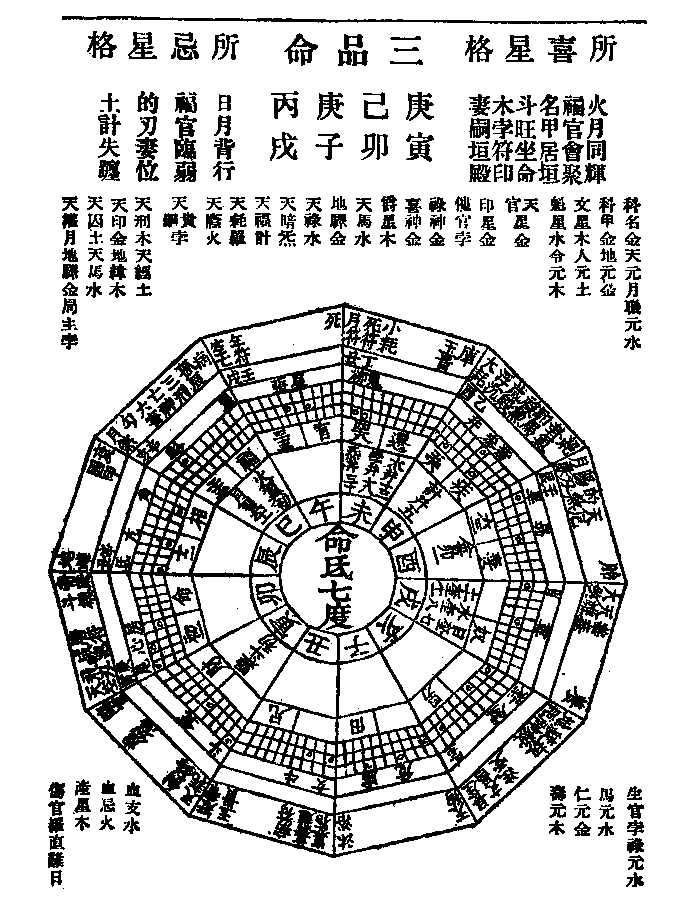七政占星術の基礎 その1
七政占星術の星図の出し方と見方について解説を試みます。本項の作成当初は七政のみの解説だったのですが、西洋占星術の比較をしながら解説したいと思います。ただし、西洋占星術については素人なので、間違っているところがあるかもしれません。西洋占星術については、さまざまな書籍やウェブサイトがありますので、正確を期すにはそれらを参照してください。
参考書は、参考文献に掲げていますが、主として次の本を使います。
『七政四餘推命全書』『古今七政五餘析義』『古今七政占星速成』
『実証占星論命』『七政占星奥義』『七政四餘快易通』『張果老五星論命講義』
『占星術バイブル』『占星学教本』『Stargazerで体験するパソコン占星学』
なお、「余」は「餘」という文字を使いますが、簡略化された「余」も使うことがあります(判田格師の書は『七政四余』なので)。また、紫?は紫気と表記します。中国の本でも紫気と表記するものもありますので、あえて難しい字は使わないことにします。
以下、中学生程度の天文学の知識があり、干支、五行など中国占術の基礎的な知識はあるものという前提で話を進めます。
-このページの目次-
1.星図あるいは命盤
2.十二宮位
3.七政四餘
4.紫気の行度計算方法
5.月孛、羅[ゴウ]、計都の行度計算方法
6.十二宮
7.命宮の位置および命度
8.身宮
9.二十八宿
10.基本星図の作成
1.星図あるいは命盤
星図という言い方は西洋占星術から来ているようで、命盤という方が普通かもしれません。ただ命盤というと紫微斗数など他の占いと勘違いしそうなので、実星を使うという意味から星図と呼ぶことにします。
七政星図とは次のようなものです。(『果老星宗』からの抜粋)
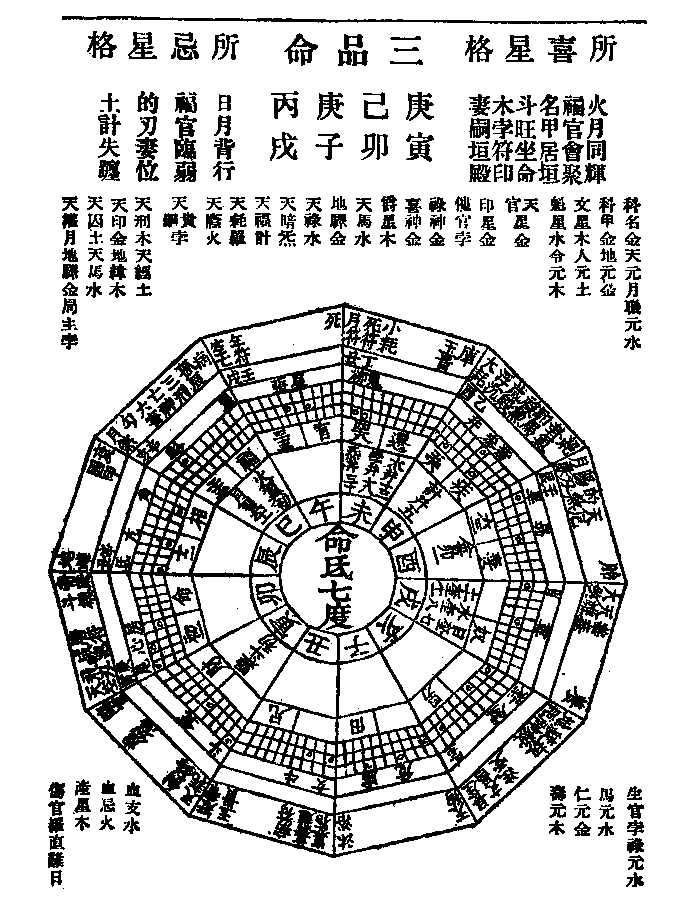
用語については後ほど解説しますが、中心に書かれているのが命度、中心から順に十二宮位、七政四餘、十二宮、二十八宿、行運干支、神殺です。このうち行運干支については古い方法で、今は行運は違う見方をしますので解説しません。それを除く項目についてざっと解説します。
(1)命度
命度とは太陽がどの位置にいるかを示すものです。これが基準位置と考えてください。なお、この図では命度を二十八宿で示していますが、十二宮位で示す場合もあります。あとで詳細は解説します。
(2)十二宮位
十二宮位は、天の方角を示すものと理解してください。西洋占星術の十二星座に対応します。
(3)七政四餘
これは、天体(惑星)および天文現象のそのときの位置を示します。ただし紫気だけはその天体もしくは天文現象がはっきりしません。
(4)十二宮
中国占術では、人事百般を十二の事柄に分類します。その十二宮のある位置にある星や神殺等で十二宮の意味する内容の判断をします。
(5)二十八宿
七政では二十七宿ではなく二十八宿を使います。星宿は密教系の占星術から由来したものだと思います。これも一種の星座であると理解しておけばいいでしょう。ただし春分点が基準ではなく、特定の恒星の位置で示されます。
(6)神殺
星と宮位や二十八宿、あるいは星同士などの関係によって吉凶を示すためにつけられた名前です。
以上が星図の構成要素ですが、(1)~(5)で基本的な占いは可能です。しかし神殺がないと七政占星術としての深みは出てきません。
概観がわかったところで、それぞれの詳論(といっても必要最低限の知識)に入ります。
2.十二宮位(周天十二宮)
十二宮位というのは、端的にいえば天球を12の方位に分割したものです。基準は春分点と太陽黄経です。太陽黄経とか春分点という言葉は、別のサイトなどで調べてください。これは西洋占星術にいう十二星座にぴったり対応します。ま、出処が同じなのであたりまえといえばあたりまえですが・・・。また、六壬でいう月将と同じです。(正確にいえば違うのでしょうが、実用的には同じと考えても差し支えありません)
表を示しますと次のようになります。
| 黄経 | 0度 | 30度 | 60度 | 90度 | 120度 | 150度 |
180度 | 210度 | 240度 | 270度 | 300度 | 330度 |
| 新暦 | 3/21 | 4/20 | 5/21 | 6/21 | 7/23 | 8/23 |
9/23 | 10/24 | 11/23 | 12/22 | 1/21 | 2/18 |
| 星座 | 白羊
牡羊 | 金牛
牡牛 | 双子 | 巨蟹 | 獅子 | 処女
乙女 |
天秤 | 天蠍 | 人馬
いて | 山羊
やぎ | 宝瓶
水瓶 | 双魚
うお |
| 節気 | 春分 | 穀雨 | 小満 | 夏至 | 大暑 | 処暑 |
秋分 | 霜降 | 小雪 | 冬至 | 大寒 | 雨水 |
| 十二宮位 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 |
辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 |
新暦で日付が書いてありますが、それはその位置を太陽が通る時期です。ただし年によって1日、2日ずれることがあります。ついでに言えば、太陽が黄経0度を通るときが春分の日であり、180度を通るときが秋分の日ですが、それも年によって違うことはご存知でしょう。
太陽黄経は地球の自転軸および公転軌道によって決められますので、少なくとも生きている間に認知できるほどの変化はありません。天球上の固定された座標と考えて問題ありません。
度数のつけ方ですが、注意してほしいのは、太陽黄経の方向と十二宮位の順序が逆だということです。度数は太陽基準ですので、黄経と同じ方向でとります。十二宮位は逆順ですが、理由は省略します。ですから、太陽黄経0度は戌の0度であり、戌の30度が酉の0度ということになります。
3.七政四餘
七政四餘とは、次の名称の星です。
七政:日(太陽)、月(太陰)、火、水、木、金、土
四餘:紫気、月孛、羅[ゴウ]、計都
[ゴウ]は日へんに侯という字です。
その他に三王という星があります。それは、
三王:天王星、海王星、冥王星
当然のことですが、三王は最近発見された惑星であり、古くは使いません。もっとも冥王星は惑星から外れてしまいました。
七政と四餘で十一曜と言います。
七政については説明は不要でしょう。位置の計算方法については、理科年表や天文年鑑あるいは天体位置計算の本を参照してください。そういう面倒なことをしなくても、最近はサイトで天体位置を計算してくれるソフトやホームページがあるのでそれを利用すればいいでしょう。七政の位置だけなら、西洋占星術のホロスコープでもOKです。星の位置については、十二宮位と星座を対照すればいいです。
七政のうち、惑星は逆行したり運行が非常に遅くなるときがあります。それは天体位置を前後1日を計算することによってわかります。逆行の場合は逆、運行が遅いときを留といいます。星表や西洋占星術のホロスコープには逆行が示されているので便利です。
また、惑星の位置表記は二十八宿で表示している星表もありますが、私自身は二十八宿ではなく、太陽黄経および十二宮位における位置の度数を使っています。この方が私は簡単だと思っているのと、西洋占星術のホロスコープに対応できるからです。
四餘は天文現象を示すものと、何を指しているのかはっきりわからないものがあります。四餘の各星の天文現象は次に示すとおりです。
紫気:天文学的意義ははっきりしない。計算法等は後述。
月孛:月の遠地点
羅[ゴウ]:月の昇交点
計都:月の降交点
なお、羅[ゴウ]、計都は逆になっている場合があります。これは歴史上で両者が混同されていたためです。参考書によると「開元占経」の「九執暦」が逆になっていたことが発端となっているらしいです。
現在は、上の方が中華圏では一般的でしょう。参考ウェブサイト。
http://www.spiritual-eye.com.tw/ci-2-32.htm
4.紫気の行度計算方法
(この項については、2013年2月12日に大幅に書き換えました)
紫気については、ずっと以前からその起源を調べているのですが、よくわかりません。多くの書の結論は、紫気は仮想的な天体であり、実星とか実際の天文現象ではないということです。とはいえ、それを求める計算方法が必要なので、いろいろな本の紫気のデータを拾ってみて、その計算式を考えてみました。
以前提唱した計算式は、
[紫気黄経] = mod(0.0352173×D+300,360) (註、左式は厳密には誤りです)
が黄経となります。modとは、360を超える場合は、360で割った余りとするという記号です。Dというのは1980年8月7日からの日数で、実用的にはこれで十分ではあります。
しかしながら、Dの係数である0.0352173という数字には錯誤があることがわかりましたので、ここに訂正する次第です。その原因は鐘義明師の計算をうのみにしてしまったことに起因します。
この過程については、七政占星術~番外編の4.に比較的詳しく書きました。で、そこに提示した結論の式は、
[紫気黄経] = mod(0.035201691×JD+290.82,360)
です。ここでJDはユリウス通日です。修正ユリウス通日ではありませんので、気をつけてください。ユリウス通日については、計算してくれるウェブサイトがありますので、それを参照してください。あるいは暦の専門書をひもといてください。
5.月孛、羅[ゴウ]、計都の行度計算方法
これらは、月の遠地点および昇交点(降交点はその反対側)の黄経で計算されます。しかし、意外とこれらの数値の計算方法は載っていないのでここで紹介します。
以下は『古天文学』(斉藤国治著)に載っている計算で、そこには近地点と昇交点の黄経計算式があげられています(オリジナルはタッカーマン表)。遠地点は近地点の反対側、降交点は昇交点の反対側です。反対側というのはすなわち180度を加える(または引く)ことで得られます。
まずはユリウス通日を求めます。それをJDと置きます。ユリウス通日の計算方法はいろいろな本やサイトにありますから、それを参照してください。
ユリウス通日を、元期1800年に修正します。この元期をJとしますと、Jは次の式で得られます。
J=(JD-2378496)/36525
もとめられたJをもとに近地点黄経、昇交点黄経を求めます。それぞれPNL、OMGとします。なお、^はべき乗を示します。単位は度です。
PNL=225.397325+4069.053805J-0.0102869J^2-0.0000122222J^3
OMG=33.272936-1934.144694J+0.00208028J^2+0.00000208333J^3
これで得られた度数は360度を超えているはずなので、360で割った余りの度数を近地点黄経、昇交点黄経とします。
近地点黄経から180度プラスマイナスしたものが月孛、昇交点黄経が羅[ゴウ]、昇交点黄経から180度プラスマイナスしたものが計都、となります。
6.十二宮
十二宮とは、人生の諸問題を12に分類し、それを星図にあてはめたものです。これは中国占術(というか中国文化)における人生の諸問題の捉え方であり、ほぼすべての占術に共通する考え方です。
命宮から相貌宮まで、その名称と意味を挙げます。
命宮:自分自身、個性、外見、先天的な能力、性格
財帛宮:財運、資産、収入源
兄弟宮:兄弟姉妹の影響力、縁の厚薄
田宅宮または父母宮:不動産、家業、父母、祖先の影響力
男女宮または子女宮:子女全般、賢愚、寿夭
奴僕宮:部下、目下との関係、影響力、助力の有無
夫妻宮:配偶者全般、婚姻、妻妾
疾厄宮:疾病、傷害、災難など
遷移宮:旅行、転居、転職など
官禄宮:職業、名誉、地位など
福徳宮:幸福感、貴賎など
相貌宮:顔形、感情、善悪観念など
命宮の位置が決まれば、命宮を基準として十二支の順とは逆に、すなわち太陽の進行方向に財帛、兄弟、田宅、・・・と並べていけばいいです。
注意してみると命宮と夫妻宮、田宅宮と官禄宮はそれぞれ反対側にあります。このことから、どうしてこういう順序になったかは何となく想像がつくでしょう。なおこの4つの宮を四正宮と呼びます。
では、次に命宮の位置の決め方を説明しましょう。
7.命宮の位置および命度
命宮は生時と月将で決まります。月将とは大六壬の章で説明しているとおり太陽の位置ですから、太陽の黄経を計算し、それが上の表のどの節気に当てはまるかをみて、下表から求めても同じです。ただ、中国占術に慣れていれば、節気の表にした方が簡単でしょうから、節気での表としています。命宮は、大六壬でいう地盤卯の上神ですし、西洋占星術でいえば上昇(星座)宮にあたります。すなわち、その時間に地上に顔を出す宮位を示しています。
| 節気・月将\占時 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 大寒~雨水・子 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 |
| 雨水~春分・亥 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 |
| 春分~穀雨・戌 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 |
| 穀雨~小満・酉 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 |
| 小満~夏至・申 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 |
| 夏至~大暑・未 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 |
| 大暑~処暑・午 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 |
| 処暑~秋分・巳 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 |
| 秋分~霜降・辰 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 |
| 霜降~小雪・卯 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 |
| 小雪~冬至・寅 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 |
| 冬至~大寒・丑 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 |
次に命度ですが、命度とは太陽が十二宮位のどの位置にあるかを示すものです。二十八宿の度数で示すこともあります。これはすなわち、命宮が何度まで地上に現れたかを示すものです。
例えば、太陽の黄経が313度だとしますと太陽は子宮の13度にあるとなります。この時期は大寒以降ですから、時刻を戌時だとしますと命宮は巳宮です。巳宮の13度を命度と置きます。
前に、命宮というのは西洋占星術でいう上昇宮だと言いましたが、正確に言えばちょっと違います。西洋占星術でいう上昇宮とはアセンダントが属する星座宮で。アセンダントとは地平線と黄道の交点のうち太陽の昇ってくる方、すなわち東方の交点にあたります。実用上は命宮と上昇宮は変わりませんが、考え方は異なります。
西洋占星術では、アセンダントが決まりますと、ハウス(室)が決められます。ハウスは1から12まであり、アセンダントから黄経の方向に第1ハウス、第2ハウス、・・・、第12ハウスと付けられます。第1ハウスと第12ハウスの境がアセンダントとなります。そうすると十二宮と12ハウスはほぼ次のように対応します。ついでに西洋占星術におけるハウスの意味も挙げておきましょう。
| 十二宮 | ハウス | 十二宮の意味 | ハウスの意味 |
| 命宮 | 第1 | 本人、先天的なもの | 本人、性格、容貌 |
| 財帛宮 | 第2 | 財運、金銭、資産 | 金銭、所得、動産 |
| 兄弟宮 | 第3 | 兄弟姉妹の影響 | 知識、旅行、兄弟 |
| 田宅宮 | 第4 | 不動産、父母、祖業 | 家庭、不動産、住居 |
| 男女宮 | 第5 | 子女、寿夭、賢愚 | 恋愛、娯楽、子女 |
| 奴僕宮 | 第6 | 部下、目下 | 健康、労働、奉仕 |
| 夫妻宮 | 第7 | 婚姻、配偶者、妻妾 | 結婚、配偶者、契約 |
| 疾厄宮 | 第8 | 疾病、災難 | 遺産、事故、遺伝 |
| 遷移宮 | 第9 | 旅行、転職、転居 | 精神、外国、旅行 |
| 官禄宮 | 第10 | 職業、地位、名誉 | 社会、地位、成功 |
| 福徳宮 | 第11 | 福徳、困窮、貴賎 | 友情、仲間、希望 |
| 相貌宮 | 第12 | 相貌、感情、善悪 | 障害、秘密、隠遁 |
さて、上のように比較してみると、十二宮の象意と西洋占星術のハウスの意味はかなり近いことがわかります。第8ハウスや第12ハウスなどは西洋占星術においても諸説があるようで、そういうハウスでは十二宮の意味が違っています。
西洋占星術のハウスの取り方にはいろいろあるようで、七政占術の十二宮のように各ハウスの角度が30度で同じ取り方を「イコールハウス・システム」と言いますが、これは現在の主流ではありません。現在の西洋占星術の主流は「プラシダス・システム」であり、これはアセンダントとミッドヘブン(天頂)を基準として、ハウスの角度が各ハウスで異なる取り方をする方法です。詳しくは西洋占星術の本を参照してください。
それにしても、意味もよく対応していますので、七政占星術と西洋占星術は同じもの(占術?哲学?宗教?)を起源としたと考えられます。
8.身宮
上の七政星図には出てきませんが、身宮というものがあります。さして使うことはないかもしれませんが、ここで紹介しておきましょう。なお、身宮は西洋占星術では明示的には出てきません。
身宮の取り方には、2つの説があります。
①月(太陰)のある宮位を身宮とする。身度はそのときの月の度数とする。
②太陰宮を月将とみたてて占時とで天地盤を作る。ただし天盤を逆に配する。
そのときの酉の上にある十二支を身宮座位とする。身度は太陰の度数とする。
①の説は星図をみればいいので簡単です。
②の説を例で説明しますと、例えば太陰が卯にある場合で辰時生まれならば、地盤辰を1とすると酉は6番目となります。(これはすぐ前の支ということである)すると卯を1として逆に数えて6番目は戌となり、つまり戌が身宮ということになります。
わかりにくいと思いますので、下表のようにまとめました。太陰宮とは月(太陰)のいる十二宮位です。
| 太陰宮\占時 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 子 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 |
| 丑 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
| 寅 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 |
| 卯 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
| 辰 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 |
| 巳 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
| 午 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 |
| 未 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
| 申 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 |
| 酉 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 戌 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
| 亥 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
9.二十八宿
二十八宿は、十二宮が天球(黄道)を12に区分したように、天球を28に分けたものです。中国の星座ととらえればいいと思います。ただし、十二宮が春分点を基準に黄道を12等分したのとは違い、二十八宿は特定の恒星をその宿の境としていますので、28等分ではありません。その境となる恒星を距星(その宿の始まりの星)と呼んでいます。さらにいえば、二十八宿はもともとは黄道を区分するためではなく白道(月の天球上の軌跡)を区分するための星座です。しかし七政では太陽等の惑星を使いますので、二十八宿の位置も黄経で計算しなおします。
恒星というのは、人の一生ぐらいの間ではほとんど動かないのでそのぐらいのスパンであれば固定して考えても問題ありません。(50年で1度ぐらい変わる)ただし、500年ぐらいとなると10度程度変わってきますので、これは影響が大きくなります。最近の人の推命をやるぐらいなら下記の表で十分でしょうが、歴史上の人物となると、修正が必要です。恒星の位置計算については、参考書を見てください。
下の表は次のサイトと恒星表を元にして、黄経は私が計算したものです。
http://www.chancezoo.net/qixiang/28.htm
上のサイトはどうも危険なサイトのようですので、リンクは外しました。このサイト以外に、『中国の星座の歴史』『古天文学』『こよみ読み解き事典』等を参照し、さらに恒星表を参照しました。
| 宿名 | 距星名 | 赤経(h,m)、赤緯(°,') | 黄経(度) |
| 角 | おとめ座α | 13h25m, -11°10' | 203.8 |
| 亢 | おとめ座κ | 14h13m, -10°16' | 214.5 |
| [テイ] | てんびん座α | 14h51m, -16°03' | 225.1 |
| 房 | さそり座π | 15h59m, -26°07' | 243.0 |
| 心 | さそり座σ | 16h21m, -25°36' | 247.8 |
| 尾 | さそり座μ1 | 16h52m, -38°03' | 256.2 |
| 箕 | いて座γ | 18h06m, -30°25' | 271.3 |
| 斗 | いて座φ | 18h46m, -26°59' | 280.2 |
| 牛 | やぎ座β | 20h21m, -14°47' | 304.0 |
| 女 | みずがめ座ε | 20h48m, -9°30' | 311.7 |
| 虚 | みずがめ座β | 21h33m, -5°34' | 323.4 |
| 危 | みずがめ座α | 22h06m, -0°19' | 333.4 |
| 室 | ペガサス座α | 23h05m, +15°13' | 353.5 |
| 壁 | ペガサス座γ | 00h13m, +15°11' | 9.1 |
| 奎 | アンドロメダ座ζ | 00h47m, +24°16' | 20.6 |
| 婁 | おひつじ座β | 1h55m, +20°48' | 34.0 |
| 胃 | おひつじ座35 | 2h43m, +27°42' | 46.9 |
| 昴 | おうし座17 | 3h45m, +24°07' | 59.4 |
| 畢 | おうし座ε | 4h29m, +19°11' | 68.5 |
| 觜 | オリオン座φ1 | 5h35m, +9°29' | 83.6 |
| 参 | オリオン座ζ | 5h41m, -1°56' | 84.7 |
| 井 | ふたご座μ | 6h23m, +22°31' | 95.3 |
| 鬼 | かに座θ | 8h32m, +18°5' | 125.7 |
| 柳 | うみへび座δ | 8h38m, +5°42' | 130.3 |
| 星 | うみへび座α | 9h28m, -08°40' | 147.3 |
| 張 | うみへび座υ1 | 9h51m, -14°51' | 155.7 |
| 翼 | コップ座α | 11h00m, -18°18' | 173.7 |
| 軫 | からす座γ | 12h16m, -17°33' | 190.7 |
上の表は西暦2000年の恒星の位置を示しています。年に0.014度程度増えるので100年で約1度の差が出ます。
上の表で[テイ]という字は「氏」の下に短い横棒の入った字です。「底」からまだれを取った字。
各距星については異説があります。とくに觜宿は非常に狭く、觜宿と参宿の距星は確定していないといっても過言ではありません。この表では順序を重んじて、参宿の距星をオリオン座ζとしましたが、古代はオリオン座δであったとされます。現在はオリオン座δの黄経の位置は觜宿距星オリオン座φ1の前に来るため、順序が逆になります。このあたりの話は『中国の星座の歴史』(大崎正次著)に詳しいです。
二十八宿にはいろいろと分類方法がありますが、次の2つの分類がとくに重要です。
(1)星曜(度主)による分類
四日宿:星、房、虚、昴
四月宿:心、危、畢、張
四木宿:角、斗、奎、井
四土宿:[テイ]、女、胃、柳
四火宿:尾、室、翼、觜
四水宿:箕、壁、参、軫
四金宿:亢、牛、婁、鬼
それぞれの星曜をその宿の度主という。
(2)分野(方角)による分類
東方七宿:角、亢、[テイ]、房、心、尾、箕
北方七宿:斗、牛、女、虚、危、室、壁
西方七宿:奎、婁、胃、昴、畢、觜、参
南方七宿:井、鬼、柳、星、張、翼、軫
10.基本星図の作成
以上で神殺および行運を除く星図は作成できます。始めに示した図のように作成できればかっこいいのですが、ここでは泥臭く、四角い表でつくりましょう。
対冲関係がわかるように、二列に並べます。また通常の星図では子からスタートしていますが、天球の方位と地上の方位はあまり関係ありませんから、あっさりと黄経の度数の方向にそって表を作成します。黄経ゼロをスタートにすると、戌宮からはじまり逆順となります。
2008年台湾総統選挙に立候補する馬英九氏の基本星図を作成してみましょう。別に私は馬候補を応援しているわけではなくて、単に手許にあった星図から拾ったものです。なお、七政四餘、二十八宿は私なりに計算、補正しています。(上の表の現在の度数から1度引けばだいたい大丈夫です)
例 1950年7月13日14時40分 東経114度 出生地 香港
[巳]
福徳 | 張5
翼23 | 土星16 |
. |
[午]
官禄 | 鬼5
柳10
星27 | . |
. |
[未]
遷移 | 井5 | 太陽20
水23 |
. |
[申]
疾厄 | 畢8
觜23
参24 | 金19
月28 |
[辰]
相貌 | 軫10
角23 | 計都2
火14 |
. |
|
[酉]
夫妻 | 婁3
胃16
昴29 | 月孛20 |
[卯]
命20 | 亢4
[テイ]14 | . |
. |
|
[戌]
奴僕 | 壁8
奎20 | 羅[ゴウ]2 |
[寅]
財帛 | 房2
心7
尾15 | . |
. |
[丑]
兄弟 | 箕1
斗9
| 紫気3 |
. |
[子]
田宅 | 牛3
女11
虚23 | . |
. |
[亥]
男女 | 危3
室23 | 木星7 |
表をみてもらえば一目瞭然だと思いますが、若干説明すると、命度は命宮の後ろの数字で、卯の20度ということです。同様に二十八宿も、例えば壁8とあるのは壁宿は戌の8度にあるということです。
命度について補足すれば、これは[テイ]宿との差が7度ありますから、[テイ]の7度ということになります。しかし昔は0度~1度を初度、1度~2度を一度と言っていましたから、昔流に言えば[テイ]宿の六度ということになります。まあこの辺の厳密性は細かい運を見ない限りは必要ないでしょう。
基本星図の作成までが終了しました。これでその1を終わります。
次に配布するべきは神殺ですが、実はこの基本星図だけでも基本的な鑑定は可能です。図の作成ばかりでは面白くありませんから、この基本星図だけ読み取れる意味について、その2で紹介します。
>>次ページ(その2)へ
作成 2008年 5月19日
改訂 2017年 3月20日 HTML5対応