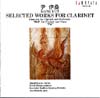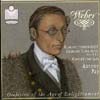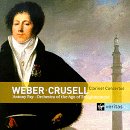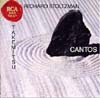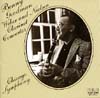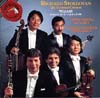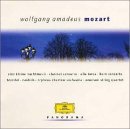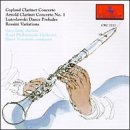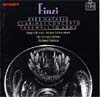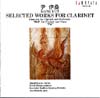 |
CDタイトル |
尹伊桑(Isang Yun)/クラリネットのための作品集 |
| 曲目 |
1.尹伊桑/クラリネット協奏曲
2.クラリネットとピアノのためのリウル
3.”ピリ”
|
| Cl. |
エドアルド・ブルンナー |
| 指揮者・オーケストラ(等) |
パトリック・トーマス指揮バイエルン放送交響楽団(1)
アロイス・コンタルスキー(ピアノ)(2) |
| CDデータ |
カメラータ東京 - 1996/02/21 CD ディスク枚数: 1 ASIN: B000050PRM |
| 感想 |
言ってしまえば現代音楽です。いわゆる咆哮する金管、炸裂する和音、爆裂する打楽器って感じなんですが、ブルンナーさんはリードミスも厭わない熱烈な演奏で迫ります。まさに鬼気迫る演奏!クラリネット協奏曲では中間部でなんとバスクラに持ち替えます。万人向けという気はしませんが、尹伊桑の切羽詰った感じ、暴力に対する抗う感情が感じられるようなところが僕は好きです。 |
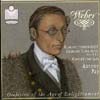
↓今はこんな感じの2枚組らしい?↓
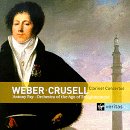 |
CDタイトル |
Weber/Clarinet Concertos 1&2 Concertino Op.26 |
| 曲目 |
1.ヴェーバー/クラリネット協奏曲第一番
2.同/クラリネット小協奏曲
3.同/クラリネット協奏曲第二番
|
| Cl. |
アントニー・ペイ(Antony Pay) |
| 指揮者・オーケストラ(等) |
エージ・オブ・インライトゥンメント管弦楽団(Orchestra of The Age Of Enlightenment) |
| CDデータ |
Virgin - #61585 / 1999/06/08 CD ディスク枚数: 2 ASIN: B00000J2QA
|
| 感想 |
アントニー・ペイさんはここでは1800年初頭の7つしかキーのついていないクラリネットの復元楽器を演奏しています。どちらかというとちょっと音ヌケ悪そうな気がしないでもないですが、素朴な味わいときらびやかさをを兼ね備えた演奏です。
今進歩した楽器があるのに、何故制約のある古い楽器を使うのか?往時をしのぶというのではなく往時の音色の素朴さをちょっとだけ垣間見られる、さりとて技巧的にちっとも違和感も感じないすばらしい演奏だと思います。
|
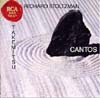 |
CDタイトル |
武満徹:ファンタズマ・カントス |
| 曲目 |
1.武満徹:ファンタズマ・カントス
2.(同):ウォーター・ウェイズ
3.(同):ウェイヴス
4.(同):カトレーンII
|
| Cl. |
リチャード・ストルツマン |
| 指揮者・オーケストラ(等) |
1.尾高忠明指揮BBCウェールズ交響楽団
2.アイダ・ガバフィアン(ヴァイオリン), フレッド・シェリー(チェロ), ピーター・ゼルキン(ピアノ),バーバラ・アレン(ハープ), ナンシー・アレン(ハープ), デビッド・フロスト(ヴィブラホン), リチャード・フィッツ(ヴィブラホン)
3.ロバート・ルッチ(フレンチ・ホルン), リチャード・シャンバーラン(トロンボーン), ドナルド・ボラー(トロンボーン), デビッド・フロスト(バス・ドラム)
4. アイダ・ガバフィアン(ヴァイオリン), フレッド・シェリー(チェロ), ピーター・ゼルキン(ピアノ)
2.4.のアイダ・ガバフィアン(ヴァイオリン), フレッド・シェリー(チェロ), ピーター・ゼルキン(ピアノ)そしてストルツマンは”タッシ”名義。 |
| CDデータ |
BMGファンハウス - 1994/09/21
CD ディスク枚数: 1
ASIN: B00005EG5K
録音:1:1992/06/02, 2-4:1978/10/16-20
|
| 感想 |
ファンタズマ・カントス、この曲は一つの協奏曲であると言えますでしょう。ただ早いパッセージでぐいぐいというものではないのですが、痺れるほど美しい曲であります。なんかこぉ、とてつもなく大きな暖かい宇宙にそっと置かれたような気がする部分とかあったり。スコアを立ち読みしたんですが、聞き耳以上に複雑。譜面が伝える音楽の限界をも感じるような(−_−)。リチャード・ストルツマンの歌心が前提となっているような気がしないでもないです。もっとも、最近ではザビーネ・マイヤーによるCDも出ているみたいです。クラリネットによる音楽表現の一つの到達点と言ってもいいんじゃないでしょうか?武満徹の死、それはどうしようもなく早すぎたと思います。 |
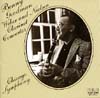 |
CDタイトル |
ウェーバー:クラリネット協奏曲 |
| 曲目 |
1.ウェーバー:クラリネット協奏曲第1番
2.ニールセン:クラリネット協奏曲
3.ウェーバー:クラリネット協奏曲第2番 |
| Cl. |
ベニー・グッドマン |
| 指揮者・オーケストラ(等) |
ジャン・マルティノン指揮シカゴ交響楽団
2.のみモートン・グールド指揮 |
| CDデータ |
|
| 感想 |
ニールセンのクラリネット協奏曲を聞いてみたくて数年前に買いました。ここではニールセンのクラリネット協奏曲について触れます。
ニールセンといえば6つの交響曲、特に第4番「滅びざるもの」で有名です(結構好き!)。クラリネット関連では管楽5重奏(木管5重奏)も作曲しています。でクラリネット協奏曲。ベニーさん、チョット音色が荒いです。なんというか、若干リップコントロールが緩いのか、音が割れてたりしています。そういう表現を狙っていると言われるとなんともはやですが、好き嫌い分かれるところでしょう。僕は好きではない。
曲は単一楽章ですが、急−緩−急の流れがあり、そういった意味では伝統的な楽章配置の名残はうけつつも、独自の様式をとります。クラリネットパートに関してはモーツァルトやコープランドに対してより一層複雑な技巧を用いることにこそ目的があるようです。差し込まれたカデンツァなど、高音から低音の移行とか、まさにクラ奏者泣かせなのがふんだんに。こおいうと、譜面買ってきて、制覇してやる!なんて空元気で気張ってみたりして。
楽曲はいろいろな局面を見せる意欲作であるとは思います。後期ロマン派的な濃厚な味わいもいいです。中間部の「緩」の部分ではちょっぴりショスタコーヴィッチ風味(注:ショスタコーヴィチよりも前に生まれた人です。1928年完成の曲です)。この曲についてこのCDで満足を得られるか?というとちょっと疑問です。現在、リチャード・ストルツマンの独奏によるCDも出ているみたいです。そちらも聞いてみたいなとは思います。 |
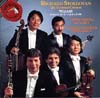 |
CDタイトル |
モーツァルト : クラリネット協奏曲&五重奏曲 |
| 曲目 |
1.モーツァルト:クラリネット協奏曲
2.同:クラリネット五重奏曲
|
| Cl. |
リチャード・ストルツマン |
| 指揮者・オーケストラ(等) |
イギリス室内管弦楽団(1)
東京カルテット(2) |
| CDデータ |
BMGファンハウス - 1999/11/20 CD ディスク枚数: 1 ASIN: B00005EGVQ
録音は(1)1990/11/5&6、(2)1990/7/22,23&25 リンクは再発CD
|
| 感想 |
ストルツマンさんは持ち前の明るい音色と微妙なリップコントロールで音色を微妙にコントロール。シュミードルさんと比べると、なんというか音にコクがあるという気がするんです。聞いたところによるとストルツマンってダブルリップアンブシャーとか。上唇のウラ痛くないのかな。
協奏曲ではカデンツァを入れています。ただし、超絶技巧の限りを尽くすたぐいではなく、歌うということに重きをおいたカデンツァです。
なんというかある意味特殊な吹き方なんですけど、こういう独特な音色でありながら納得してしまう演奏素晴らしいです。そういえばフルート、サックスでは一般的となっているヴィヴラート、クラリネットでなかなか一般化しないのは何故なのでしょう?ストルツマンはそのヴィヴラートも入れつつ微妙な音色コントロールを聞かせます。 |
 |
CDタイトル |
モーツァルト:交響曲第25番、交響曲第29番、クラリネット協奏曲 |
| 曲目 |
1.交響曲第29番
2.交響曲25番
3.クラリネット協奏曲 |
| Cl. |
ペーター・シュミードル |
| 指揮者・オーケストラ(等) |
レナード・バーンスタイン指揮ウィーンフィルハーモニー |
| CDデータ |
ユニバーサルクラシック(グラモフォン)- 1990/06/25 CD ディスク枚数: 1 ASIN: B00005FHVU Amazonでは在庫切れの模様・・・録音年月は1987/9
輸入盤はある模様。なんつって、僕も10年ほど前に輸入版で買いました。だって国内盤より安いし。なんで国内盤のほうが高いのかねぇ。はぁ。
|
| 感想 |
ぶっちゃけ、このCD買った理由は、バーンスタインがウィン・フィルを指揮していること、そして僕の大好きな29番交響曲を演奏していることであった。おまけにクラリネット協奏曲が入っているし、という気分でした。今日改めて聞きなおして、どうして当時はこのクラリネットの音色に驚嘆しなかったんだろう、と愕然としました。変なたとえですが、みずみずしく弾けるぷりんぷりんとした、明朗闊達でヌケのよい音という訳のわからん表現しかできません。僕は世界中のオーケストラの主席奏者が誰でなんていうことは全く知らないので、こういう人がオーケストラの主席であるということを全く認知しておらなかったわけです(ただ例外的にNHK交響楽団の主席奏者であった浜中浩一さんは知っています。なぜなら、母校の大先輩だから!あとひょんなことからカール・ライスターさんがベルリン・フィルの主席であることも知ってはいます。)。
今更ながら、ペーター・シュミードルさんの音を追っかけてみようかと思います。遅いって。使用楽器はHammerschmidt/Wattensとあります。エーラー式でしょうか?これを吹いたらこの音に誰でもなれるのなら、喜んでローン組みます。ってこれを書きながら、カール・ライスターさんが吹くプーランクのクラリネット・ソナタを意地悪く聞いていたりします。
|

↓
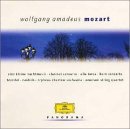 |
CDタイトル |
モーツァルト:クラリネット協奏曲 ホルン協奏曲第1番・第4番
↓
(現在、モーツァルト:作品集(2)に所収) |
| 曲目 |
1.クラリネット協奏曲
2.ホルン協奏曲第1番
3.ホルン協奏曲第4番
↓
現在、以下の曲目で2枚組みのCDになっています。
1.クラリネット協奏曲イ長調K.622
2.ピアノ・ソナタ第11番イ長調K.331「トルコ行進曲付き」
3.セレナード第13番ト長調K.525「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」
4.セレナード第6番ニ長調K.239「セレナータ・ノットゥルナ」
5.フルートとハープのための協奏曲ハ長調K.299
6.ロンド イ短調K.511
7.弦楽四重奏曲第17番変ロ長調K.458「狩り」
8.ホルン協奏曲第4番変ホ長調K.495
|
| Cl. |
チャールズ・ナイディッヒ(バセット・クラリネット) |
| 指揮者・オーケストラ(等) |
オルフェウス室内管弦楽団 |
| CDデータ |
POCG-1221(423 377-2)
↓
ユニバーサルクラシック - 2000/11/22 CD ディスク枚数: 2 ASIN: B00005HO1S
クラリネット協奏曲録音年月、僕のCDで1987/3
|
| 感想 |
ここでナイディッヒ(ナイディック)さんはバセット・クラリネットを吹いています。バセット・クラリネット、簡単に言えばクラリネットの最下音記譜上EだったのをCまで最下音を拡大したクラリネットのこと(何を今更、という方、ごめんなさい)。本当は、モーツァルトに委嘱したアントン・シュタートラーはこの特殊なクラリネットのための協奏曲をモーツァルトに委嘱したわけらしく、そういった意味ではこの楽器を用いることが「正統」。しかし、一般人がこの楽器を手に入れるのは至難の業だし、一般人は普通のクラリネットで頑張ろう。
ナイディッヒさんの演奏は心地よく即興的フレーズを織り交ぜながらの本当に楽しげな音色。そして、バセット・クラリネットならではの低音を聞かせる譜面を再構成したものによっている。確かに、あそこの部分通常のクラリネットでオクターブずれて、ん?と思わせていた部分が低音からせりあがったりするとなるほど!と膝を打ちたくなる。しかし、そういう学究的なことはどうでもよくなる、実に楽しく即興性に富んだ、ノリノリな演奏です。しかも、ナイディッヒさん、カデンツァをご自分で作っていて、あぁ、協奏曲は自分の技巧を観客に魅せるためのものだったのよね、ということを再認識させてくれます。いつからクラシックではこの「即興演奏」が封印され、他人が作ったカデンツァを演奏するようになったのか、は調べていないのでわかりませんが。そのカデンツァの区切りからオーケストラの演奏が再開されるあたり、指揮者もいないオルフェウス室内管弦楽団が何の違和感もなく合わせて演奏している。現在では2枚組み、しかもクラリネットと全然関係のない曲ばかりならべられているから、購買意欲は損なわれるでしょうが、この演奏は1度はなんらかの手段で聞いておいても損はないと思います(輸入版でなら1枚のでクラ協、ホルン協1,4のやつがあるみたいです。上の方のCDジャケットをクリックしてみてください。)。 |
 |
CDタイトル |
Benny Goodman Collector's Edition |
| 曲目 |
1.Bernstein:Prelude, Fugue & Riffs
2.Copland:Concerto for Clarinet and String Orchestra (With Piano & Harp)
3.Stravinsky:Ebony Concerto: I-Allegro Moderato
4.Gould:Derivations for Clarinet and Band: I-Warm Up
5.Bartok:Contrasts
|
| Cl. |
Benny Goodman(ベニー・グッドマン) |
| 指揮者・オーケストラ(等) |
Columbia Jazz Combo(1,3,4)
Columbia Symphony Orchestra(2)
Joseph Szigeti(violin on 5)
Bela Bartok(piano on 5)
Leonard BernStein(cond, on 1)
Aaron Copland(cond, on 2)
Igor Stravinsky(cond, on 3)
Morton Gould(cond, on 4) |
| CDデータ |
CBS - ASIN: B0000026F3(輸入盤) |
| 感想 |
コープランドのクラリネット協奏曲の委嘱者にして初演者であるベニー・グッドマン。ベニー・グッドマンはスウィング・ジャズの名クラリネット奏者として余りに有名。が、もちろんクラシックのトレーニングを受けた後にジャズへ転向したわけで、でもどこか純粋クラシックのクラリネット奏者とは違う雰囲気があります。正直、音色であるとかは純粋クラシック音楽的立場で言えば、あまり参考にはならないかもしれません。しかし、それを度外視した音楽の推進力(いわゆるグルーヴ感)であるとか、歌心と言う点では目を開かせてくれるものがあるのではないでしょうか。2と5を除けば(だいたい、前奏曲、フーガとリフなんてタイトル、アメリカ人以外つけられないでしょう。さすが、バーンスタイン!)、純粋なおクラシックな曲はありません。がこういったことも表現可能なクラリネットという楽器、正直選んでよかったと僕は思うわけです。
演奏は全曲作曲者が演奏に参加しているというマニアックなつくり。5.だけはバルトーク生前の(!)演奏故、モノラルです。、なお、Amazonでクラシックコーナーでいくら探してもでてきません。ポピュラー音楽コーナーで探さないと。クラシックよりの楽曲とはいえ、奏者がベニー・グッドマンですから。 |
 |
CDタイトル |
コープランド:エル・サロン・メヒコ |
| 曲目 |
コープランド:エル・サロン・メヒコ
同:クラリネット協奏曲(クラリネット、弦楽とハープおよびピアノのための)※
同:劇場のための音楽
同:管弦楽のための《コノテーションズ》 |
| Cl. |
スタンリー・ドラッカー※ |
| 指揮者・オーケストラ(等) |
レナード・バーンスタイン指揮ニューヨークフィルハーモニック |
| CDデータ |
ユニバーサルクラシック(グラモフォン) ASIN: B00005FJ9N |
| 感想 |
クラリネット的見地からいえば、協奏曲のみ。強いて言うなら、エル・サロン・メヒコのEbクラでしょうか(^^;;僕が一番好きなクラリネット協奏曲、しかも指揮がバーンスタイン!今のところこの演奏が一番好き。曲の委嘱者、ベニー・グッドマン自身の演奏のCDも持っているが、それは後ほど。この曲、緩・急の2部構成で、この「緩」部分でどれだけうまく歌えるかというのがとても重要だと思う。この演奏ではバーンスタインの晩年の演奏にありがちな落としめのテンポでたっぷり情感込めて歌っています。ただ、こういうじっとり型が嫌いな人にはちょいキツイかも。その他の曲は聞きなれないものだが、一聴の価値あり。とくにコノテーションズはコープランドにもこんな曲(ちょいゲンダイオンガク風)があるのかと |
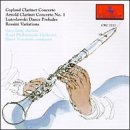 |
CDタイトル |
Copland: Clarinet Concerto(The Art of Gary Gray) |
| 曲目 |
Copland: Clarinet Concerto;
Lutoslawski: Dance Preludes;
Arnold: Clarinet Concerto No. 1;
Rossini: Variations for clarinet and small orchestra in C op.109 |
| Cl. |
Gary Gray |
| 指揮者・オーケストラ(等) |
Harry Newstone(cond)Royal Philharmonic Orchestra |
| CDデータ |
? ASIN: B0000057XC |
| 感想 |
本当のところ、クラ協ではコープランドが一番好き。それにつられてその他にもクラリネット関連曲がつまっているので購入。ルトスワフスキーはこの時点ではまだ前衛バリバリではない。「ピータールー」で有名な人アーノルドの協奏曲はそんなに面白くない。ロッシーニの変奏曲という珍品も。全体的に控えめな演奏という印象。 |
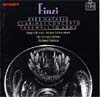 |
CDタイトル |
FINZI:DIES NATALIS/FAREWELL TO ARMS/CLARINET CONCERTO |
| 曲目 |
Finzi: Dies natalis(Cantata for high voice and strings)
Finzi: Farewell to Arms(Introduction and Ara for tenor and strings)
Finzi: Concenrto for clarinet and strings |
| Cl. |
Michael Collins |
| 指揮者・オーケストラ(等) |
Richard Hickox(cond.)City of London Sinfonia |
| CDデータ |
Virgin classics VC7 90718-2 |
| 感想 |
クラリネット協奏曲漁りをしていたころに偶然発見。哀愁漂う曲調がgoo。クラリネットのCollinsもほどよい透明感とほどよい情熱感でいいです。Virgin classicsって廃盤?Finziのクラ協奏曲、最近ではNAXOSなどからいろいろ発売中。1枚は持っていたい。 |