例えばヴェーバーのクラリネット小協奏曲のクラソロはこう始まります。
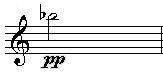
おらおら、こんな音弱音で始められるか!喧嘩うっとんかい!といくら逆ギレしたところで作曲者は要求しているんだから仕方ありません。楽器を知らねぇなと嘯いてもせん無いこと。楽器の限界を超えさせたい作曲者はいっぱいいるわけでそのおかげで日々進歩があるわけで。
ところが、ある日、合奏曲でこれが登場しました。シバの女王ベルキスの2ndクラだったと思います。そもそも私2ndって一番嫌いです。何が嫌いって1stに和音付けする、1stは歌わなければならない、そこへ3和音の3度を割り当てられる割合が非常に高い→低めにとる→眉間に皺が寄る→神経が磨り減る→歌いながらそんなに神経使えるか!その上指揮者に聞こえないと言われるということで。3rdはいいですよ。低音を気持ちよく吹けたりしますからね。もっとも自分は目立ちたがりなので1stが一等好きですけど。1st、3rd、(バス)、(Eb)2ndの順かな。。。
横道にそれました。このB♭を弱音でしかも落ち着き払った音で吹く難しさといったら。。。まずB♭を吹く指は通常下の3つが考えられましょう。
この中で自分の中の感想は
- の音が最も好き。でも使用範囲がぐっとせばまる。
- 使用頻度が高い。中庸な感じの音と言っていいのか。
- よっぽどの時の変え指。音抜けわろし。しかも上管・下管を結ぶジョイントの調整をきちんとしないと間抜けな音が出る。これは以下のフレーズの救世主としてはかなり重宝する。

で、先のB♭について。ここでの重要ポイントは「静かに」かつ「突拍子もなく出さない」いろいろ試しました。1.2.3.どれも使える状況ですもの。1.2.の両方で試したのですが、腹筋がつるつる。ppでこいつを吹くのはどうもまずい!どう吹いてもびびったような音が出ている!こんなんじゃだめだ!!!で3.を使って息を多目に吹き込んで(勿論ppで)吹いてみる。あら不思議。今まで音抜けわろしと思っていた指使いがちょうどよいソフトな響きでこの場面に非常にマッチしました。以来病みつき。さらに例の上管・下管のキーを結んでいる部分の調整により一層神経を使うようになりました。
この時、音大に通う人が賛助してくれていたのですが、その人も同じ指使いをしていました。音大生がやるんだから間違いなし!と妙な自信を持ってしまった。指使いに絶対なんてないですね。うん。いろいろその場の状況に合わせて選択肢を持っておくというのは非常に面白いです。ただし、セクション組む人とよく話し合って統一はした方が音色統一のためにはよいと思います。
じゃぁこれの半音上のBやさらに上のC、半音下のAはどうする?と言われたらどうしよう。もうあきらめて弱音を吹くための腹筋を鍛えるしかないな・・・(逃げ)