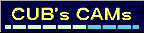2020/9/16(水)
α7Cての、これはマズいぞ。高さが丁度バルナックのそれ、幅はやや詰まって厚みがグリップ抜きでも凄そうだが、あの高さ、まことに心地が好い。M3 から M6クラシックへ至る・・・・・ついでにコンタG1 も・・・・・より、 少しだけ背が低いのだが、その差が掌の収まり感に直結して、構える方向でボディの左側を、左手の親指を上に、人差指他を下にして、一日中掴んでいたい程に、心地好いのである。 ◆フルサイズで裏面照射で、古いレンズ付け放題・・・・・そんな夢想をしてから随分経つが、エプソン R-D1 系のフルサイズ化を待っていたら消えてしまうし、α7 が出た時は衝撃的だったが高かったし先行き判らなかったし、 よくよく考えるとちょっと遊んで終わりそうなものに投資が見合うのか・・・・・とウダウダ考えるうちに半ば忘れてしまっていたのだったが、α7C、今回グイっと引き戻された感。 ◆制約はあろうが、アダプターで EFレンズ付けたっていいのである。とはいえ RF機代わりとしてコンパクトにしたいから、常用域は専用で固めてもいい。28-60mmなど、まさにライカで持ち歩いてたようなカンジだし、 これ 1本でイケる。クロップで 135mmm 相当は割り切るとしても、90mm 相当なら十分許容できるだろう。それに Gマウントのビオゴン21mm を加えれば、大体事足りる。 なんなら同じくゾナー90mm もあるし、もう G1 代わりで・・・・・ホロゴンの後玉が干渉しなければ、言うことなしなんだが。
2020/9/3(木)
HX90V とシグマ C18-200mm、両方上がってきた。HV90V は高く付いたナァ・・・・・買い値の半分強よ。一瞬の不注意がコレ。外したリングも付いてきた。ていうか、これだけ? これ交換しただけで?
シグマ C18-200mm の方は結局、AF駆動系交換のようだったが、再修理ということで追加料金ナシ。元々はズームの不具合として依頼したものだったが、依頼分しか診ないとは考えにくく、
最初から不具合があったなら見積もりで見落としたことになるし、或いは修理の分解組付けの際におかしくなっ・・・・・真相は定かでないが、一度完成しましたと返した以上は、今更取れないということか。
早速動作を確認したが、端から端までツーツーと動いた。動作だけは、大丈夫、多分。
2020/8/30(日)
富津岬から横須賀を出港するしらせを、と 90D にシグマ C150-600mm、更に専用テレコンを加えると、ピントが合わん。ツーツーと引っ掛からないのではなく、合ったフリしてズレてるという、ややこしいやつ。
マスターレンズ開放 F6.3 のところテレコンで 1段落ちて F9 相当、EOS7D2 では、本来 F8 まで対応のところ合ったらめっけもの、という具合だったし、多くを望むものではなかったが、
まあこのあたりは、ミラーレス導入まで辛抱か。
2020/8/27(木)
店頭で EOS R5 に初めて触れる。振って連写して感触を見たが、フレームレートを上げても違和感は残るが、なんとかなる、のかな。クロップの手動切替が意外と手間。
解像度と一緒に切り替える・・・・・フルで45MB常用は流石に・・・・・となると、ん゛ー。
2020/8/25(火)
HX90V の修理見積、安いのだったら買えちゃうな・・・・・とはいえびっくり箱ファインダーこと EVF が無ければ意味ないし。修理続行。
2020/8/13(木)
シグマ C18-200mm、AF駆動不良の件であらためてヨドバシへ持って行く。その前に売り場のサンプルで動作を確認・・・・・ほーら本来はこうなんだよ。預ける前もフツーにこうだったよ。
次に修理コーナーへ持ち込んだが窓口氏、カメラに疎いのか情報伝達に不安。修理上がりから日が経ってますが・・・・・ってずっと梅雨明けなかったし、そこは察してくだされ。
愚考するに、今回のズーム機構の修理の際、分解組立の過程で AF駆動系にも触れぬハズはなく、ここらの組付けの具合ではないかと、思うのだがな。駆動系もイカレてましたなんて後出しは、なしな。
◆RF800mm/F11、絞りないのか。今頃気付いた。おもしろレンズ工房ですか、「どどっと800」ですか。
◆尤も、開放 F11 からまだ絞るかという話ではあるのだが、とりあえず、レフレックスみたいなもんと思ってれば良さそうだ。IS はあるし、絞りとどっちを取ると言われれば、ISを取る(笑)。
そもそも絞りが欲しい時とは?・・・・・ピントや描写の他に、シャッター速度を落としたい場合がある。プロペラや回転翼と止めずに撮るには 1/125 とか 1/250、場合によってはもっと遅くしたいところなのだが、
晴れ順光で ISO100 まで落としても、やや際どい。保険でNDフィルター、或いは PL でクッキリというのもアリかもしれないが、追いながら目まぐるしく変わる光線状態に合わせての脱着など、
現実的ではない・・・・・いや、プロペラ機を追うような機会など、この先ほぼなくなるか(涙)。
2020/8/8(土)
シグマ C18-200mm、修理上がり後 1ヶ月を経て、KissX9 に着けお気楽モードでようやく持ち出す・・・・・と、ピントが合わない。というより、端から端まで往復して合いませ−ん、
ならまだ解るが、ピントリングが途中で諦めてしまう感じだったり、ちょこ、ちょこ、と動いてようやく合わせに行く。モーターに変な負荷がかかってるんじゃ、あるまいな。
90D に着けても同じ。修理前はこんなでなかったハズ。
2020/8/7(金)
ふと取り出した HX90V、コントロールリングがやけに渋い・・・・・あ、この間落としたんだった(汗)。見たところ他の動作や写りに影響なかったからホッとしてたが、このリングは触ってなかったな・・・。
もう 2年半以上使っているから、修理するか買い換えるか悩ましいところだが、買った方が安いですよー、という程の廉価機でもなし。なんだーかんだーで馴染んでしまってるし。
◆後継機、あるんだな。HX99。内部処理などは判らないが、基本スペックは一緒らしい・・・・・尤も、コンデジなんてもうそんなもんだ。いや、GPS が抜けてる。
位置情報が必ずしも欲しいわけではないが、時計合わせに丁度いいのだな・・・・・といいながらコイツに限っては殆ど使ってなかった。まあいっか。
殆ど同じモノを買うのもつまらん、という気もしてキヤノンのパワーショットの競合帯を見ると、40倍ズームなんていうシロモノもあったりするが残念、EVF付がない。
これなー、もう離れられないんだわ。しゃあない、修理に出そうか・・・・・この盆前の間の悪さ。不在中は最悪、WX350 再登板か。
2020/8/5(水)
梅雨も明けたことだしと、ぼちぼち夜の近所鉄など。ただまあ、ここまではガマンするかと ISO25600 まで上げもするが、EOS6D2 はどうしても厳しいカンジで、今更 5D4 でもあるまいし、
R5 を 22MP 級で常用してれば・・・・・R5 は無理でも R6 の高感度番長ぶりもどうか。EFレンズで旧来の EOS 並に使えればそれでよく、あと EVF のクセ次第か。
2020/7/19(日)
ネオワイズ彗星。天気予報を睨みながら、あわよくば撮れるかとギャンブルのつもりで海ほたるへ。日没後肝心な方角と仰角に嫌がらせのような雲が漂い始める中、用意だけはと、EF100-400mm2 に EOS90D、
リモートケーブルを・・・・・げっ、コイツ N3端子でなくて、ステレオミニプラグ様の E3だったのか・・・・・Kiss クラスだけと思ったら、2桁シリーズもこっちだったんかい。面倒臭いな。
◆まあ手押しでもなんとかなるシチュエーションでは、ある・・・・・先程からの邪魔な雲は薄れたものの大気の抜け具合が思わしくなく、肉眼では星が全く見えないので目視は諦め、
凡その位置は判っているので、ままよとソレと思しき方向へサーチをかけるようにシャッターを切りまくると、ぼう、と尾を引いた光点が写り込んだ。タリホー♪ それっとズームを寄せながらフレームを追い込んで行き、
大気の好転を祈りながらシャッターを切り続けたが、逆にどんどん苦しくなって行き、引きで撮る余裕もないままに、終了。ソレと判る形で捉えられたのは、ヘール・ボップ彗星以来四半世紀近くを経ていた。
あの時のようにクッキリと、再び、今度はデジで撮ってみたいものだが、こればかりは気長に待つしかない。
2020/7/16(木)
今筑西市で組立中の科博 YS-11 の様子を見に出かけ、一応、と持って来てた忍者レフが早速活躍。二重ガラスで超広角で、というのはそれでもなかなか厳しかったが、ガラス面と光軸が垂直とは限らないが、
長方形の辺をガラス面に押し付け密着、これがなかなか具合が良い。787用(笑)四角タイプで正解だったか。畳んでもそこそこ大きいように思われたのが、ハクバのアクティブスリングバッグの、
二階部分にカメラ共々収まった。なんだこれなら気軽に持ち歩けるではないか。その窓の構造からこれまでどうしても遮光ができなかった、飛行機に乗るのが楽しみで・・・・・随分乗ってないな。
2020/7/14(火)
ガラス越しの撮影というのも時々あって、帽子や上着を被せたりして映り込みを凌いできたが、ふと思って前から目に止まってた、忍者レフ、買ってみた。最初円形の大小で迷ったが、
ボーイング787用と称する(笑)四角いの・・・・・撮影フォーマットが長方形なのだから、円形よりは合理的な気がして。貯まってたヨドバシのポイントを、ここでも吐き出す。
2020/7/9(木)
EOS R5、R6 他、正式発表。いよいよ本格攻勢である。EOS における「5」とは、フラッグシップを仰ぎながら、次世代先取りな機能満載で攻める、言いようによっては斬込隊長的な役回り。
EOS-1(無印) の下での EOS 5 はマルチ測距であり視線入力であったし、今とは違う命名法で次の代は EOS 3 に譲ったが、遡れば F-1 に対する A-1、NF-1 に対する T-90、もこれに相当する。
デジでは EOS-1Ds2 の下で初代 EOS 5D、スペックで上を食うということはないものの、35mm フルサイズの裾野を広げる戦略機と言えた。6D が出てからは裾野はそちらへ任せ、
一方 EOS-1D 系が DX に合流すると、5D は高解像度を守備範囲とする。スピードとタフの 1DX、表現の 5D、単なるヒエラルキーの上下関係ではない。
◆EOS の数字による命名法則は、銀塩時代のごく初期を除いてほぼ変わっておらず、「1」を頂点に、1桁グループが続き、2桁、3桁と裾野へ向かう。商品寿命の短いデジタルの時代に入ると、
1桁シリーズの名称は「世襲制」となり、位置付けが固定化した。一眼レフの 5D、6D はそのまま R5、R6 になるのであり、すると当然に、R1 は現在空席と解されるわけだが、
R5、は当面のフラッグシップとして、ここでも斬込隊長を演じることになる。R や RM がどこか煮え切らない、市場への打診といった印象ばかりだったのに対し、今回は迷いがない。
◆ソニーがα7以降伸してきてからしか知らない層には、キヤノンやニコンは時代遅れにしか見えないらしいが、それは「新しい方が全面的に優れている筈だ」という先入観でしかなく、
ちょっと撮ってみれば判ることも知らないに過ぎない。一眼レフの覇者であるキヤノンやニコン・・・・・独自路線のペンタは横に置いておく・・・・・は、
ミラーレスに追い付けないのではなく、古い技術にしがみ付いていたわけでもない。「イノベーションのジレンマ」は避けて通れない話ではあるが、時期尚早なものに急いで飛び付く理由がなかったのだ。
優位性の残る間は一眼レフでやるだけやって、その一方でミラーレスの熟成を進め、タイミングを見て移行する・・・・・要は今がその時。
◆APS-C に未練タラタラな身としては、その要求の大部分は超望遠へのそれであって、現状手持ちの玉としては最長 600mm、35mmフル換算1.6掛けで 960mm、やっぱこれくらいは欲しいわけですよ。
更に x1.4 テレコン着けることも、たまーに、ある。しかしフルサイズで 1000mm越えなど、まずはムリ。R5 で APS-C にクロップするとおよそ 18MP、初代 EOS7D 程の解像度で、
今となっては 90D の 30MP クラスには遠く及ばない、ということになる・・・・・30MP のアウトプットが常時必須なのか、という話は置いておく。
◆とそこへ、単焦点の RF600mm/F11、RF800mm/F11 なんてモノが現れるわけである。実売価格は判らないが廉価を売りにしているらしく、銀塩時代で言う 400mm/F5.6 くらいのノリなのだろうか。
無理せずシンプルにバランスを取る方向、F11なんて一見トンデモスペックに思えるが、デュアルピクセルCMOS の時代である、測距センサーがバンザイしてだんまりを決め込むこともない。
条件さえ許せば大体 F11 くらいには絞るものであるし、開放で十分な画質が保て・・・・・そこが問題なのだが・・・・・さえすれば、問題ない。
◆で、である。800mm は 600mm の約 1.3倍、奇しくもこれは、EOS-1D 系 APS-H と APS-C とのサイズ比と概ね等しい。換言すれば APS-H の 800mm は、APS-C の 600mm と画角が同等なのだ。
そして、仮に R5 の 45MP センサーで APS-H 相当にクロップしたとすると、26MPちょい! 7D2 以上 90D 未満。つまりこれは、EOS R5 + 800mm で、画角、解像度共に、
概ね現用の EOS90D + 600mm に近い像が得られることを意味する。スバラシイ・・・・・計算合ってるよな?
◆実際には R5 のクロップ機能に APS-H サイズはないから、フルサイズからトリミングすることになるが、45MP というトリミング耐性のなせる業ではある。データの肥大化を甘受した上で、
切り取り放題という使い方であれば、APS-C機のことは一旦、忘れることも出来る・・・・・クロップが刻めればなあ。そもそも RF800mm/F11、いくらなんだろ。
2020/7/4(土)
シグマ C18-200mm の修理上がりを回収、貯まってたヨドバシのポイントで賄う。出番いつだろか。
2020/7/3(金)
ヨドバシで買い物したら、レジ袋が白黒反転してる。どうもレジ袋有料化を受けて、素材を変えてその対象外にしたらしい。ナルホド。黒いヤツとっとくかな。
2020/7/2(木)
ふと、EF50mm/F1.8STM でちょっと絞るなら、パンケーキ EF40mm/F2.8STM 開放ではどうだろう、と思って、夜のヘッドライトゴーストバリバリなところへ再チャレンジしてみると、
これが結構、塩梅よし。あくまで比較論だが、そうだったかぁ・・・・・抑えたスペックは強み、か。
もっと前へ